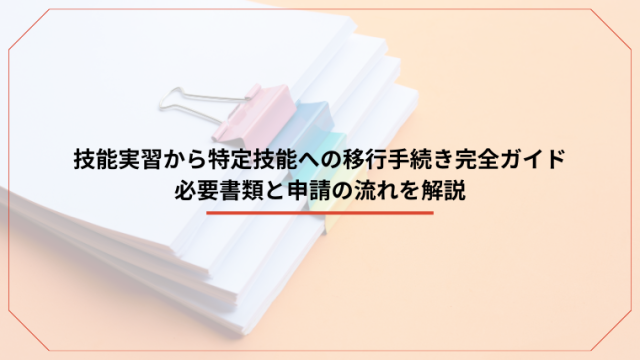ビルクリーニング分野で技能実習生の受け入れを検討する企業からは、次のような悩みが多く聞かれます。
- 制度の仕組みや対象業務が正確に分からない
- 受け入れに必要な条件や手続きが複雑で不安
- 定着やトラブル防止のためにどんな体制を整えるべきか知りたい
本記事では、ビルクリーニング分野における技能実習制度の概要から、受け入れ条件・申請手続き・実務上の注意点までを整理して解説します。正しい制度理解と準備を進めることで、安心して技能実習生を迎え入れ、現場に定着させるための実践的なポイントを把握できます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
ビルクリーニング分野の技能実習制度とは?

ビルクリーニング分野は、2018年に技能実習制度の対象職種として追加されました。これは、施設や建物の衛生管理を行う清掃作業において、一定の技術水準と知識を要する業務であることが認められたためです。
技能実習制度は、開発途上国の若者に日本の技術・技能・知識を移転することを目的とした制度であり、「単純労働力の受け入れ」ではない点に注意が必要です。特にビルクリーニングは、衛生管理・安全作業・品質維持といった面で、職業としての専門性が重視されています。
対象となる作業範囲
ビルクリーニング分野で技能実習制度の対象となるのは、主に以下の作業です。
- 事務所・商業施設・病院・学校などの屋内清掃
- 床、カーペット、ガラス、トイレなどの定期清掃および日常清掃
- 機械を使用した清掃(ポリッシャー、バキューム等)
ただし、屋外清掃(除草・落ち葉処理など)や、家庭向けの家事代行業務は対象外です。実習計画を立てる際は、この作業範囲を正確に理解し、逸脱しないように注意する必要があります。
技能実習1号~3号のステップ
ビルクリーニング分野における技能実習のステップは以下の通りです。
| ステージ | 期間 | 内容 |
| 技能実習1号 | 最長1年 | 入国後に基礎的な実習(日本語・生活指導含む)を受ける |
| 技能実習2号 | 最長2年(1号と合わせて通算3年まで) | より高度な作業の実習(実地作業中心) |
| 技能実習3号(移行対象者のみ) | 最長2年(通算5年まで) | 成果が認められた場合に追加実習が可能 |
各ステージの移行には、技能評価試験の合格が必要です。試験は学科と実技で構成され、受け入れ企業は試験に向けた支援体制を整えることが求められます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習生を受け入れるための企業の要件と準備
技能実習生を受け入れる企業には、法令で定められたさまざまな要件があります。これは、技能実習が「労働力確保」ではなく「技能移転」を目的とした制度であるため、実習先企業にも教育・指導体制の整備が求められるからです。準備不足のままでは受け入れが認められない場合もあるため、事前に必要な要件を確認し、体制を整えておくことが重要です。
受け入れ企業に求められる主な要件
受け入れ企業が満たすべき主な条件は以下の通りです。
- 技能実習責任者の選任
技能実習制度に関する知識と責任を持って全体を管理する責任者を置く必要があります。技能実習責任者講習の受講が必須です。 - 指導員と生活指導員の配置
実習現場で技能を教える「指導員」と、生活面の支援を担当する「生活指導員」をそれぞれ配置する必要があります。 - 実習計画の策定と認定
実習生ごとの具体的な技能習得計画(技能実習計画)を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)から認定を受けなければなりません。
※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。参照 ▶ 外国人技能実習機構 - 適正な労働環境の提供
最低賃金の順守、36協定の提出、労働時間や休日の管理など、労働法令に則った雇用環境を提供することが義務付けられています。
宿舎や生活環境の整備も必須
技能実習生が安心して生活できるよう、生活環境の整備も必要です。主なポイントは以下の通りです。
- 宿舎の確保と環境整備
プライバシー確保、十分な広さ、清潔な水回り、エアコンや暖房などの生活設備が求められます。 - 生活オリエンテーションの実施
入国後、実習前に日本のルールや生活マナー、防災・医療情報などを伝えるための教育が求められます。 - 緊急連絡体制の整備
体調不良やトラブル時にすぐ連絡できる体制、翻訳・通訳支援ができる体制も整備しておく必要があります。
受け入れにあたっては監理団体(組合)と連携して準備を進めるのが一般的ですが、最終的な責任は実習実施者である企業にあるため、要件の理解と対応は不可欠です。
技能実習生の要件とビルクリーニングでの試験制度
受け入れ対象となる外国人の条件
ビルクリーニング分野で技能実習生を受け入れるには、実習生自身が一定の条件を満たしている必要があります。主に以下のような要件があります。
- 18歳以上の健康な男女であること
- 技能実習制度に基づく送り出し機関を通じて選抜されていること
- 母国での職歴や学歴により、ビルクリーニング分野に関連する基礎的な知識・経験があることが望ましい
これらの条件に加えて、受け入れ先企業の職場環境や仕事内容が、技能実習の目的に合致していることも重要です。
日本語能力の目安
実習生には日常会話レベルの日本語能力が求められます。必須ではありませんが、入国前に日本語教育を受け、N5〜N4程度の日本語能力があると、職場での指導や生活面でのトラブルを防ぐ上でも有利です。
監理団体や送り出し機関によっては、入国前研修で日本語教育が含まれている場合もあります。
技能実習評価試験(基礎級・随時3級)の概要と内容
技能実習制度では、実習生の技能習得状況を客観的に確認するため、段階ごとに技能評価試験が実施されます。ビルクリーニング分野では、主に以下の2つの試験が行われます。
- 基礎級試験:入国後6〜8ヶ月以内に実施。清掃の基本動作や用具の使い方など、初歩的な技能を確認します。
- 随時3級試験:実習2年目の前半に受験。業務全体の理解と実務能力の定着を評価します。
いずれも、実技試験と筆記試験の2部構成となっており、合格により次のステージへの移行が可能になります。
試験の実施方法・合格基準・試験対策の支援
試験は、全国の認定試験会場で定期的に実施され、日程や会場はJITCOや技能評価機関からアナウンスされます。参照 ▶ JITCO 公益財団法人 国際人材協力機構
- 合格基準:実技・筆記ともに60%以上の得点が目安
- 試験言語:母国語または日本語(選択可能な場合あり)
監理団体や支援機関の多くは、実習生に対する事前の試験対策講座を提供しています。企業側も、実地での指導や練習機会を積極的に設けることが、合格率向上につながります。
ビルクリーニング分野における技能実習生の作業内容
 実習対象となる業務の範囲と例
実習対象となる業務の範囲と例
ビルクリーニング分野において、技能実習生が従事できる業務は制度上で明確に定められています。主な作業は以下の通りです。
- 建築物内外の床・壁・天井の清掃
- トイレ・洗面所などの衛生設備の洗浄および消毒
- 窓ガラスや手すり、エレベーター内の拭き掃除
- 掃除機、モップ、ポリッシャーなど各種清掃用具の使用
- 廃棄物の分別・収集・運搬
これらは「ビルクリーニング作業」に該当し、技能実習の対象業務として認定されています。
危険を伴う作業や認められない業務の区別
技能実習生には、危険または高度な専門性を要する作業は原則として認められていません。たとえば以下のような作業は対象外です。
- 高所作業車やゴンドラを使用した高所窓清掃
- 建築現場や工場など、ビルクリーニング以外の清掃業務
- 特殊な薬剤・機械を用いた専門的な清掃(例:外壁洗浄など)
実習生が本来の業務以外に従事した場合、不適切な受け入れとみなされるリスクがあります。監理団体と連携し、業務内容が制度の範囲内であるか常に確認しておくことが重要です。
実習計画書に基づく段階的なステップとOJTの流れ
技能実習は「実習計画書」に基づき、段階的にOJT(実地研修)を進める形式で行われます。
- 第1号(1年目):基本的な清掃作業の理解と安全衛生管理の習得
- 第2号(2〜3年目):作業範囲の拡大、効率的な業務遂行、後輩指導の基礎など
実習先企業は、計画書に沿って定期的な評価とフィードバックを行い、技能の着実な習得を支援する必要があります。
技能実習生の受け入れ手順と必要な準備
受け入れ企業が行うべき基本的な流れ
技能実習生を受け入れるには、以下のようなステップで手続きを進める必要があります。
- 監理団体(組合)への加入・相談
技能実習制度では、ほとんどの企業が監理団体を通じて実習生を受け入れます。まずは業種に対応した適切な団体を選び、制度の概要や流れを確認します。 - 実習計画書の作成と認定申請
実習生が行う作業内容・教育体制・評価方法を明記した「技能実習計画書」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に申請・認定を受けます。
※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。参照 ▶ 外国人技能実習機構 - 受け入れ準備と事前教育
実習生の住環境や労働環境の整備を行い、必要に応じて受け入れ前の事前講習(日本語や生活指導)も実施します。 - 入国・配属・実習開始
実習生の在留資格(技能実習)を取得した後、日本に入国し、企業へ配属。ここから実習がスタートします。
実習生受け入れ前に必要な環境整備
技能実習生が安心・安全に働けるようにするために、以下の受け入れ環境の整備が求められます。
- 安全・衛生に配慮した職場
作業手順の明確化、安全対策の徹底、衛生管理マニュアルの整備が必要です。 - 宿舎の確保と基準の遵守
個室・共有スペースの確保、プライバシーへの配慮、冷暖房・インターネット環境などが整った住まいを準備することが求められます。 - 生活支援体制の構築
通訳可能なスタッフの配置、日本語学習の支援、病院の案内、銀行口座の開設など、生活面でも手厚いサポートが必要です。
社内体制(責任者・指導員など)の整備
技能実習を適切に運用するには、以下のような社内体制を整える必要があります。
- 技能実習責任者
実習計画の管理、監理団体とのやり取り、制度運用全般の責任を担います。指定講習の受講が必須です。 - 技能実習指導員
実習生に対する実地指導を担当し、業務を段階的に教える役割を担います。十分な実務経験が必要です。 - 生活指導員
実習生の日常生活をサポートする役割で、言語や文化の壁を越える橋渡し的な存在です。職場外での相談対応も含まれます。
これらの役割を担う人材を社内で明確にし、教育体制を構築することが、受け入れ後のトラブル防止や実習の成功に直結します。
受け入れに必要な制度上の条件と手続き
技能実習制度の対象業種と受け入れ枠
技能実習制度には、受け入れが認められている「対象職種・作業」が定められています。2025年現在、農業・建設・製造・介護など80職種以上が対象となっており、受け入れを希望する企業は自社業務が該当するかを確認する必要があります。
また、受け入れ人数には「常勤職員数に応じた上限枠」があり、たとえば企業に常勤職員が30人いる場合、受け入れ可能な技能実習生は最大9人(1号3人・2号6人)となります。この枠を超えての受け入れはできません。
法的な要件(労働条件・就業規則の整備など)
技能実習生も日本人労働者と同等の労働関係法令が適用されます。企業は以下のような法的要件を満たす必要があります。
- 適正な労働契約の締結
日本語・母国語の契約書を用意し、賃金・勤務時間・休日などを明記します。 - 最低賃金の遵守
都道府県ごとの最低賃金以上を支払う必要があります。実習生にだけ特別に安い賃金を設定することはできません。 - 労働時間・残業・休日の管理
労働基準法に則った管理が求められ、長時間労働や違法な残業は厳しく監視されます。 - 就業規則の整備と説明
企業の就業ルールを整備し、技能実習生にも理解できる言語で説明することが重要です。
これらに加えて、労働保険・社会保険への加入も義務付けられています。受け入れ前に社内体制や規則の整備をしっかり行うことが、制度違反の防止につながります。
監理団体との連携と書類申請の流れ
技能実習の実施においては、企業単独ではなく、監理団体と連携して進めるのが一般的です。以下が基本的な手続きの流れです。
- 監理団体と契約を結ぶ
まず、受け入れ業種に対応する監理団体を選定し、契約を締結します。 - 実習計画書を作成
実習内容、実施体制、スケジュールなどを記載した計画書を監理団体と一緒に作成します。 - 外国人技能実習機構(OTIT)へ申請
作成した実習計画は、外国人技能実習機構に提出し、認定を受ける必要があります。※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。
参照 ▶ 外国人技能実習機構 - 在留資格認定証明書の申請(入管)
実習生の国籍や身元確認書類をもとに、入国管理局に在留資格の申請を行います。 - 技能実習生の入国・配属手続き
在留資格が交付された後、日本へ入国し、所定の講習を経て企業へ配属されます。
このように、制度に則った正しい手順で準備・申請を進めることで、実習生の受け入れがスムーズに進みます。
技能実習生を定着させるためのサポート体制
生活面の支援(住居・生活ルール・健康管理など)
技能実習生が安心して働ける環境を整えるためには、生活面での支援が不可欠です。多くの実習生にとって、日本での生活は初めての経験であり、文化や習慣の違いによる戸惑いが少なくありません。
- 住居の提供と生活指導
住まいは企業側で手配するのが一般的です。共同生活となる場合も多いため、ゴミ出しのルール、騒音マナー、防災などについても丁寧な指導が必要です。 - 健康管理のサポート
病気やけがの際に速やかに対応できるよう、近隣の病院や保険の使い方についても案内しておくと安心です。 - 日常生活の相談窓口
生活上の悩みや不安を気軽に相談できるよう、日本語の話せる担当者や、母国語対応の支援者の配置が望まれます。
こうした支援を継続的に行うことで、実習生の不安や孤立感を軽減し、離職防止にもつながります。
日本語教育や文化理解のための取り組み
円滑な職場コミュニケーションを図るためには、日本語教育の提供や異文化理解の取り組みが効果的です。
- 日本語学習の支援
入社時だけでなく、定期的な日本語レッスンの機会を設けることで、職場でのやり取りがスムーズになります。eラーニングや地域の日本語教室の活用も有効です。 - 職場内の異文化理解研修
受け入れ側の日本人従業員に対しても、文化や宗教、価値観の違いを理解するための研修を行うと、双方にとって働きやすい環境づくりにつながります。 - 交流イベントの実施
社内行事や地域の祭りなどに実習生を招くことで、職場や地域への帰属意識が高まり、孤立を防ぐことができます。
トラブル防止とメンタルケアの仕組み
実習生が安心して働き続けるためには、トラブルの未然防止と精神的なサポート体制も欠かせません。
- 相談窓口の設置
ハラスメントや労働条件に関する悩みを受け止める窓口を社内または監理団体内に設け、匿名相談も可能にすることが望まれます。 - 定期的な個別面談
配属後も定期的に面談を実施し、実習生の不安や不満を早期に把握し、対応することが大切です。 - ストレスチェックやカウンセリング体制
心身の不調を早期に察知するために、簡易なストレスチェックや母国語でのカウンセリングサービスの導入も効果的です。
トラブルを放置すると、実習の中断や帰国、制度違反など大きな問題に発展する可能性があります。早期対応と予防を重視したサポート体制の構築が、長期的な受け入れ成功の鍵となります。
まとめ
技能実習生の離職や転職を防ぐためには、制度の仕組みを正しく理解し、受け入れ企業側が実習生一人ひとりに対して丁寧なサポートを行うことが何より重要です。待遇面の整備やキャリア形成支援、日本語教育・生活支援・メンタルケアなど、複合的な取り組みが定着率の向上に直結します。
とはいえ、制度対応やサポート体制の構築には時間や人手、専門的な知識が求められるため、企業単独で進めるには限界があるのも現実です。
そこで、私たち「オープンケア協同組合」は、技能実習制度に精通した支援パートナーとして、以下のようなサポートを行っています。
- 実習生の受け入れ準備・制度対応のアドバイス
- 配属後の定着支援(生活サポート・相談対応)
- 日本語教育や文化研修の企画・実施サポート
- 離職・トラブル発生時の早期対応相談
- 監理団体や行政との連携・手続きの補助
外国人材の受け入れに不安や課題を感じている企業様は、まずはお気軽にご相談ください。現場の実情に合わせた、現実的かつ実効性のある支援をご提案いたします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/