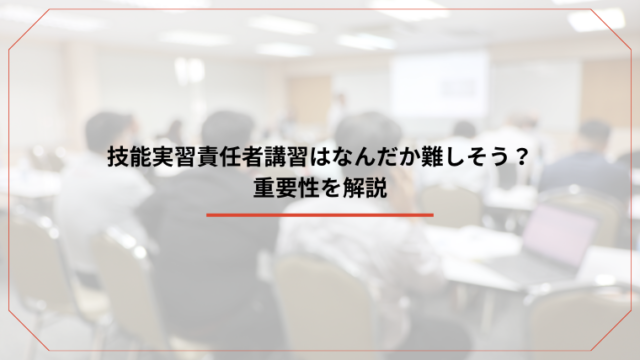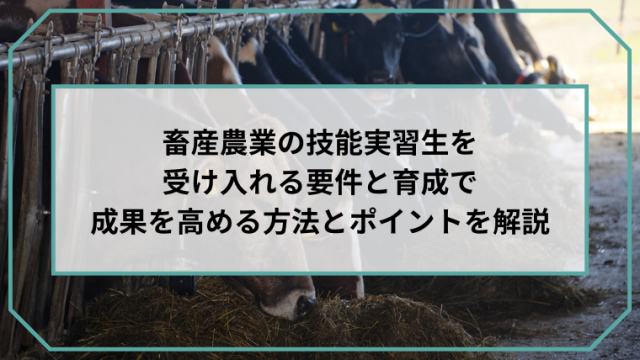技能実習制度では、実習内容や学びの記録として「技能実習日誌」の作成が義務づけられています。この日誌は、実習の進捗管理やトラブルの予防、制度の適正な実施を証明する重要なツールです。
しかし、「どんな項目を記載すべきか分からない」「記入例やテンプレートが欲しい」といった声も多く寄せられます。
本記事では、技能実習日誌の目的と制度上の位置づけから、記載すべき基本項目、書き方のポイント、注意すべきミス、記録・保管上のルールまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。初めて日誌管理を担当する方や、制度の見直しを行いたい企業にもおすすめの内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習日誌とは?制度における位置づけと目的

技能実習日誌とは、技能実習生が日々の実習内容を記録し、学びの振り返りや課題の整理を行うための記録帳です。技能実習制度においては、単なる作業記録ではなく、「技能移転の進捗」や「適正な実習の実施状況」を確認するための重要なツールとして位置づけられています。
日誌には、実習生本人による記載と、指導者の確認署名が求められ、適切な保管が義務づけられています。これにより、制度本来の目的である「開発途上国への技能移転の促進」と「技能実習生の保護」の双方を支える役割を果たしています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習制度と日誌記録の関係
技能実習制度では、技能実習生が単なる労働力として働くのではなく、計画に基づいて技能を学び、成長していくことが求められます。日誌の記録は、そのプロセスを「見える化」する手段の一つです。
技能実習計画には、実習で習得すべき技能や指導内容が具体的に記されていますが、それが日々の現場でどのように実施されているかを示すのが日誌です。実習内容と計画との整合性を確認するうえでも、日誌の記載は非常に重要です。
また、監査時には、日誌が適切に記入・保管されているかが確認項目となっており、団体監理型の監理団体による定期訪問でもチェックされることがあります。
外国人技能実習機構が求める日誌の意義
外国人技能実習機構(OTIT)は、日誌の活用を制度運用要領において明確に推奨しています。日誌は以下の3つの意義を持つとされます。
- 技能習得の振り返りと意識づけ
日誌を書くことで、実習生自身が「どの技能を学んだのか」「どのような課題があったのか」を整理でき、自主的な学習姿勢を促します。 - トラブルや不適切な実習の早期発見
不自然な記載や、実習内容と計画とのズレを通じて、制度上の不適正な運用が見えることがあります。監理団体や実施者が早期対応するためのサインとしても有効です。 - 制度の適正運用の証拠資料としての機能
監査や申請時に、日誌は実習の実態を裏づける書類の一つとして扱われます。技能実習評価試験に向けた準備記録としても活用されることがあります。
このように、技能実習日誌は制度運用上、技能実習生の学びを支えるだけでなく、制度全体の透明性と適正性を確保するためにも不可欠なツールとされています。
日誌が持つ3つの役割(進捗管理/トラブル防止/法的証明)
技能実習日誌は、単なる作業記録やメモではありません。制度の適正運用を支える文書として、以下の3つの重要な役割を果たしています。
1. 進捗管理:技能習得の状況を「見える化」
実習生が日々どのような作業を行い、どの技能をどのレベルまで習得しているかを日誌によって可視化することで、進捗の管理が可能になります。特に、技能実習計画に基づいた内容と日々の実習が一致しているかを確認する上で、日誌は重要な資料です。
実習実施者(企業)や監理団体は、日誌を通して実習内容の過不足を把握し、必要に応じて指導内容の見直しや補足支援を行うことができます。
2. トラブル防止:不適切な状況の早期発見につながる
日誌の記載内容には、実習生の体調や職場環境に関する記述も含まれることがあり、実習生の不満や困りごとがにじみ出るケースもあります。
たとえば、「同じ作業ばかりで技術が身につかない」「体調が悪いが休めない」などの記載があれば、監理団体や実施者が早期に状況を把握し、問題を未然に防ぐ対応が可能です。これは、技能実習生の人権保護や労働環境の改善にもつながります。
3. 法的証明:制度運用の正当性を裏付ける書類
日誌は、制度に基づいて技能移転が行われたことを示す「証拠書類」の一つとして扱われます。外国人技能実習機構や入国在留管理庁による監査の際には、実習の適正な実施状況を確認する資料として提出を求められることがあります。
また、万が一トラブルや訴訟が発生した場合、実習生がどのような実習を受けていたかを示す客観的資料としても活用されます。そのため、記載漏れや虚偽記載がないよう、正確かつ継続的な記録が求められます。
日誌に記載すべき基本項目とは
技能実習日誌は、制度の適正な運用を裏付ける大切な記録書類です。外国人技能実習機構(OTIT)や監理団体の指導でも、必要記載項目が明確に定められており、以下の5つの基本項目は必ず含めるべき内容とされています。
① 実習を行った日付
日々の実習がいつ実施されたかを明記することは、実習計画との整合性を確認する上で不可欠です。記載漏れがあると、実習が実施されていなかったと判断される恐れもあるため、実習を行った「年月日」は必ず記録します。
② 実習内容(作業・工程・指導項目)
その日に行った作業や工程、学んだ技能などを具体的に記述します。単に「作業」や「清掃」などと書くだけでなく、「組立ラインで製品Xのネジ締め作業を実施」など、できるだけ詳細に書くことで、技能習得の実態を正確に反映できます。
③ 実習生の学びや課題
実習を通じて得た知識・技術、または難しかった点、分からなかった点などを実習生の視点で記録します。これは、技能の定着度を振り返るとともに、今後の指導の参考資料としても有効です。
例:「初めてX工程を経験し、ネジの締め具合に注意が必要だと学んだ」
④ 指導員の指導内容と署名
実習生が正しく実習に取り組んでいるかを確認するため、担当指導員によるコメントや指導内容の記載が必要です。また、確認の証として指導員の署名欄を設けることが求められています。これにより、日誌が「一方的な記録」ではなく、「双方向の確認記録」として機能します。
⑤ 補足欄(トラブル・気づき・体調など)
その日の出来事で特筆すべきことがあれば、補足欄に自由に記載します。たとえば体調不良や職場でのトラブル、改善点への気づきなどは、実習生の支援体制を整えるうえでも貴重な情報源です。記入内容は監理団体や受け入れ企業の早期対応にも役立ちます。
技能実習日誌の書き方と記録例

技能実習日誌は、単なる業務記録ではなく、制度上の適正な技能修得を証明するための重要な書類です。ここでは、実際の記録様式や書き方のポイント、分野ごとの具体例、注意点について解説します。
分野別(日常作業/建設/介護など)具体的な記入例
技能実習の内容は分野によって異なるため、日誌の書き方にも特徴があります。以下に分野ごとの記入例を紹介します。
【日常作業(製造業など)】
2025年7月10日:ライン作業にて製品Xのパッキング作業を行う。正確さとスピードが必要で、指導員から作業手順の改善点を指摘された。
【建設分野】
型枠組立作業を初めて経験。鉄筋の位置確認と安全ベルトの使用方法について指導を受けた。重機作業との連携が課題。
【介護分野】
食事介助とレクリエーション補助を実施。高齢者との日本語でのやりとりが難しく、表情やジェスチャーで補う工夫をした。
記入時のポイントとよくあるミス
技能実習日誌の記録にはいくつかの注意点があります。
記入のポイント
- 主語(自分)と内容(作業・学び)を具体的に書く
- その日の感想や気づきを忘れずに
- 誤字脱字や空欄がないよう確認する
- 指導員の確認印・署名を必ずもらう
よくあるミス
- 「作業をした」「勉強した」など抽象的な記述
- 日付の記入漏れや連続記載の抜け
- 指導欄の未記入・未署名
- 実習と関係ない私的な内容の記載
これらのミスは監査時に指摘されることが多いため、定期的なチェックが必要です。
Excel・PDFのダウンロード可否とテンプレート活用
外国人技能実習機構(OTIT)やJITCOの公式サイトでは、参考様式4-2号のフォーマットがPDF形式で公開されています。一部の監理団体や支援サイトでは、Excel形式のテンプレートも提供されており、実習生や企業担当者が効率的に記入・管理できるよう工夫されています。
【活用ポイント:】
- Excel形式:毎日記入やフィルタ管理に便利
- PDF形式:印刷・保管に適し、監査提出用に推奨されることもある
記入負担を軽減しつつ、記録の正確性を保つためにも、テンプレートの活用は非常に有効です。
記載・保管における注意点と監理団体のチェックポイント
技能実習日誌は、技能の習得状況や実習の適正な実施を確認するための「公的な記録」として扱われます。そのため、記載や保管には細心の注意が必要です。本章では、日誌記録に関する注意点や監理団体・外国人技能実習機構による確認事項について解説します。
日誌の記入頻度と誰が書くか
技能実習日誌は、原則として実習生本人が毎日記入することが求められます。
- 記入は業務終了後にその日の作業内容を振り返って書くのが基本です。
- 言語は日本語が望ましいですが、日本語学習の進捗に応じて母語併記も可能です(監理団体や指導員の確認ができる形式が推奨されます)。
- 指導員は日誌の記載内容を確認し、必要に応じてコメント・署名を行うことが望ましいとされています。
まとめ書き・代理記入がNGな理由
技能実習日誌の信頼性を確保するために、まとめ書きや他者による代理記入は禁止されています。
- まとめ書きでは実習内容の正確な記録が困難になり、習熟度や課題の把握ができなくなります。
- 代理記入が発覚した場合、制度違反と見なされるリスクがあり、受入企業や監理団体の評価にも悪影響を及ぼします。
監理団体や外国人技能実習機構による実地調査において、筆跡の類似性や記録タイミングの不一致などから不適切な記載が指摘される事例もあります。
保管義務(最低4年間)と帳簿との連携
技能実習日誌の保管期間は、技能実習が終了した日から1年間とされています。しかし、実際には技能実習生が配属された日から起算して、最低でも4年間(たとえば3年間の実習期間+1年間の保管期間)保管する必要があります。これは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて義務付けられているものです。
以下(↓)、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に関する参考資料となります。https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
- 実習実施者(受入企業)は、日誌と帳簿(賃金台帳・出勤簿など)を一元的に管理することが望ましいとされています。
- トラブル発生時や監査対応において、日誌の記録と他の文書との整合性を確認できることが重要です。
監理団体・外国人技能実習機構の確認項目とは
監理団体および外国人技能実習機構(OTIT)は、巡回訪問や実地調査の際に技能実習日誌の以下のようなポイントを確認します。
| 確認項目 | 内容 |
| 記録の連続性 | 毎日記録されているか、空白や不自然なまとめ書きがないか |
| 内容の具体性 | 実習内容や学びの記載が明確か、抽象的すぎないか |
| 指導欄の記入 | 指導員の確認やコメント、署名の有無 |
| 保管状況 | 紛失・改ざんがなく、必要な期間保管されているか |
| 帳簿との整合性 | 出勤簿・工程管理表など他記録と矛盾がないか |
これらの確認は、「技能実習が適正に実施されているかどうか」を判断する重要な材料となります。
日誌作成を効率化する方法とツール紹介

技能実習日誌は、日々の記録を正確に残すという点で非常に重要ですが、紙ベースでの管理や実習生ごとのフォローアップは、企業担当者や生活指導員にとって大きな負担になることもあります。そこで、日誌作成を効率化するためのツールや方法を導入することで、記録の質を維持しながら業務負担の軽減が図れます。
デジタルテンプレートやアプリ導入例
紙の手書き日誌に代わり、Excel形式のテンプレートやスマートフォン・タブレット対応の記録アプリを活用する企業が増えています。
- Excel・PDF形式のテンプレート:OTITの様式を基に作成されたテンプレートを配布し、PCで入力できるようにすることで記載ミスや読みづらさの防止につながります。
- 記録・共有用アプリ活用例(CLOUDBIZ、noteeなど):CLOUDBIZは業務管理ツール、noteeは録音・文字化できるノートアプリです。作業内容や学びをスマホで記録しクラウドで共有する際に活用可能です。指導員は遠隔で確認・コメントできます。(※公式な実習日誌は別途所定様式で記録が必要です。)
- 実習生向け記録アプリ(例:CLOUDBIZ、noteeなど):作業内容や学びをスマホで記録し、そのままクラウドに保存する形式。指導員も遠隔で内容確認・フィードバック可能なため、時差なく対応できます。
こうしたツールは、日本語・母国語併記機能や音声入力対応など、外国人材に配慮した設計がされているものもあります。
クラウドでの一元管理と多言語対応
日誌のクラウド管理を導入することで、実習実施者・監理団体・生活指導員がそれぞれの立場から情報にリアルタイムでアクセスでき、以下のようなメリットがあります。
- 一元管理により過去記録の検索や帳簿連携が容易になる
- 監理団体が月次確認や指導記録をクラウド上で完結できる
- 翻訳機能により日本語が苦手な実習生の入力も支援可能
特に、多言語UI対応ツールを活用することで、記載ミスや誤読のリスクを減らし、記録内容の質を安定させることができます。
担当者の業務負担軽減の工夫
生活指導員や人事担当者が複数名の実習生の日誌を確認・保管する際には、効率的な運用体制が求められます。以下のような工夫が有効です。
- 定期的な入力リマインドの自動送信(メール・アプリ通知)
- 記載内容のサマリー表示による要点チェック
- テンプレート化された指導コメントの活用
- チェックリストや進捗バーで記入状況の見える化
これらの工夫により、単なる業務削減だけでなく、実習生の学びを可視化しやすくなるという教育的メリットも期待できます。
まとめ|日誌を正しく活用して制度の適正運用を
技能実習日誌は、単なる記録ツールではなく、制度の適正な運用を支える重要な役割を担っています。記載内容の質と一貫性は、実習生の学びや安全、監査対応に直結します。
技能実習日誌に不備があると、監理団体や外国人技能実習機構からの指摘を受ける可能性があり、企業の適正な実習体制が問われます。逆に、日誌を丁寧に記録し、保管・管理を徹底することは、制度への理解と法令遵守の姿勢を示すことに繋がり、企業としての信頼性を高める要素になります。
実習生の支援にもなる記録の蓄積を
日誌は、実習生が日本での学びや成長を自ら振り返る機会でもあります。作業内容だけでなく、課題・感想・気づきなどの記録を積み重ねることで、生活支援やメンタルケアのヒントとなり、より的確なサポートが可能となります。
また、トラブルや不調の兆候を早期に把握できるツールにもなります。正しく日誌を活用することは、実習生と企業双方にとって有益であり、より良い技能実習の実現に繋がります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/