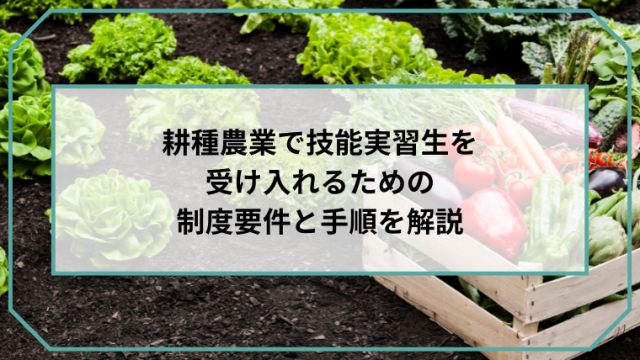型枠施工業務で技能実習生の受け入れを検討している企業様へ。この記事では、対象業務や制度の概要、受け入れ準備のポイントをわかりやすく解説します。導入の可否判断や制度理解に役立つ内容を整理しました。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習制度における型枠施工職種とは?


型枠施工とは、建設現場で鉄筋コンクリート構造物を形成するために必要な「型」を組み立て、コンクリートを打設し、硬化後に取り外す一連の作業を指します。主に木製または鋼製の型枠を用い、建物の基礎・壁・柱などの構造部を成形する上で不可欠な工程です。この作業は、精度・安全性・工程管理において高度な技術が求められるため、一定の専門性と訓練が必要とされます。
建設分野における型枠施工の位置づけ
型枠施工は、日本の建設業において「型枠工」として分類される専門的な職種であり、特にコンクリート系建築物の施工で大きな役割を担っています。建設業界における技能職の中でも肉体的負荷が大きく、慢性的な人手不足に直面している分野のひとつです。このため、外国人技能実習生の受け入れニーズも高く、制度上も正式に認められた職種として位置づけられています。
技能実習制度で型枠施工が認められる背景
技能実習制度の目的は、開発途上国の人材に対し、技術や技能を移転し、その国の発展に寄与することです。その中で型枠施工は、日本独自の技術が必要とされる専門領域であり、国際的にも通用する技術移転対象とみなされています。
型枠施工が認められている背景には、以下の要素が挙げられます。
- 日本
- 独自の建築技術としての教育的価値がある
- 実務に密着した技能が体系化されている
- 技能検定制度が整備されており、評価が明確である
このように、制度的にも社会的にも意義が大きいことから、技能実習制度での対象職種として明記されています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習生が対応できる型枠施工の具体的な作業範囲
制度で定められた対象作業と制限
技能実習制度では、型枠施工において技能実習生が従事できる作業範囲が明確に定められています。対象となる作業は、いずれも「建設分野」の一職種として法的に認められており、1号・2号・3号いずれの段階でも具体的に記載された工程に基づいて実習が行われます。
対象作業には以下のような内容が含まれます。
- 木製または鋼製型枠の組立て、設置および解体作業
- 型枠の寸法確認および墨出し(マーキング)作業
- コンクリート打設前後の型枠調整・締付け作業
- 使用後型枠の洗浄・整理・保管作業
これらの作業は「技能移転を目的とするものであり、単純作業としての労働力活用を目的としない」点に注意が必要です。
監理団体との関係と役割分担
技能実習制度では、受け入れ企業が単独で制度運用を行うことはできません。必ず「監理団体」と呼ばれる外部機関と連携し、技能実習計画の申請・運用・定期報告などを進めていきます。監理団体は、企業と実習生の間に立ち、制度の適正運用を支援・監査する立場にあります。
監理団体が担う主な役割は以下のとおりです。
- 技能実習計画の審査・提出支援
- 定期訪問による実習状況の確認・指導
- 実習生への生活支援(相談対応、翻訳支援など)
- 入国時手続き、講習、居住支援などの総合支援
企業は監理団体を「制度のパートナー」として活用し、業務分担を明確にしながら制度遵守を徹底する必要があります。
技能実習計画書に記載すべき業務内容
技能実習を適正に実施するためには、監理団体を通じて「技能実習計画」を作成し、出入国在留管理庁などに提出・認可を受ける必要があります。この計画書には、技能実習生が従事する予定の具体的な作業内容を明記しなければなりません。
計画書において重視されるのは、対象作業が制度で定められた範囲内であること、指導体制が整備されていること、そして実習の段階(1号・2号)ごとに求められる成果が明確であることです。万が一、非該当業務を含めたり、記載内容と実務に齟齬があると判断された場合、制度違反となるリスクがあるため、慎重な作成が求められます。
実務上の注意点と想定される誤解
技能実習生に型枠施工を任せる際には、制度上許される作業であっても、現場実務とのギャップに注意が必要です。以下は、現場で起こりやすい誤解と対策です。
- 型枠施工以外の作業(資材運搬、清掃など)を主業務として割り当ててしまう
- 解体作業のみ、あるいは単純補助のみを継続させる
- 教育的要素のない単調作業を長期にわたって行わせる
これらはいずれも「技能移転」という制度の趣旨に反する可能性があります。実務上は、日本人技能者の指導を伴いながら、計画に沿った技能向上が確認できる内容であることが重要です。
受け入れ前に確認すべき制度要件
実習実施者としての企業側の条件
技能実習生を受け入れるには、企業側が「実習実施者」として所定の条件を満たす必要があります。これは法令に基づき、受け入れ体制の妥当性を確保するために設けられたものです。
企業側が整えておくべき主な条件は次のとおりです。
- 技能実習責任者・指導員・生活指導員の配置
- 安全衛生管理体制の確保(教育資料・装備の用意など)
- 日本人労働者と同等以上の労働条件・報酬設定
- 雇用契約・就業規則の整備と翻訳対応
これらの体制が未整備であると、技能実習計画の認定が下りない可能性があります。特に初めて受け入れる企業は、監理団体と相談しながら一つ一つ確認していくことが大切です。
技能実習計画の作成と申請プロセス
技能実習の実施には、監理団体と協力して技能実習計画書を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)および出入国在留管理庁の認定を得る必要があります。計画書には、対象職種・作業内容・実習期間・教育体制・評価方法など、細かな内容を記載しなければなりません。
申請から認定までには1〜2か月程度を要することがあり、書類不備や要件未達により差し戻しされるケースも少なくありません。特に、初回受け入れ時はスケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。申請段階で不安がある場合は、経験豊富な監理団体や支援機関に相談することがリスク回避につながります。
技能評価試験と型枠施工における検定内容の理解


技能実習制度では、一定期間の実習後に「技能評価試験」を受け、実習成果の到達度を証明することが求められます。型枠施工職種においては、主に以下の技能検定が実施されています。
- 基礎級:実習1年目の修了時に受検。基本的な作業内容と知識の理解度を評価。
- 随時3級:2号移行の際に受検。より実践的な技術力・応用力が求められる。
- 特別試験(帰国者用):帰国後に受けることで、技能の証明や再来日制度の活用が可能。
試験は「実技」と「学科」の両面から評価され、現場での応用力・安全意識も審査対象となります。合格者は制度上の移行や就業機会において有利になるため、事前の対策が重要です。
中央職業能力開発協会による試験問題の閲覧方法
技能検定試験を主催しているのは、中央職業能力開発協会(JAVADA)です。同協会では、公式サイト上で過去問題や試験基準を一部公開しており、実習実施者や監理団体が事前準備に活用できます。
試験情報の入手方法には以下があります。
- 「技能検定試験問題公開サイト」にアクセスし、職種別に閲覧
- 検索キーワードで検索 例:「型枠施工 技能検定 問題 JAVADA」
※著作権保護の観点から、無断転載・二次使用は禁止されているため注意が必要
また、監理団体経由で教材や指導マニュアルを入手するケースも多いため、必要に応じて団体に確認しましょう。
合格率と実務支援のポイント
型枠施工における技能評価試験は、他の建設職種と比較しても一定の実技力を要する試験です。実際の合格率は実習生の訓練状況や企業側の支援体制によって左右される傾向があります。
特に実技試験では、現場に近い環境での練習が合否を分ける大きな要素となります。木材加工や組立て、寸法の正確性、安全対策の実施など、細かい部分までの習熟が求められます。企業としては、実習時間の確保だけでなく、OJT指導や評価ポイントの明示など、継続的な支援体制の構築が重要です。
受け入れ準備で押さえるべきポイント
住居や生活環境の整備
技能実習生を迎える際には、生活の基盤となる住居や周辺環境の整備が欠かせません。住宅の確保だけでなく、家具・家電、インターネット環境の整備までを含め、安心して暮らせる環境を準備する必要があります。
以下のような点が整備対象となります。
- 住居(アパートや社宅など)の契約と清掃・家具設置
- 寝具、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などの生活必需品
- 通信手段(Wi-FiやSIMカードの提供)
- 最寄りスーパー・医療機関・交通機関などの生活圏情報の案内
生活環境が整っていないと実習への集中が難しくなるため、事前準備の丁寧さが定着率にも影響します。
入国後講習と実習開始までの流れ
技能実習生は日本に入国後、すぐに現場に入るわけではありません。まずは1か月間程度の「入国後講習」が義務づけられており、日本語や生活ルール、安全衛生についての基礎知識を学びます。
講習修了後、監理団体の指導のもと、配属先企業へ移動し、実務がスタートします。この配属直後の時期は、文化的・言語的ギャップが顕著に現れることが多く、企業側には丁寧な受け入れ対応が求められます。
また、講習期間中に企業が実習環境の最終準備を整えておくと、スムーズな導入が可能になります。
型枠施工業務に適した日本語教育とは
型枠施工のように指示内容が安全に直結する現場作業では、一定の日本語理解力が求められます。特に、数字・位置関係・工具名など、実務に関する用語を中心とした訓練が効果的です。
「やさしい日本語」やイラスト付き教材を使い、現場用語の反復練習を行うことで、誤解や事故を未然に防ぐことができます。可能であれば、入社後に簡易的な日本語学習時間を設けることも、長期的なパフォーマンス向上に寄与します。
現地面接(ベトナム等)とマッチングの注意点
実習生の選考は、送り出し国であるベトナムやインドネシアなど現地で実施されます。企業担当者が渡航して対面で面接する、あるいはZoomなどを用いたオンライン面接が一般的です。
現地面接で確認すべきポイントは以下の通りです。
- 日本語レベルとコミュニケーション能力
- 体力や建設現場での作業経験・志望動機
- 長期就労意欲や家庭背景
- 技能実習制度への理解度と適応力
選考段階での丁寧な確認が、実習開始後のトラブル防止に大きく影響します。
特定技能への移行も視野に入れた長期計画
近年では、技能実習2号を修了した実習生が、特定技能1号へ移行し、引き続き日本での就業を希望するケースが増えています。型枠施工は、特定技能の建設分野にも該当しており、評価試験に合格すれば再度在留資格を得ることが可能です。
そのため、企業としても「3年間で終わる関係」ではなく、「継続雇用の可能性がある人材」として育成・支援する視点が求められます。特定技能制度を活用することで、安定した人材確保と相互成長が実現しやすくなります。
まとめ
型枠施工における技能実習生の受け入れは、制度的な理解と丁寧な準備があってこそ実現可能です。対象作業や技能検定、計画書の作成や生活環境の整備まで、各工程には明確なルールと注意点があります。
特に初めて導入を検討する企業にとっては、監理団体との連携や支援体制の活用が成功の鍵を握ります。自社での受け入れが可能かどうか悩まれている方は、制度に詳しい専門機関に早めに相談し、導入可否の判断材料を得ることをおすすめします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/