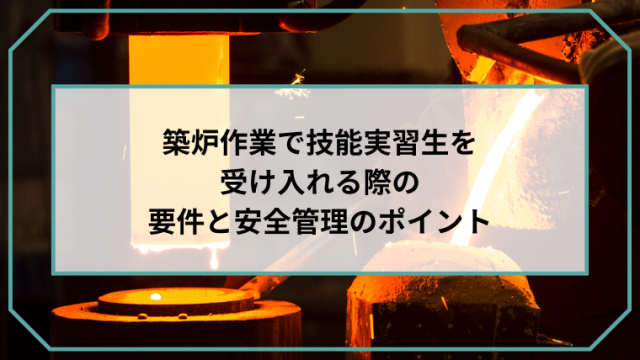建設現場での外国人技能実習生を受け入れたいけど、受け入れ方法が分からない方へ。本記事では、建設機械施工に関わる技能実習制度の仕組みと申請手続き、対応機種や試験内容まで網羅的に解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
建設機械施工とは?技能実習で対応できる作業内容と機種を確認

技能実習制度における「建設機械施工」の定義
建設機械施工とは、建設現場で使用される機械を操作し、整地・掘削・積込みなどの土工関連作業を行う業務を指します。技能実習制度では、この作業分野が「職種」として定められており、一定の作業分類に沿って実習が認められます。
具体的には「車両系建設機械を使用する施工作業」が主軸となっており、運転技術だけでなく安全確保や機械点検などの基礎も含まれます。制度上の目的は、日本の高度な施工技術を開発途上国へ移転することであり、「労働力確保」が目的ではない点に留意が必要です。
対象となる建設機械と作業の種類
技能実習制度で認められている建設機械施工には、操作対象となる機械と作業内容に一定のルールがあります。
対象となる機械の代表例
- ブルドーザー
- 油圧ショベル(バックホウ)
- ホイールローダー
- モーターグレーダー
対象となる作業分類の一例
- 整地・掘削作業
- 運搬路の造成
- 盛土・埋戻し作業
- 資材の積込みおよび運搬補助
これらの作業は、あらかじめ技能実習計画に明記し、制度上の要件に適合している必要があります。
施工業務に必要な講習と関連制度との関係
建設機械施工に従事するには、該当する技能講習の修了が前提となるケースが多くあります。例えば「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」は、実習生が現場で安全に業務を行うために必要な資格のひとつです。
この講習は日本国内で受講させることが求められます。さらに、技能実習評価試験の合格も要件となるため、講習と試験対策を並行して行う計画が重要です。なお、講習内容と技能実習制度上の要件との整合性を確保することが受け入れ側の責任となります。
現場で求められるスキルと安全配慮
建設現場での機械施工には、操作スキルだけでなく現場安全に対する高度な意識も必要です。外国人技能実習生の場合、文化や言語の違いにより誤解や判断ミスが発生するリスクもあるため、以下のような配慮が欠かせません。
- 日常業務での指差呼称・安全確認の徹底
- 作業指示は翻訳アプリやピクトグラム等を用いて視覚的に伝える
- 機械の取り扱いに関するマニュアルを技能実習生の母国語でも整備する
- ヒヤリハット報告制度の導入で事故予防を促進する
企業側には、安全教育と技術指導の双方において、技能実習生に適応した工夫と責任が求められます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
受け入れに必要な条件とは?法的・実務的ポイント
企業側に求められる基本要件と遵守事項
建設機械施工職種において技能実習生を受け入れる場合、企業は一定の基準を満たしている必要があります。これらの要件は主に「実習実施者としての適格性」に関するもので、監理団体やOTIT(外国人技能実習機構)により厳格に確認されます。
- 過去3年間に労働関係法令違反がないこと
- 常勤職員数が適切で、技能実習指導員・生活指導員を配置できること
- 社会保険や雇用保険に加入していること
- 実習に対応する業務が日常的に行われていること
これらの条件は、制度趣旨である「技能移転」を適切に実現するための基本とされており、違反がある場合は認定が取り消される可能性もあります。
技能実習計画の作成と認定基準
技能実習制度の運用においては、OTIT(外国人技能実習機構)へ提出する「技能実習計画」が極めて重要な役割を担います。この計画には、実習内容・実施期間・指導体制などを具体的に記載し、認定を受ける必要があります。
計画内容は、建設機械の種類や操作範囲、技能評価試験の実施予定、使用設備の詳細まで記載することが求められます。特に実習生が従事する作業が制度上の「対象作業」に合致していなければ認定されないため、建設業に特化した専門監理団体の助言を受けることが望ましいです。
建設機械施工職種に必要な設備・指導体制とは
技能実習を適正に実施するには、実習内容に見合った設備や指導体制を整えておく必要があります。建設機械施工では、技能実習生が操作する重機の種類・保守体制・管理方法が明確になっていることが求められます。
必要な体制の一例としては以下の通りです。
- 実習対象の建設機械が稼働できる環境と管理責任者の配置
- 指導員が当該作業の実務経験5年以上を有していること
- 技能実習指導計画に基づいた作業手順書や安全マニュアルの整備
- 機械操作に関する日本語と母国語の併記マニュアル
このような設備や指導体制が整っていない場合、技能実習生の安全確保や制度の適正実施が困難となり、結果として受け入れが認められないリスクがあります。
監理団体との連携で確認すべき点
受け入れ企業が単独で制度対応を行うことは困難であるため、適正に認可された監理団体との連携が不可欠です。監理団体は企業と技能実習生の間に立ち、申請業務や指導支援、トラブル対応など多岐にわたる業務を担います。
連携時には、技能実習計画作成や申請書類の提出における支援の有無、建設機械施工に関する監理実績、評価試験や講習スケジュールへの対応力、さらには技能実習生の生活支援体制や文化的配慮の内容など、複数の要素を事前に確認しておくことが大切です。
信頼できる監理団体との連携は、技能実習生の円滑な受け入れと定着に直結するため、選定の段階から慎重な検討が求められます。
申請から実習開始までの流れと必要書類

実習実施者としての登録と申請の手順
技能実習生を受け入れるためには、企業が「実習実施者」としての登録手続きを行う必要があります。登録は監理団体を通じて行われ、企業単独での申請は基本的に認められていません。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 技能実習計画を作成し、監理団体が内容を確認
- OTIT(外国人技能実習機構)へ技能実習計画認定申請を実施
- 認定後、出入国在留管理庁へ在留資格申請
- 許可後、実習生が来日・入国し、講習を経て実習開始
この一連の流れには数ヶ月を要することもあるため、スケジュールには十分な余裕を持って準備を進める必要があります。
必要書類一覧と書き方の注意点
技能実習計画の申請や在留資格の取得には、多岐にわたる書類が必要です。特に建設機械施工職種では、機械の種類や使用環境に関する明細まで記載する必要があります。
代表的な提出書類
- 技能実習計画書(OTIT所定様式)
- 実習実施者の会社概要資料
- 実習指導員・生活指導員の経歴証明書
- 機械使用の安全管理体制に関する説明書
- 雇用契約書(翻訳付)
- 技能実習生本人の履歴書
- パスポートのコピー
これらの書類は、日本語で統一することが求められますが、一部の提出先では翻訳版の添付も必要な場合があります。記入ミスや不備があると再申請となり、スケジュールに大きな影響を及ぼすため、監理団体との事前確認が不可欠です。
在留資格申請と機械操作に関わる制限
技能実習生が来日するには、「技能実習(1号)」の在留資格を取得する必要があります。この際、在留資格認定証明書交付申請を行い、地方出入国在留管理局の審査を受けます。
建設機械施工職種では、「重機の操作を含む作業内容」であることから、安全管理や指導体制に関する説明が特に重視されます。また、実習生が日本国内で操作できる機種にも制限があるため、事前に使用予定の機械が対象かどうかを確認しておくことが重要です。
実習生の教育機関での講習歴や、母国での経験の有無も審査時の補足資料として役立つケースがあります。
スケジュール管理と失敗しない申請準備
技能実習の受け入れには、多数の関係機関と書類のやり取りが発生するため、スケジュール管理が成功の鍵を握ります。
準備段階で押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- OTITの認定審査には約1ヶ月〜1.5ヶ月かかることを想定
- 在留資格審査にはさらに1〜2ヶ月かかるため、計画的に動く
- 試験や講習日程は地域ごとに異なり、早期確保が必要
- 実習生の選考・面接も事前にオンラインで実施しておく
申請から受け入れ開始までの流れを把握し、各ステップでの遅れを最小限に抑えることで、実習開始時のトラブルや混乱を防ぐことができます。
技能実習評価試験とは?出題傾向と実施方法
初級評価試験の目的と概要
技能実習制度では、各段階で「技能実習評価試験」の受験が義務付けられており、建設機械施工職種ではまず「初級評価試験」を受けます。
この試験は、技能実習1号を修了するにあたり、実習生が必要な基本的知識・技術を身につけているかを確認するものです。内容は「学科」と「実技」で構成され、両方に合格することが2号移行の条件となります。
建設機械施工分野では、一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)が主催し、全国の指定会場で年数回実施されます。学科では安全や構造の知識、実技では操作や点検手順が評価され、実践的な技能の確認が重視されます。
学科・実技試験の内容と傾向
建設機械施工の初級評価試験は、「学科」と「実技」の2つのパートに分かれて実施され、それぞれに合格基準が設けられています。
出題内容の傾向は以下の通りです。
- 学科試験は択一式で、建設機械の構造、保守管理、安全ルールに関する基礎知識を問う
- 実技試験はブルドーザーやショベルなどの操作手順、点検、基本的な運転技能を評価
- 実際の施工現場に即した実技内容が出題されるため、実機訓練が不可欠
- 学科・実技ともに日本語で実施されるため、基本的な用語理解も重要
各試験はあらかじめ定められた試験場で行われ、受験申込は監理団体を通じて実施されるのが一般的です。
合格基準と評価の観点
初級評価試験の合格には、学科・実技の両方で一定の基準を満たす必要があります。学科は択一式で、建設機械の構造や安全知識が出題され、正答率60〜70%以上が目安とされています。
実技では「正確さ」「安全操作」「点検手順の理解」が評価され、具体的には急操作の有無や安全確認の徹底、点検項目の網羅性などが採点基準となります。
いずれも単なる作業遂行能力ではなく、「安全かつ正確に作業を実施できるか」が重視されるため、実務に即した訓練が不可欠です。
試験対策で活用すべき教材と講習
技能実習生が試験に合格するためには、十分な対策と指導が欠かせません。特に、初級試験では日本語での出題が原則となっているため、事前の語彙理解も含めた総合的な学習が求められます。
主な対策手段は以下の通りです。
- JCMAが発行する「建設機械施工技能評価試験教本(初級用)」を活用する
- 講習機関による事前講習を受講し、操作や点検手順を反復訓練する
- 過去問や模擬試験を用いて試験形式に慣れる
- 実技操作の動画教材を活用し、動きと流れを視覚的に理解する
また、監理団体が独自に実施する模擬試験や学習会に参加することで、技能実習生の理解度を事前に把握し、必要なサポートを講じることができます。
企業が受け入れ前に知っておきたい注意点
技能実習制度の目的と誤解しやすい点
技能実習制度の目的はあくまで「開発途上国への技能移転」です。「人手不足解消」が直接の目的ではないため、安易な即戦力期待や単純労働の補完として捉えると制度趣旨から逸脱します。受け入れ企業は、技能実習生に対し段階的な指導と育成の姿勢を持つことが求められます。
建設現場での教育体制構築の重要性
技能実習生は、言語や文化の違いから現場においてミスや事故のリスクが高まる可能性があります。受け入れ企業は以下のような教育体制を整えておくことが重要です。
- 安全マニュアルや作業指示書の多言語化
- OJT指導の際の具体的なチェックリストの運用
- 作業前後の定例ミーティングでの注意喚起の実施
教育体制の有無が定着率や作業品質に直結します。
日本語・生活支援におけるリスク対策
技能実習生が生活に不安を抱えると、仕事への集中力やモチベーションに悪影響が出ることがあります。生活支援では、住環境の整備、近隣施設の案内、日本語学習支援などが大切です。生活指導員を通じた定期的なヒアリングもリスク軽減に有効です。
早期離職や定着不安の軽減ポイント
離職リスクの背景には、実習内容と事前説明の乖離、現場の人間関係の不安などがあります。以下のような取り組みが定着率向上に効果的です。
- 実習前にオンライン面談を行い、仕事内容や職場環境を説明する
- 日報や業務振り返りを取り入れ、不安や課題を早期に発見する
- 同国出身の先輩技能実習生のフォロー体制をつくる
継続的なコミュニケーションが、安心と信頼の構築につながります。
優良な監理団体・支援機関の見極め方
制度対応や定着支援の質は監理団体によって大きく異なります。監理団体を選ぶ際は、建設機械施工の実績有無、日本語教育支援の有無、トラブル対応の体制などを事前に確認しましょう。見学や説明会の参加で、具体的な支援内容を把握することもおすすめです。
まとめ
建設機械施工における技能実習生の受け入れは、制度理解と現場体制の整備があってこそ円滑に進みます。対応機種や実習内容を正しく把握し、評価試験や法的手続きを確実に進めることが、技能実習生との信頼関係構築と長期的な人材育成につながります。
制度導入に不安がある場合は、実績豊富な監理団体へ相談することが第一歩です。適切な支援のもとで、技能実習生と企業がともに成長できる環境を整えていきましょう。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/