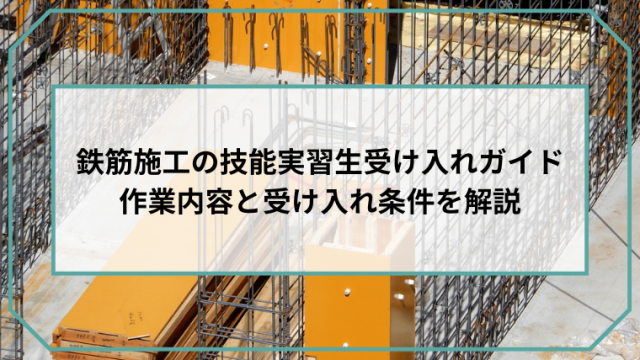本記事では、制度の基本から林業での受け入れ条件、必要な準備までを丁寧に解説。初めての事業者でも安心して導入判断ができるよう、法的要件や支援内容を分かりやすくご紹介します。
林業分野で技能実習制度が注目される理由

外国人技能実習生の導入が進む背景
技能実習制度を通じて外国人を受け入れる動きが林業でも進んでいます。制度改正により「育林」「素材生産作業」が対象に追加されたことで、実習生が従事できる作業の幅が明確化され、導入が検討しやすくなりました。
また、実習制度は国際的な信頼性が高まりつつあり、特定技能制度との連携によって長期的な人材確保にもつながる点が評価されています。
国際協力としての技能実習制度の位置づけ
技能実習制度は、単なる労働力確保の手段ではなく、開発途上国への技術移転と人材育成を目的とした国際協力制度です。林業においても、技術を持ち帰った実習生が母国の森林管理や木材産業に貢献することが期待されています。
企業側には、教育的な視点を持って実習生を受け入れる姿勢が求められます。人材育成に真摯に取り組むことで、制度本来の目的を果たすことができます。
実習生には日本人と同等以上の報酬・待遇が保証され、受け入れ側には「実習計画の作成」「技能試験の受験支援」など、実習の質と人権尊重が求められます。事業者はこの制度趣旨を十分に理解したうえで、制度を活用すべきです。
技能実習制度の仕組みとは?
技能実習1号・2号・3号の違いと林業での該当段階
技能実習制度は1号から3号までの3段階で構成されており、段階ごとに実習内容や期間、要件が異なります。
- 技能実習1号(1年):基礎的な技能習得が目的。入国後、講習と初期実習が実施される
- 技能実習2号(2年):1号終了後、技能検定に合格した実習生がステップアップ可能。より実践的な作業に従事
- 技能実習3号(2年):優良な監理団体・実習実施者であることが条件。母国への技能移転が実現できる段階
林業分野においては、近年「技能実習2号」の対象職種として認定されたことで、継続的かつ高度な技能の指導が可能となりました。
受け入れの目的と制度の趣旨
制度の目的は、日本の技術を開発途上国に移転し、現地の経済発展に貢献することです。労働力確保の手段ではなく、教育・技能向上を主軸とした制度であることを理解する必要があります。
実習生には日本人と同等以上の報酬・待遇が保証され、受け入れ側には「実習計画の作成」「技能試験の受験支援」など、実習の質と人権尊重が求められます。事業者はこの制度趣旨を十分に理解したうえで、制度を活用すべきです。
監理団体とJITCO・OTITの役割
技能実習制度の適正な実施には、複数の機関が関与します。とくに以下の機関の役割を押さえておくことが重要です。
- 監理団体:受け入れ企業をサポートし、実習計画の作成・申請、定期監査、生活支援を行う。(例:オープンケア協同組合)
- JITCO(国際人材協力機構):制度運営の支援機関。相談窓口や情報提供を担う
- OTIT(外国人技能実習機構):法令遵守・適正実施の監督・指導・認定を行う機関。制度の品質維持を担保
これらの機関と連携を取りながら進めることが、スムーズな受け入れのカギとなります。
技能実習と特定技能との違い
技能実習制度と特定技能制度は混同されがちですが、目的と運用の性質が大きく異なります。以下のような違いを理解しておくことが必要です。
| 項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
| 目的 | 技能移転・人材育成 | 即戦力人材の受け入れ |
| 期間 | 最大5年(1〜3号) | 最大5年(更新制) |
| 対象業務 | 実習計画で限定された作業 | 幅広く実務全般に従事可能 |
| 雇用形態 | 実習生(教育的要素) | 労働者(就労目的) |
| 管理機関 | 監理団体・OTIT | 登録支援機関・入管庁 |
林業分野でも、技能実習から特定技能へ移行可能な職種がありますが、要件や体制は大きく異なるため、制度の違いを正しく理解することが重要です。
林業で受け入れ可能な技能実習職種と作業範囲【対象作業】

育林作業(植栽・下刈など)
苗木の植え付けや下刈り、間伐などを行う育林作業は、森林の健全な育成を目的とした基本的な工程です。林業職種のうち、この育林作業が技能実習制度の対象に含まれています。
具体的には以下の作業が認められています。
- 植栽や除伐などの育成作業
- 雑草・灌木の刈り取り(下刈り)
- 成長調整のための間伐・支柱設置など
これらは経験を積むことで安全性と効率性が向上する作業であり、教育的価値の高い工程といえます。
素材生産作業(伐採・造材)
素材生産は、木材を生み出す伐採・造材・搬出などを指し、実習の中でも特に技能と安全配慮が求められる分野です。
制度上、以下の作業が対象となっています。
- 立木の伐倒と玉切り(チェーンソー使用)
- 木材の集材と搬出
- 現地での簡易加工や積込補助
現場では労災リスクが高いため、装備や作業指導体制の整備が必要不可欠です。
安全衛生対策が必要な作業
林業は高リスク産業であるため、安全衛生管理は実習運営の最重要項目です。作業前のKY活動、装備の支給、監督者の同行が基本であり、制度上も安全講習の受講が義務付けられています。
受け入れ企業は、安全教育に関する資料整備や多言語対応の指導体制を事前に準備しておくことが望まれます。
対象作業の範囲外で注意すべき点
制度上、対象作業は限定されています。林道開設や重機による土木作業、木材加工、農作業補助などは認められていません。制度に適さない作業に実習生を従事させた場合、違反となる恐れがあるため、計画段階から慎重な検討が必要です。
制度の範囲外か判断に迷う作業がある場合は、監理団体やOTITに相談することが推奨されます。
林野庁・OTITが定める受け入れ基準
林業で技能実習を行うには、林野庁やOTITが定める基準を満たす必要があります。実習内容・安全体制・住居環境・教育支援などが確認対象となり、基準を満たしていなければ認定が下りません。
審査前に体制チェックリストを活用し、受け入れ体制を客観的に見直すことが制度活用の第一歩です。
技能実習生を受け入れるまでの流れと必要な手続き
監理団体との契約と事前準備
技能実習制度を活用するには、まず受け入れ企業が「監理団体」と契約を結ぶ必要があります。監理団体とは、実習制度が適正に実施されるよう支援・管理する外部組織で、法令に基づき国から認可を受けています。
契約の前には、企業として以下のような準備を整えることが求められます。
- 実習に従事させる作業内容が制度対象に該当しているかの確認
- 技能実習生のための住居や生活インフラの整備計画
- 安全衛生マニュアルの準備と指導員の配置
- 実習計画を運用できる体制(作業現場・人数・資材)の確保
これらの条件を満たしていなければ、監理団体によって契約が見送られることもあります。事前に相談を行い、段階的に整備を進めることが大切です。
実習計画書の作成と申請ステップ
実習生の受け入れには「技能実習計画書」の提出が必須です。この計画書では、実習内容・期間・実施方法・評価方法などを詳細に記載する必要があり、制度趣旨(技能移転・人材育成)に沿った内容であることが求められます。
計画書は監理団体が作成をサポートし、外国人技能実習機構(OTIT)に申請されます。審査では、作業内容の適正性や安全体制、教育・指導内容などがチェックされ、承認を得られた場合にのみ、受け入れ準備へと進むことができます。
在留資格取得と入国手続き
計画認定後は、法務省管轄の出入国在留管理庁に対し、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。技能実習1号としての資格が得られると、実習生の入国が可能になります。
在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能実習計画が正式に認定されていること
- 適切な監理団体の指導のもとでの実施体制が整っていること
- 実習生本人に日本語の基礎的知識と意思疎通能力があること
審査後に交付される証明書をもとに、現地大使館でビザを取得し、入国日が確定します。監理団体は入国に向けた段取りや航空券の手配、到着後の空港送迎なども支援します。
住居準備・生活サポートの整備
技能実習生の受け入れでは、労働環境だけでなく生活面の支援体制も重要視されます。住居の確保だけでなく、生活用品・通信インフラ・防寒対策など、初期の生活基盤を整える必要があります。
生活面の整備には以下のような項目が含まれます。
- アパートや寮などの住居手配と賃貸契約
- 寝具・家具・家電などの生活必需品の準備
- スマートフォン・Wi-Fiなど通信手段の確保
- 地域のゴミ出しルールや交通マナーの説明
また、到着後には日本語学習のサポートや地域交流の場づくりも含めて、実習生が安心して過ごせる環境を整えます。
技能実習制度で守るべき4つの法的ルールと実務対応
労働条件の設定と雇用契約の注意点
技能実習生を雇用する場合、日本人と同等以上の待遇を保証する必要があります。最低賃金の遵守はもちろんのこと、実習生専用の契約書を母国語で用意し、内容をしっかりと説明することが求められます。
以下のような点を特に確認する必要があります。
- 時間外労働・休日労働の明記と適正な割増賃金
- 雇用形態や賃金支払い方法の透明化
- 社会保険・労災保険などの加入手続きの完了
- 雇用契約書と実習計画の齟齬がないかのチェック
また、労働条件通知書や就業規則の内容が技能実習生に正確に伝わるよう、通訳や翻訳対応も重要です。
技能評価試験(基礎級・随時級)への対応
技能実習生は、各段階の終了時に技能評価試験を受験する必要があります。1号では基礎級、2号移行時には随時級の試験が求められ、合格することで次のステージへ進めます。
試験は作業の実技が中心で、企業には試験対策の実技指導、練習機会の提供、会場までの送迎なども求められます。これらは単なる形式ではなく、制度運用の信頼性を担保する重要なプロセスです。
安全衛生教育と労災対策
林業は高所作業やチェーンソーの使用など危険が伴うため、安全衛生に関する教育が制度上でも必須とされています。受け入れ企業は労働安全衛生法に基づき、技能実習生に対して適切な指導を行う責任があります。
安全確保のために必要な取り組みは以下の通りです。
- 入国後講習での安全教育(40時間以上)
- 作業前のKYミーティング(危険予知活動)の実施
- 防具の無償支給(ヘルメット・安全靴・防護ズボン等)
- 災害発生時の通報・対応フローの整備と共有
また、万が一の事故に備えて、労災保険の適用確認や通訳を含む医療対応体制の確保も求められます。
監査・定期報告に向けた体制整備
監理団体やOTITによる監査や定期報告は、技能実習制度の信頼性維持に欠かせない要素です。企業は、定期的に実施される帳簿確認や聞き取り調査に備え、実習内容・勤務記録・給与明細・指導記録などの保管を徹底する必要があります。
報告書類の整備は日常業務の一部としてルール化するのが理想であり、監理団体と連携して、報告漏れや誤記入が発生しない体制づくりが求められます。また、問題が発生した場合には、速やかに報告・是正措置を行う誠実な対応が企業評価にも直結します。
林業での技能実習生受け入れを支援する団体とサービス
監理団体が提供するサポート内容
技能実習制度では、受け入れ企業単独での対応が難しい項目が多く存在します。そのため、認可を受けた監理団体が企業に代わって、制度の円滑な運用を支援する役割を担います。
監理団体が提供する代表的な支援内容には以下があります。
- 実習計画の作成支援および制度申請手続きの代行
- 入国後講習(生活・安全・日本語)の実施
- 住居・生活インフラの整備支援と現地調整
- 定期訪問・巡回による状況把握と企業への改善指導
これらの支援により、受け入れ企業は法的リスクを抑えながら、制度を適正に運用することが可能になります。監理団体の選定にあたっては、林業分野の実績や専門知識を有するかどうかも重要な判断材料となります。
オープンケア協同組合の林業特化支援
オープンケア協同組合は、林業を含む特定分野に対応した受け入れ支援体制を整えており、特に初めて技能実習生を受け入れる事業者にとって心強い存在です。
以下のような特長を持っています。
- 初期費用0円・月額2万円という業界内でも低コストな支援プラン
- Zoomによる実習生との事前面談の実施で、マッチングのミスマッチ防止
- 林業現場で求められる安全教育・生活指導のフォローアップ体制
- 家具・家電・通信環境を含めた住居インフラの一括整備支援
また、同組合はインドネシア人材に特化しているため、日本語教育や文化適応支援にも強みがあります。林業に必要な体力や粘り強さを備えた人材の確保に寄与し、企業側の不安を丁寧に解消する取り組みを展開しています。
JITCO・OTITによる情報提供と支援制度
制度全体の運用を支えるのが、JITCO(公益財団法人国際人材協力機構)とOTIT(外国人技能実習機構)です。企業が制度の正確な理解や適正な実施を行うためには、これらの公的機関の情報活用が不可欠です。
JITCOは、制度概要や申請書類の記載例、実習実施者へのQ&Aなど、導入にあたっての基礎情報を広く提供しています。また、研修資料や翻訳テンプレートなどの実務ツールも活用できます。
一方、OTITは制度監督機関として、実習生の人権保護・安全確保に向けたガイドラインを整備しており、問題発生時には企業・監理団体・実習生からの相談を受け付けています。特に2024年以降、制度の透明性と信頼性がより一層求められているため、これらの機関のガイドラインを常に参照することが推奨されます。
まとめ
林業分野で技能実習生を受け入れるには、制度の目的や対象作業、必要な準備を正しく理解することが重要です。実習制度は人材不足を補うものではなく、教育・技能移転を目的とした国際協力制度であり、企業側にも高い運用責任が求められます。
この記事では、制度の仕組みから林業で認められる作業範囲、受け入れまでの手続き、遵守すべき法令、支援団体の活用方法までを整理しました。初めての導入でも制度を正しく使い、長く信頼される受け入れ体制を目指すことが大切です。
不安な点があれば、監理団体や支援機関へ早めに相談し、制度に詳しいパートナーの力を借りることで、安全で安定した受け入れ体制を構築できるでしょう。