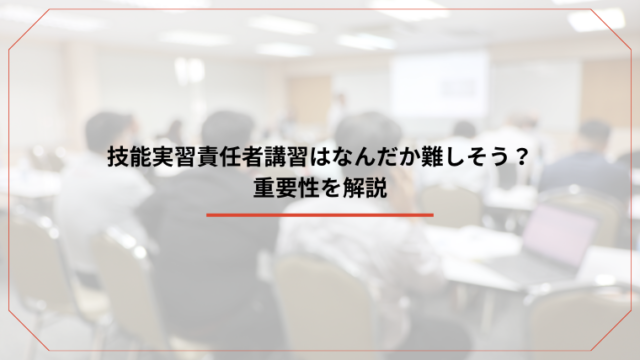建設業で左官作業に携わる外国人技能実習生の受け入れを検討している企業様へ。本記事では、技能実習制度における左官職の位置づけから、実習範囲、必要な手続き、現場での受け入れ準備までを専門的に解説します。適切な制度活用の判断材料として、実務に即した知識を提供します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
左官職とは?建設現場における実習対象作業の実態


左官とは、建物の内外装において、モルタルや漆喰、コンクリートなどを使い、壁面を平滑に仕上げる専門職です。建設現場における仕上げ工程の要となる作業であり、建物の機能性や美観、耐久性に大きく関わる重要な役割を担います。左官職は熟練度が求められる技能であり、施工精度によって仕上がり品質が大きく左右されるため、高い集中力と経験が必要とされます。
特に日本の左官技術は伝統的な漆喰工法から最新の仕上げ技術まで幅広く、実習生にとっても学び甲斐のある職種といえるでしょう。
技能実習制度で認められる作業範囲とは
技能実習制度において、左官作業は「建設分野」の指定職種に該当します。実習可能な作業内容は制度上で細かく定められており、対象となるのは以下のような工程です。
- モルタルやセメントを用いた壁面や床面の塗り仕上げ作業
- 下地処理や養生など、左官作業に伴う付帯工程
- 水準器や鏝を用いた平滑仕上げ技術の活用
- 建物の内外壁、土間、床仕上げなどの定型作業
このように、あくまで“実習計画書で定義された技能”に限定されており、建設全般の作業が認められているわけではありません。受け入れ企業は、対象範囲外の業務に従事させないよう注意が必要です。
他職種との違いと混同に注意すべき点
技能実習制度では、左官と類似する業務が存在するため、職種の混同には注意が必要です。たとえば「とび職」や「建築大工」なども建設分野に含まれますが、作業内容や技能検定の項目が明確に分かれています。
特に、土木系の作業や躯体工事に実習生を従事させたい場合、それが左官として認められる内容かどうか、あらかじめ制度上の定義を確認し、監理団体とも協議しておくことが重要です。曖昧な職務範囲による制度違反を避けるためにも、受け入れ前の作業整理は必須です。
作業例と具体的な実務の流れ
実際の建設現場で技能実習生が担当する左官作業は、以下のような工程で構成されます。
- 下地処理(清掃・プライマー塗布)
- モルタルの練りと搬送
- 鏝を使った壁・床の塗り付け作業
- 乾燥後の表面仕上げ
- 作業場や道具の清掃と後片付け
これらの作業は、職長や熟練左官の指導のもと段階的に習得していくことが一般的です。企業側は、「習熟度に応じたステップ型教育」を行うことで、実習効果と安全性の両立を図ることができます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習生の受け入れに必要な準備ステップ
実習計画と監理団体との連携
技能実習生の受け入れには、まず「実習計画書」の策定と、監理団体との密な連携が不可欠です。実習計画は、技能実習機構の審査を通過するための重要書類であり、左官職としての実習内容・スケジュール・指導体制を明示する必要があります。
監理団体はこの計画書作成を支援する立場にあり、制度運用の実務や提出書類の整備、行政への申請を企業に代わって行ってくれます。そのため、受け入れ企業は計画段階から監理団体としっかり連携し、自社の実務と制度の整合性を確認しておくことが重要です。
職場・作業環境の整備と安全対策
受け入れ前に行うべき準備として、現場の作業環境や安全体制の整備も極めて重要です。以下のような対策を講じることが求められます。
- 防塵・防音などの作業環境配慮(屋内左官作業が多いため)
- 工具・保護具(マスク・ゴーグル・ヘルメット等)の整備
- 作業マニュアルの多言語化(技能実習生の母語対応が望ましい)
- 災害時や怪我時の緊急連絡体制の構築
- 技能実習責任者・指導員の社内配置と講習修了
技能実習法では、外国人労働者の人権や安全確保が強く求められているため、現場改善と制度遵守を両立させる必要があります。
日本語支援・生活支援体制の構築
技能実習生は言語や生活文化の違いに直面しやすいため、職場外での支援体制の整備も受け入れ企業の責任です。日本語教育や日常生活の支援体制が整っていない場合、トラブルや離職のリスクが高まります。
支援内容としては、以下が基本となります。
- 入国直後からの日本語教育の継続支援(N4~N3レベル)
- 住居の提供と契約・家電設置等の初期支援
- 通訳対応や多言語案内(ゴミ出しルール・通勤手段等)
- 病院・役所などの同行サポート体制
これらは監理団体と協力して行う部分も多いため、役割分担を明確にしておくことが円滑な運用につながります。
技能検定試験と評価制度の仕組み
左官職における技能検定の概要
左官職で技能実習生を受け入れる場合、技能検定の実施は制度上の重要なステップです。技能実習制度では、実習期間中に段階的な技能評価を行うことが義務づけられており、これに合格することで次の実習段階への移行が可能となります。
左官職の技能検定には、主に以下の区分があります。
- 技能実習1号修了時:基礎級技能検定(筆記+実技)
- 技能実習2号修了時:随時3級または随時2級(実技試験が中心)
- 技能実習3号移行時:さらに高難度の評価対象(※優良要件あり)
これらの検定試験は、原則として日本国内で実施され、合格すれば技能習得の証明にもなります。受け入れ企業にとっても、教育効果の見える化や適性評価に役立ちます。
評価試験の実施タイミングと内容
技能評価試験の実施は、技能実習の段階ごとに明確なタイミングで行われます。とくに技能実習2号に進むためには、1号修了時に行われる「基礎級」の合格が必須条件です。
評価試験の内容は以下のように構成されます。
- 基礎級:工具の名称確認、壁面仕上げの基本操作など
- 随時3級:コンクリート面へのモルタル施工、指定時間内作業の精度確認
- 随時2級:複数面への仕上げ精度、仕上がりの均一性チェック
試験会場や申請方法は都道府県や監理団体によって異なる場合があるため、早めのスケジュール調整が必要です。
技能レベルに応じた実習ステージの変化
技能実習制度では、検定合格に応じて実習生がステップアップしていく仕組みが採用されています。これは単なる試験というだけでなく、企業側にも「次段階でどこまで任せてよいか」を示す基準になります。
たとえば、基礎級合格後はより高度な塗り仕上げ作業を任せられるようになり、随時3級合格後には、一定範囲での自主的な判断や作業効率を求められるようになります。企業はこの段階的成長に合わせて、指導内容や任せる範囲を調整していくことが望ましいです。
特定技能への移行で変わる5つのポイント
技能実習と特定技能の制度的違い
技能実習と特定技能は、いずれも外国人材の就労を可能にする制度ですが、その目的と運用には明確な違いがあります。技能実習は「人材育成を通じた国際貢献」を目的としており、雇用はあくまで“実習”の一環です。一方、特定技能は日本の労働市場の担い手として「人手不足分野での労働力確保」を主目的とする在留資格であり、雇用の自由度が高いのが特徴です。
特定技能では転職や再契約が制度上認められており、技能実習のような監理団体の存在も不要です。そのため、より高い責任と実務的な雇用管理が企業側に求められる点に注意が必要です。
左官職での試験要件と合格後の働き方
左官職で特定技能1号へ移行するためには、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。具体的には、建設分野の技能評価試験(左官作業区分)に合格し、かつ「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」もしくは「日本語能力試験N4以上」の取得が条件となります。
合格後は、技能実習生という枠を超えた正規雇用に近い形での契約が可能となり、労働時間や待遇も日本人労働者と同様の扱いが求められます。
受け入れ企業に求められる支援内容
特定技能に移行した外国人材を雇用する企業には、法令で定められた支援義務が発生します。技能実習とは異なり、支援内容の実施責任が企業側に直接課される点が大きな特徴です。以下のような項目が該当します。
- 契約内容の説明(母語対応)
- 生活オリエンテーション(通勤・銀行口座・病院案内など)
- 日本語学習の支援
- 住居の確保や入居手続きの補助
- 苦情対応や行政手続きの支援
これらの支援は「登録支援機関」に委託することも可能ですが、最終的な実施責任は雇用主にあります。
長期雇用のメリットと注意点
特定技能へ移行する最大の利点は、就労期間の延長が可能になる点です。特定技能1号では最長5年間の就労が認められており、技能実習で最大3年間だった在留期間と比べて、人材の安定確保が期待できます。
ただし、移行後は本人が「転職」を選ぶことも可能になるため、待遇や職場環境によっては離職リスクが生じます。技能実習中から信頼関係を築いておくことが、長期雇用の基盤となります。
移行支援の活用事例と選択肢
近年では、特定技能への移行を前提とした実習計画を組む企業も増えており、段階的に人材の成長をサポートするモデルが定着しつつあります。移行支援の一環として、以下のような取り組みが実際に行われています。
- 実習2年目からの日本語試験対策支援
- 技能評価試験の模擬訓練
- 移行希望者へのキャリア相談
- 登録支援機関との早期連携による準備期間の短縮
- 離職リスクを抑える待遇改善・評価制度の導入
こうした取組みにより、企業側も実習期間を"育成期間"と位置づけ、より安定的な雇用へとつなげることができます。
まとめ|即戦力育成と国際協力を両立するために

左官職における技能実習生の受け入れは、建設現場における即戦力育成と国際協力の両立を図る重要な取り組みです。実習対象となる作業範囲を正しく理解し、制度に沿った手続きと環境整備を行うことで、受け入れ企業と実習生の双方にとって有意義な成果が期待できます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/