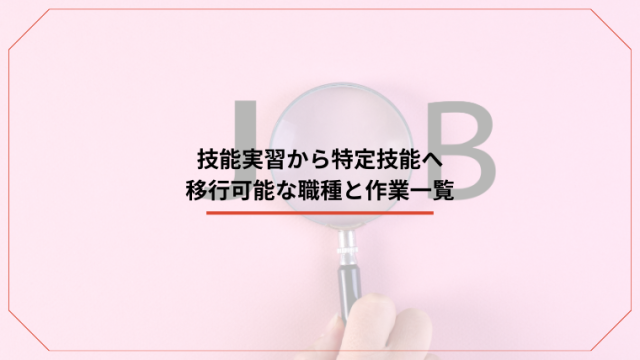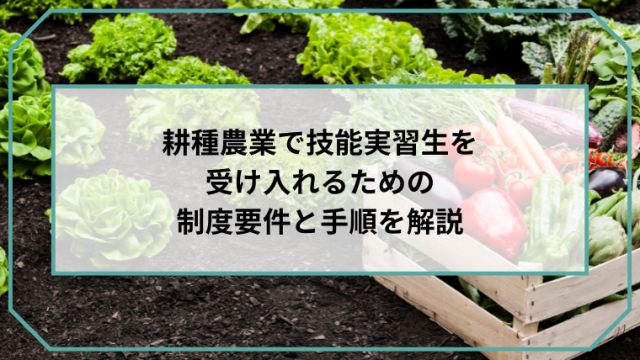- 「受け入れのメリットと、管理コストや法令対応のデメリットが気になる」
- 「在留資格や作業区分、監理団体との役割分担がよく分からない」
そんな不安を感じたことはありませんか?
本記事では、技能実習制度の目的と仕組み、受け入れのメリット・デメリットを整理し、建設・製造など主要分野の受け入れポイントを具体的に解説します。さらに、特定技能への移行条件や2025年の制度改正の要点、実務で必要な計画作成・日本語 / 生活支援体制・監理団体との連携まで、導入判断に直結する情報をまとめました。
「自社で技能実習を活用すべきか」を検討する経営者・人事担当者の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。
制度の理解から実務の準備まで、最初の一歩でつまずきがちです。オープンケア協同組合は、受け入れ計画づくりや日本語・生活支援まで伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
外国人技能実習制度とは?受け入れ企業が理解すべき仕組みと在留資格

技能実習制度の目的と国際協力としての位置づけ
技能実習制度は、日本で培われた技能や知識を開発途上国の人材に移転することを目的とした制度です。外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき運用されており、単なる労働力確保ではなく「技能移転による国際協力」という性格が強調されています。制度の趣旨を理解せずに導入を進めると、受け入れ後にトラブルが生じる可能性があるため、まずは基本的な目的を正しく認識することが重要です。
在留資格の種類と在留期間の基本ルール
技能実習生は「技能実習」という在留資格で滞在します。制度は1号(最長1年)、2号(最長2年)、3号(最長2年)と段階的に区分され、技能実習全体で最長5年間の在留が可能です。それぞれの段階に進むためには技能検定試験に合格することが条件となっており、在留資格や在留期間の管理を正しく理解することが企業にとって欠かせません。
団体監理型と受け入れ企業の役割の違い
技能実習制度の受け入れ方式には「団体監理型」と「企業単独型」があります。特に中小企業の多くは団体監理型を利用しており、監理団体が申請手続きや巡回指導を行い、企業は技能実習生を直接雇用します。受け入れ企業は、雇用契約の締結や安全教育、日本語教育などの支援を担う必要があります。監理団体は制度適正化のための監査・指導を行う立場であり、両者の役割を混同しないことが大切です。
このように、技能実習制度の目的や仕組みを理解することは、メリット・デメリットを整理する前提となります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習生を受け入れるメリット
人材確保の選択肢が広がる(建設業・製造業)
日本の中小企業、とりわけ建設業・製造業などの分野では、制度に基づき外国人技能実習生を受け入れることで、技能移転を目的とした国際協力の枠組みに参画できます。例えば、建設分野22職種33作業、機械・金属分野17職種34作業など、制度上認められた範囲での受け入れが可能です。実習生は特定の作業を通じて技能を学び、日本企業はその指導を担うことで、双方にとって有益な学習・協力関係が形成されます。
採用コストや雇用比較における利点
受け入れに伴う費用面では、監理団体を通じた制度的な仕組みにより、募集や採用活動にかかる企業側の負担が一定の範囲で整理されやすい特徴があります。また、技能実習生はあらかじめ定められた在留期間に基づき計画的に実習を行うため、企業は継続的な技能移転を支援するスケジュールを立てやすいという側面があります。
技能移転を通じた国際貢献と企業の評価向上
技能実習制度の目的は「技能移転」です。企業が技術や知識を外国人技能実習生に伝えることで、母国での産業発展につながります。これは国際協力としての社会的意義があり、CSR活動の一環として企業の評価向上にも寄与します。さらに、多国籍人材との関わりが企業文化を刺激し、新しい発想や改善につながることもあります。
日本人従業員への刺激と多文化理解の促進
技能実習生との協働は、日本人従業員にとっても学びの機会となります。異なる文化的背景を持つ仲間と働くことで、現場の多文化理解が進み、コミュニケーション力や指導力が強化される傾向があります。これにより、職場の一体感や柔軟性が高まり、組織全体の働き方改善につながる可能性もあります。
このように、技能実習生の受け入れは人材確保やコスト面の安定、国際貢献といった複数のメリットをもたらします。
技能実習生を受け入れるデメリットと注意点
定着率や転職リスクへの対応
技能実習制度は在留資格によって在留期間が定められており、長期的に同じ人材が定着する仕組みではありません。そのため、技能実習2号を修了した後に帰国要件がある点や、制度上の制約によって転職につながるケースもあります。
企業は計画的に人員配置を行い、一定期間で交代が発生することを前提とした体制を整える必要があります。
-
技能実習2号修了後に帰国要件があるため長期雇用につながりにくい
-
制度上の制約によって転職に至るケースがある
-
計画的に人員配置を行い、交代を前提とした体制を整える必要がある
日本語や生活習慣への適応支援の必要性
技能実習生は母国で一定の研修を受けて来日しますが、日本語能力や生活習慣の違いから、現場でのコミュニケーションが難しい場合があります。企業が求められる対応は次の通りです。
-
安全指示や専門用語を理解するための日本語教育支援
-
生活習慣の違いを考慮した日常生活のサポート体制
-
教育や生活支援が企業の負担増につながるリスク
管理コストや監理団体との連携負担
技能実習生を受け入れる際は、制度上の管理業務にも対応しなければなりません。主な負担は以下の通りです。
-
監理団体との契約や巡回指導への対応
-
技能実習計画や定期報告の作成にかかる時間と労力
-
書類作成や監査準備に伴う管理コストの増加
これらの課題を踏まえ、企業は制度の特性を理解し、計画的かつ持続可能な体制を構築することが不可欠です。
法令遵守・監査対応に関する課題
技能実習制度は外国人技能実習機構(OTIT)や出入国在留管理庁による厳格な運用が行われています。受け入れ企業には労働基準法や技能実習法の遵守義務が課されており、違反があった場合には受け入れ停止や監理団体の認定取消しといったリスクも存在します。企業は制度や関連法令を正確に理解し、適切な運用を徹底することが求められます。
こちらをご確認ください 参照:▶ OTIT 外国人技能実習機構
受け入れのメリットと同時に、こうした課題を正しく理解しておくことが重要です。
建設業など主要分野での技能実習と受け入れ事例
建設業分野(22職種33作業)の特徴と課題
建設業は技能実習制度の中でも代表的な受け入れ分野の一つです。対象は22職種33作業に細かく区分され、とび職・型枠施工・塗装・溶接などが含まれます。これらは専門的な技能が求められる一方で、国内の人材不足が続いている分野でもあります。技能実習生は現場の実務を通じて技術を学び、帰国後に母国で活かすことが期待されています。ただし、安全管理や日本語での指示伝達に課題が残るため、教育体制を整備することが不可欠です。
食品製造での受け入れ状況
食品製造も技能実習生の受け入れが多い分野です。食品製造ではライン作業や衛生管理の習得が目的とされています。これらの分野では日本語によるコミュニケーションが重要なため、事前研修や継続的な日本語教育が成果に直結します。特にサービス業では文化的背景の違いが顧客対応に影響を及ぼす可能性があるため、企業が十分な支援を行うことが求められます。
在留資格や作業区分による受け入れの違い
技能実習制度では職種や作業ごとに受け入れの可否が決められています。例えば、建設業や機械金属分野では特定技能制度への移行が可能なケースもありますが、全ての分野で移行できるわけではありません。また、在留資格は技能実習1号から3号へ段階的に進む仕組みになっており、移行には技能検定試験の合格が必要です。受け入れ企業は自社の業務内容に合った作業区分を確認し、適切な在留資格で受け入れることが求められます。
このように、技能実習制度は分野ごとに特徴や課題が異なるため、制度理解と分野別対応が成功のカギとなります。
※職種・作業数は制度改正に伴い随時更新されます。
最新の対象職種・作業一覧は厚生労働省や外国人技能実習機構(OTIT)の公表資料をご確認ください。こちらをご確認ください。参照:▶ OTIT 外国人技能実習機構
技能実習から特定技能への移行条件と制度改正
技能実習2号から特定技能1号へ移行する要件
技能実習制度を修了した人材の一部は、特定技能1号への移行が可能です。移行には「技能実習2号を良好に修了していること」が要件となり、同一分野であれば技能評価試験や日本語試験は原則免除されます。これにより、技能実習で培った経験を活かしながら、日本での就労を続けることができます。ただし、移行対象は限定された職種・作業であるため、自社の業務が対象に含まれるかを確認することが不可欠です。
特定技能2号による長期就労の可能性
特定技能2号は、在留資格の更新を繰り返すことで長期在留が可能となる制度です。技能実習を経て特定技能1号に移行し、その後さらに2号に進めば、より長期的に日本で働く道が開かれます。2023年の制度改正により、介護を除くほぼ全ての特定産業分野で2号への移行が可能となっています。企業にとっては長期的な戦力確保につながる可能性があります。
最新制度改正(2025年4月施行)のポイント
2025年4月から施行される制度改正では、入国前の結核スクリーニング義務化などが盛り込まれています。これにより、受け入れ企業は従来以上に適正な運用を求められることになります。その他の改正内容については、最新の官報や法務省・厚生労働省の発表を確認することが重要です。
技能実習生受け入れ企業が押さえるべき実務ポイント
実習計画の作成と必要書類の流れ
技能実習を受け入れるには、技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)への申請・認定を受ける必要があります。計画には職種や作業内容、指導体制、日本語教育の方法などを具体的に盛り込まなければなりません。また、雇用契約書や在留資格申請に必要な書類を整える手間も発生します。こうした準備を怠ると認定が下りないため、制度上の流れを把握したうえで確実に対応することが重要です。
日本語教育・生活支援の体制づくり
技能実習生が安心して生活できる環境を整えることは、企業にとって大きな責任の一つです。住居の確保、生活用品の準備、通信インフラの整備など、生活支援に関する体制を整備する必要があります。特に日本語教育は、業務効率や安全確保に直結するため、計画的に実施することが求められます。
監理団体との連携と支援機関の役割
団体監理型を選択する場合、監理団体が定期巡回や書類点検を行います。企業は監理団体との連携を通じて、制度が適正に運用されるよう協力しなければなりません。また、監理団体の多くは協同組合など非営利法人を母体としており、生活支援や日本語教育に関する支援も提供します。受け入れ企業は自社の体制と監理団体の役割を切り分け、両者を効果的に活用することが大切です。
コスト・メリット・デメリットを比較検討する方法

技能実習生を受け入れる場合、企業には一定の費用と同時に多面的な効果が伴います。具体的には以下のような点が挙げられます。
-
事務手続きや監理団体への委託にかかる費用
-
住居の確保や生活支援に要するコスト
-
人材確保の安定性による計画的な雇用の実現
-
技能移転を通じた国際貢献と企業イメージの向上
こうしたコストとメリット・デメリットを総合的に比較し、自社にとって最適な活用方法を判断することが重要です。
このように、技能実習の受け入れには計画立案から支援体制の整備まで幅広い準備が必要です。
まとめ|技能実習生の受け入れメリットデメリットを理解して制度を正しく活用
外国人技能実習生の受け入れには、人材確保や国際貢献といったメリットがある一方で、日本語教育や管理コスト、法令遵守といった課題も伴います。特に建設業や製造業など主要分野では、制度の枠組みや移行条件を理解したうえで導入を進めることが不可欠です。受け入れ企業は、制度の目的が「技能移転」にあることを踏まえ、メリットとデメリットを比較検討しながら準備を整えることが重要です。最新の制度改正にも注意を払い、専門機関や監理団体と連携することで、安心して技能実習制度を活用できます。
オープンケア協同組合では、住居や生活支援、日本語教育までを含む包括的な受け入れ支援を提供しています。初めて外国人技能実習生を受け入れる企業の方も、制度の理解から実務の準備まで安心してご相談いただけます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/


とは?技能実習制度における対象作業と申請要件を徹底解説-640x360.jpg)