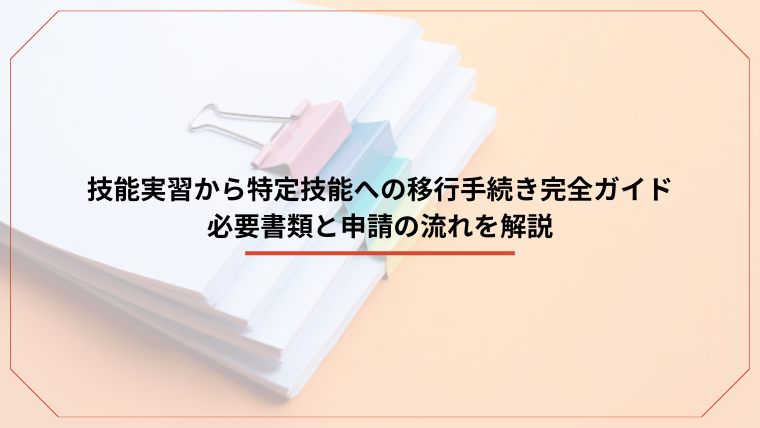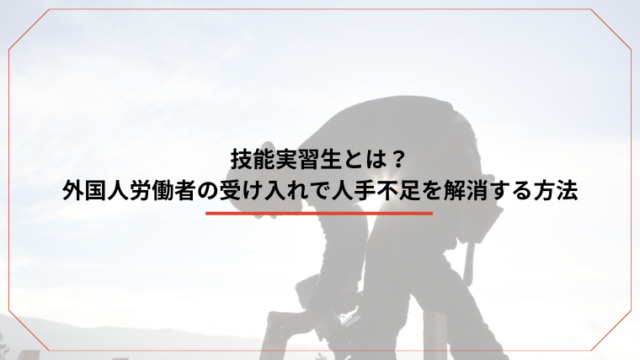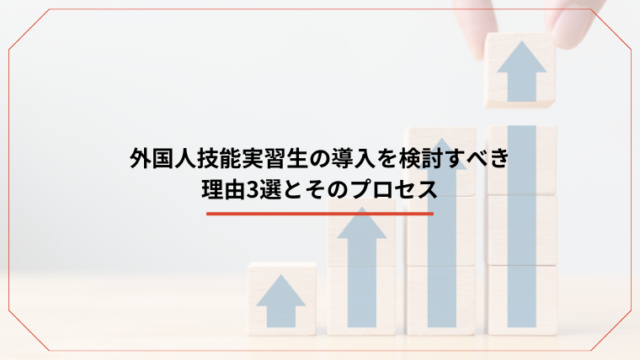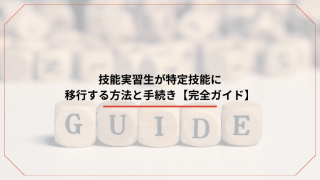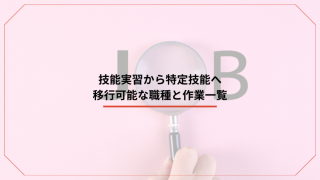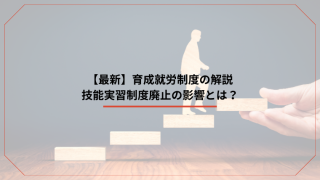特定技能1号への移行は、技能実習2号を修了した外国人が日本で継続して働くための重要なステップです。
企業にとっては、即戦力となる外国人材を継続雇用できるという大きなメリットがありますが、移行には在留資格変更の申請が必要であり、正確な書類の準備と適切な手続きが求められます。
本記事では、企業が準備すべき書類、外国人本人が用意する書類、申請の流れ、手続き上の注意点について詳しく解説します。特定技能への移行をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
移行手続きに必要な書類一覧
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号へ移行するためには、企業側と外国人本人の両方が必要な書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請する必要があります。 書類の不備があると審査が遅れる可能性があるため、事前に必要書類を把握し、正確に準備することが重要です。
企業が準備すべき書類と取得方法
企業が特定技能外国人を受け入れる際には、以下の書類を用意する必要があります。
| 書類名 | 取得方法・記入時のポイント |
| 雇用契約書 | – 外国人本人との労働契約内容を明記(賃金、労働時間、業務内容 など)
– 日本人と同等以上の待遇であることを確認 |
| 支援計画書 | – 特定技能外国人の生活・就労支援計画を作成(住居確保、生活指導、日本語学習支援 など)
– 自社で実施するか、登録支援機関に委託するかを明確にする |
| 会社概要書 | – 企業の基本情報(事業内容、資本金、従業員数 など)を記載
– 事業の安定性を証明するための重要書類 |
| 直近の決算書 | – 企業の経営状況を示す書類(損益計算書・貸借対照表)
– 企業の財務状況を確認されるため、最新のものを提出 |
| 特定技能所属機関の誓約書 | – 企業が特定技能外国人を適正に雇用・管理することを誓約する書類
– 出入国在留管理庁の指定フォーマットを使用 |
| 社会保険・雇用保険加入証明書 | – 外国人労働者が適正に保険加入していることを証明するための書類
– 健康保険証や労働保険の加入状況を確認 |
| 役員の住民票(法人の場合) | – 企業の代表者の住所を証明するために必要
– 市区町村役場で取得可能 |
これらの書類を準備する際は、申請内容に不備がないか事前に確認し、スムーズな手続きを進めることが大切です。
外国人本人が用意する書類と記入時の注意点
特定技能1号への移行手続きでは、外国人本人が準備しなければならない書類も複数あります。これらの書類に不備があると、申請が遅れたり、不許可となる可能性があるため、慎重に準備を進めることが重要です。
以下に、必要な書類の一覧と、それぞれの取得方法・記入時の注意点をまとめます。
1. 必要書類一覧と取得方法
| 書類名 | 取得方法・記入時のポイント |
| 在留資格変更許可申請書 | – 出入国在留管理庁の指定フォーマットを使用し、正確に記入する。
– 企業側の情報と一致していることを確認する。 |
| 在留カード(コピー) | – 現在の在留カードの両面コピーを提出。
– 在留期限が近い場合は、早めに申請を行う。 |
| パスポート(コピー) | – 顔写真ページと最終入国記録のページをコピー。
– 有効期限が切れていないか事前に確認。 |
| 技能実習修了証明書 | – 技能実習を適正に修了したことを証明する書類。
– 監理団体または受け入れ企業から発行してもらう。 |
| 技能検定試験の合格証(基礎級または随時3級) | – 技能実習2号を修了した証明として提出が必要。
– 紛失した場合は、発行機関に再発行を依頼する。 |
| 日本語能力試験の合格証(該当する場合) | – 一部の業種では、日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic試験の合格が必要。
– 技能実習2号を修了している場合は免除されるケースもあるため、確認が必要。 |
| 住民票(最新のもの) | – 市区町村役場で取得可能。
– 住所変更があった場合は、最新の情報に更新しておく。 |
| 健康保険証(コピー) | – 社会保険に加入していることを証明するために提出。
– 未加入の場合は、企業側で適切な手続きを進める必要がある。 |
2. 記入時の注意点
- すべての書類は最新の情報を記載すること
- 古い情報が記載された書類を提出すると、不備となる可能性があるため、申請前に最新の情報へ更新することが重要です。
- 企業側の書類と整合性を取ること
- 雇用契約書や支援計画書の内容と、在留資格変更許可申請書の情報が一致しているか事前に確認する。
- 日本語での記入が求められる場合がある
- 書類によっては、日本語での記入が求められるため、不安がある場合は企業担当者や行政書士に確認しながら作成する。
- 提出期限を守り、在留期限切れにならないよう注意
- 在留期限が切れる前に、少なくとも3か月前には申請準備を開始するのが望ましい。
外国人本人が適切に書類を準備し、企業側と連携して申請を進めることで、特定技能1号へのスムーズな移行が可能になります。
申請の流れと各ステップの詳細
技能実習2号から特定技能1号へ移行するためには、在留資格変更の申請を行い、出入国在留管理庁の審査を経て許可を取得する必要があります。
企業と外国人本人が協力し、必要な書類を準備し、適切なスケジュールで手続きを進めることが重要です。
在留資格変更の申請手続きとスケジュール
特定技能1号への移行手続きは、複数のステップを経て完了します。以下に、申請から許可取得までの流れとスケジュールの目安をまとめます。
1. 事前準備(申請前の確認)【1〜2か月前】
2. 在留資格変更許可申請の提出【在留期限の2〜3か月前】
3. 出入国在留管理庁の審査【1〜2か月】
4. 在留資格変更許可の取得【審査完了後】
5. 就労開始と報告義務【許可取得後すぐ】
申請のスケジュールを把握し、余裕をもった対応が重要
特定技能1号への移行には、最低でも2〜3か月の期間が必要です。在留期限が切れる前に申請が間に合わないと、一時帰国が必要になる場合もあるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
出入国在留管理庁での審査と承認の流れ
技能実習2号から特定技能1号へ移行するためには、出入国在留管理庁(入管)での審査を経て、在留資格変更の許可を得る必要があります。 審査では、外国人本人の適格性だけでなく、受け入れ企業の適正性や雇用条件も厳しくチェックされるため、事前準備が重要です。
1. 申請受理と書類審査
【審査期間:1〜2か月】
申請書類が受理されると、入管で書類審査が行われます。
審査の主なポイントは以下のとおりです。
審査の途中で不明点がある場合、追加書類の提出を求められることがあるため、申請後も速やかに対応できるよう準備しておくことが重要です。また、2025年1月以降は窓口の混雑や審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されると出入国在留管理庁は告知しています。余裕にもった行動が大切です。
(参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001427304.pdf)
2. 企業の適格性審査
入管では、企業が特定技能外国人を適正に受け入れる体制が整っているかを審査します。主なチェックポイントは以下の通りです。
財務状況が不安定な企業や、過去に労働基準法違反があった企業は、不許可となる可能性が高くなります。
3. 在留資格変更許可の通知と新しい在留カードの受け取り
新しい在留カードを受け取った後、企業は雇用契約に基づき特定技能外国人を正式に雇用開始できます。
4. 企業が行うべき報告義務
在留資格変更が完了した後、企業には定期的な報告義務があります。
報告義務を怠ると、次回の特定技能外国人の受け入れが認められなくなる可能性があるため、適正な管理が求められます。
申請時に注意すべきポイント
技能実習2号から特定技能1号へ移行する際、書類の不備や手続きの遅延によって、審査が長引いたり、不許可となるリスクがあります。 申請をスムーズに進めるためには、書類の正確な準備、提出期限の厳守、適正な雇用環境の整備が必要です。
ここでは、企業側・外国人本人が特に注意すべきポイントを整理し、移行手続きを確実に進めるための対策を解説します。
書類不備を防ぐためのチェックリスト
申請時に最も多い問題は、書類の不備や内容の不一致です。以下のチェックリストを活用し、提出前に必ず確認を行いましょう。
1. 企業が確認すべき書類のポイント
| 確認項目 | チェックポイント |
| 雇用契約書 | 日本人と同等以上の待遇が確保されているか、業務内容が特定技能1号の対象範囲に収まっているか |
| 支援計画書 | 外国人の生活・就労支援内容が適切に記載されているか、自社で対応できるか、登録支援機関に委託するか明確か |
| 会社概要書 | 企業の事業内容・資本金・従業員数が最新の情報になっているか |
| 社会保険加入証明書 | 外国人労働者が適正に社会保険・雇用保険へ加入できる状況か |
| 決算書 | 直近の財務状況が健全であり、外国人雇用の維持が可能であることを証明できるか |
2. 外国人本人が確認すべき書類のポイント
| 確認項目 | チェックポイント |
| 在留資格変更許可申請書 | 企業が作成した雇用契約書と内容が一致しているか |
| 在留カード(コピー) | 有効期限が切れていないか、記載情報が最新か |
| パスポート(コピー) | 申請時に有効期限が十分に残っているか |
| 技能実習修了証明書 | 技能実習2号を適正に修了している証明書が揃っているか |
| 技能検定試験の合格証 | 免除対象ではない場合、特定技能評価試験に合格しているか |
| 住民票 | 住所変更がある場合、最新のものを取得しているか |
3. 申請時の注意点
- 在留期限に余裕をもって申請する
- 在留資格変更の審査には1〜2か月かかるため、在留期限の3か月前には準備を開始する。
- 期限を過ぎると一時帰国が必要となり、企業にも負担がかかるため注意が必要。
- 企業と外国人本人の書類の整合性を確認する
- 申請書類の記載内容に不一致があると、追加資料の提出を求められることがある。
- 企業が作成する雇用契約書や支援計画書と、外国人本人の申請内容が一致しているかチェックする。
- 書類提出後も連絡をこまめに確認する
- 追加書類の要求があった場合、速やかに対応できるよう準備しておく。
- 企業担当者と外国人本人が、入管からの通知を随時確認し、審査遅延を防ぐ。
4. 企業の受け入れ体制を適正化する
まとめ:スムーズな移行手続きを実現するために
技能実習2号から特定技能1号への移行は、企業にとって即戦力となる外国人労働者を長期的に確保できる重要な手段です。しかし、手続きをスムーズに進めるためには、必要書類の準備、適切な雇用契約の締結、在留資格変更のスケジュール管理が求められます。
特定技能外国人の受け入れには、生活支援や労働環境の整備が必要ですが、登録支援機関を活用することで、企業の負担を軽減することが可能です。
適切な準備と管理を行うことで、特定技能外国人の安定した雇用を実現し、企業の人材確保を成功させることができます。