農業分野で技能実習生の受け入れを検討しているものの、制度の仕組みや準備内容に不安を感じていませんか?本記事では、耕種農業・畜産農業における技能実習制度の概要と、受け入れに必要な準備のポイントをわかりやすく解説します。スムーズな導入判断のための参考にしてください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
農業分野における技能実習制度とは?

制度の目的と農業における位置づけ
技能実習制度は、開発途上国の人材に日本の技術や知識を習得してもらい、母国の発展に貢献することを目的とした国際協力制度です。農業分野はその対象業種の一つであり、耕種・畜産の現場で培われた技能を技能実習生が学び、帰国後に生かすことが期待されています。
単なる労働力確保ではなく、「技術移転」を重視するこの制度は、受け入れ企業にも教育的な役割が求められます。農業現場においても、指導体制の整備や技能向上のサポートが重要とされ、制度を正しく理解したうえでの活用が不可欠です。
耕種農業と畜産農業での適用範囲
農業分野の技能実習は、大きく「耕種農業」と「畜産農業」に分類され、それぞれに対象となる作業範囲が定められています。
耕種農業の例
- 野菜・果樹・稲作などの栽培作業
- 播種、苗の管理、収穫、出荷準備など
畜産農業の例
- 乳牛・肉牛・豚・鶏などの飼養管理
- 給餌、清掃、搾乳、健康観察など
いずれも「技能実習評価試験」によって技術習得の程度が確認されるため、単純作業ではなく体系的な教育と経験の提供が求められます。
農業分野での実習生数と導入傾向
農業分野は他業種と比べて自然条件や季節性の影響を受けやすく、人材確保が困難な地域も多いため、技能実習制度を活用する事業者が年々増加しています。
出入国在留管理庁の統計によると、農業分野における外国人技能実習生は全体の中でも割合が増えており、特に地方圏や中山間地域での導入が進んでいます。繁忙期の戦力としてだけでなく、技術の継承者という側面からも注目が高まっている分野です。
後も農業現場での実習生受け入れは重要な選択肢として位置づけられていくと考えられます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
受け入れ対象となる農業作業の種類と具体例
耕種農業での代表的な作業内容
耕種農業とは、野菜・果樹・穀物などを育てる農業全般を指します。技能実習制度においても、耕種農業は多くの実習生が従事する代表的な分野の一つです。主な作業は以下のとおりです。
- 種まき、育苗、植え付け
- 雑草・害虫の防除、施肥管理
- 収穫、選別、箱詰めなどの出荷作業
- ビニールハウスや設備の管理作業
これらの作業は、単に作業手順を覚えるだけでなく、栽培時期の理解や品質管理などを含めた技能教育として評価されます。
畜産農業での代表的な作業内容
畜産農業では、家畜の飼育を中心に技能実習が行われます。対象となるのは乳牛・肉牛・豚・鶏などで、日々の健康管理や衛生的な飼養環境の維持が重要です。以下のような作業が一般的です。
- 給餌、水やり、糞尿処理といった日常管理
- 搾乳や分娩時の補助
- 飼養施設の清掃・消毒
- 体調チェックや飼料の調整
動物の命を預かる仕事であるため、細やかな観察力や責任感が求められます。受け入れる側には、衛生管理や安全教育の徹底が必要です。
実習内容と技能評価試験の対応関係
技能実習制度では、一定期間ごとに評価試験が実施されます。これは実習内容が計画通り実施されているかを確認し、技能習得の達成度を客観的に測るものです。
試験には「基礎級」「随時2級」「随時3級」などがあり、例えば耕種農業では収穫や箱詰め、畜産農業では搾乳や飼養管理が評価対象となります。
評価試験の合格は次の段階への移行に必要であり、実習生と企業双方にとって重要な節目です。そのため、日々の実習が試験内容と直結していることを意識し、丁寧な指導が求められます。
現場でよく行われる業務例
農業現場で実習生が担当する作業の中でも、頻度が高く重要とされる業務を以下に示します。
- 畑やハウスでの収穫・出荷準備
- 苗の育成と管理
- 給餌・清掃などの飼養管理業務
- 設備の点検や環境衛生の維持
これらはすべて技能実習制度の評価項目とも連動しており、単純作業ではなく継続的な技能習得が求められる分野です。業務内容の選定は、受け入れ企業の体制と照らし合わせて行うことが重要です。
技能実習生を受け入れるまでの流れと準備すべきこと
監理団体の選定と契約の流れ
技能実習制度を活用するには、監理団体との契約が必要です。監理団体とは、企業と技能実習生の間に入り、制度運営を監督・支援する立場にある非営利組織です。農業分野での実習受け入れには、経験豊富で農業に理解のある監理団体を選ぶことが成功のカギとなります。
契約時には、受け入れ可能人数や費用、サポート内容などを明確に確認しましょう。また、監理団体によっては、実習生の選抜・入国手続き・講習・住居支援まで幅広く対応可能な場合があります。
実習計画の作成と申請手続き
技能実習は、実習計画の認定を受けたうえで開始されます。この計画には、対象業務や教育方法、評価方法、指導体制などを詳しく記述し、出入国在留管理庁に申請する必要があります。
実習計画の構成要素
- 作業工程・指導内容
- 評価試験の時期
- 生活支援の体制
- 日本語指導や相談窓口の設置
作成には専門知識が必要となるため、多くの場合は監理団体のサポートを受けながら進めます。不備があると認定が下りないこともあるため、丁寧な準備が重要です。
寮・生活環境の整備に関する注意点
技能実習生の受け入れには、適切な生活環境の提供も求められます。特に農村地域では交通手段や通信環境に課題があるケースも多いため、事前の整備が不可欠です。
最低限整えておくべき環境
- 清潔で安全な住居(個室または2人部屋推奨)
- 冷暖房・照明・調理器具・寝具の完備
- Wi-Fiなどの通信インフラ
- スーパーや病院などへのアクセス手段
生活の安定は実習の定着率にも直結するため、受け入れ前に十分な準備を行いましょう。
事前講習と受け入れ前の対応
実習生は入国後、一定期間の「講習」を受けてから配属されます。講習では日本語教育、生活ルール、防災・交通安全、職場でのマナーなどが教えられます。事業者はこの講習の内容を把握し、現場でも同様の対応ができるよう準備しておく必要があります。
また、Zoomなどを活用した事前の顔合わせや面談を行えば、配属後の不安を軽減し、スムーズな関係構築に役立ちます。言語や文化の違いを理解した上での、丁寧な導入が重要です。
地域との共生に向けた配慮
農業は地域社会とのつながりが強いため、実習生がその土地で安心して暮らせる環境づくりも大切です。受け入れ地域でのサポート体制や理解促進に向けた取り組みが推奨されます。
配慮すべき地域共生のポイント
- 近隣住民との関係構築(あいさつや紹介の場の設置)
- 行政との連携(住民票、保険加入、相談窓口の共有)
- 地域イベントへの参加や交流促進
地域社会との信頼関係が築ければ、実習生も安心して長く働くことができ、雇用の安定にもつながります。
実習開始後のフォロー体制
実習生が配属された後も、定期的な面談や生活相談、業務フィードバックなどのサポートが欠かせません。特に言葉や文化の壁がある初期段階では、丁寧なフォローが離職防止にもつながります。
指導員を中心とした育成体制を整え、トラブル時の対応マニュアルを事前に用意しておくと安心です。また、監理団体による定期巡回や報告書の提出も義務づけられているため、企業と団体の協力体制が鍵となります。
農業で技能実習生を受け入れるメリットと想定される課題
農作業の継続性
技能実習生の導入は、作業の効率化や標準化にもつながります。実習計画に基づいた業務分担や教育が行われることで、作業内容の明確化や改善が進みやすくなります。
実習生受け入れによる業務の変化
- 作業マニュアルの整備が進む
- 日本人従業員の指導スキルが向上
- 若手社員との連携による業務の可視化
- チームワークや役割分担の明確化
結果として、農場全体の運営効率が高まり、次世代への技能継承にも好影響を与えるケースが増えています。
実習生の生活適応や言語の課題
一方で、受け入れ時に配慮すべき課題も存在します。とくに生活環境の変化や言語の壁は、実習生の不安要素となり得ます。農村部では公共交通機関が乏しく、孤立しやすい状況にあるため、生活支援体制の構築が不可欠です。
また、日本語の理解度は個人差があり、業務指示が伝わりにくい場合もあります。翻訳アプリや図解資料の活用、日本語教育の継続など、実習生とのコミュニケーションを工夫することが重要です。
気候・文化の違いに対する配慮点
技能実習生は多くが東南アジア出身であり、日本の気候や文化に慣れるまでに時間がかかることもあります。特に冬場の寒冷地や、梅雨・台風などの気象条件はストレスの原因になる可能性があります。
文化・気候への配慮として効果的な工夫
- 服装・防寒具などの支援
- 食文化や宗教への理解(ハラル対応など)
- 地域習慣やゴミ出しルールの説明
- 孤立を防ぐための交流機会の創出
こうした配慮が実習生の満足度と定着率を高め、結果として現場全体の安定運営にもつながります。
技能実習制度を活用する農業経営者に求められる視点
指導体制と育成への姿勢
技能実習制度は「育成」を目的とした制度です。そのため、受け入れ事業者は労働力として扱うのではなく、指導者としての役割を担う必要があります。現場では、技能実習指導員や生活指導員などの担当者を配置し、日常業務の中で継続的に教育を行う体制を整えることが求められます。
また、実習生との信頼関係の構築も重要です。丁寧な指導と共に、褒める・認める姿勢を持つことで、実習生の意欲を高め、職場全体の雰囲気も良くなります。
長期的な雇用設計とキャリア支援
実習生の受け入れは一時的な対処策ではなく、農場経営における人材育成の一環と捉えることが望ましいです。技能実習2号を修了した実習生は、一定条件を満たせば「特定技能」など他の在留資格へ移行し、より長く働き続けることも可能です。
長期的な視点での雇用設計に必要な考え方
- 実習後のキャリアパスを想定した指導
- 技能・責任に応じた業務配置の見直し
- 日本語教育や資格取得の支援体制の充実
- 退職・帰国後のフォローや関係継続
こうした取り組みは、技能実習制度の本来の趣旨にも合致し、将来にわたって良好な人材循環を実現する基盤となります。
法令遵守と人権配慮の重要性
技能実習制度には、実習生の権利保護に関する厳格なルールが定められています。労働時間や賃金、休暇の取得、安全衛生の確保など、日本人と同等以上の待遇が必要です。違反があれば制度利用停止や罰則の対象にもなります。
加えて、実習生に対するハラスメントや差別の禁止、相談窓口の設置など、人権配慮も不可欠です。制度を正しく運用することは、農場経営者自身の信頼を守り、持続的な人材確保にもつながります。
まとめ|国際貢献と農業経営の両立を実現するために

農業分野での技能実習生受け入れは、現場の人手不足に対処するだけでなく、技術伝承や業務の効率化にもつながる有効な手段です。ただし、制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、正しい理解と適切な準備が求められます。
耕種農業・畜産農業における作業内容は明確に定められており、受け入れには監理団体との連携、生活環境の整備、教育体制の構築など多くのステップが必要です。一方で、丁寧な対応と信頼関係の構築により、実習生の定着率や現場の活性化といった大きな成果も期待できます。
初めての受け入れに不安を感じている事業者の方は、専門機関に相談することでスムーズな導入が可能になります。制度を活用し、持続可能な農業経営の実現を目指しましょう。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/


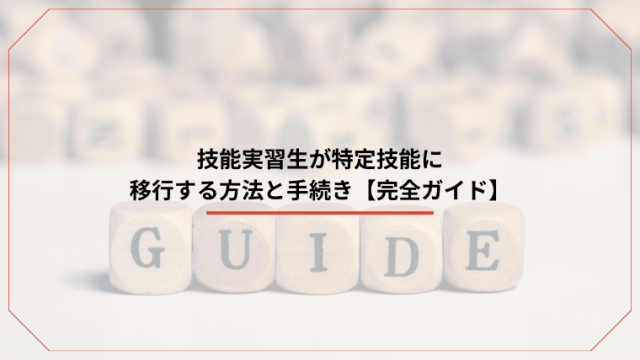



とは?技能実習制度における対象作業と申請要件を徹底解説-320x180.jpg)






