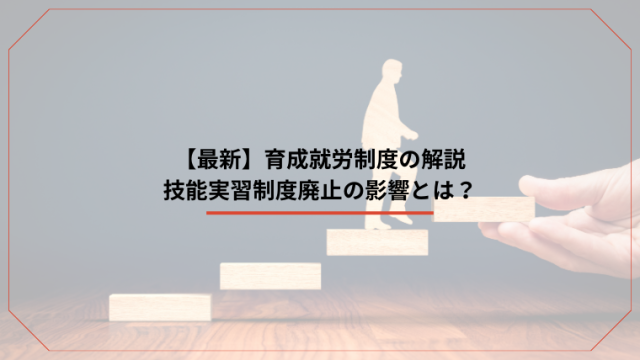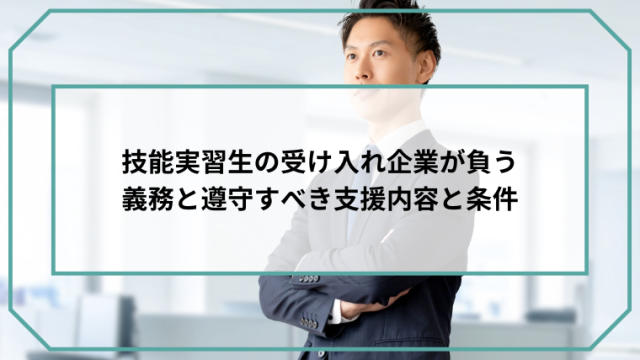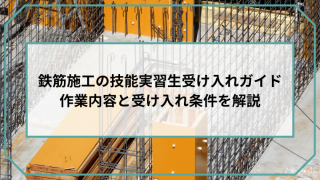石材施工分野で外国人技能実習生を受け入れる際、こんな疑問はありませんか?
- どの作業が技能実習の対象なのか分からない
- 受け入れ手続きや必要書類の流れを整理したい
- 安全管理や監理団体との関わり方を具体的に知りたい
石材施工は、切断・研磨から据え付けまで高い精度を求められる専門分野です。制度の理解や準備が不十分だと、申請の遅延や監査での指摘につながるおそれもあります。
本記事では、石材施工分野で技能実習生を受け入れるための制度概要・要件・手続き・リスク管理を体系的に解説します。初めての企業担当者でも安心して導入準備を進められる実務ガイドです。
外国人技能実習の受け入れを検討中の企業様へ
オープンケア協同組合では、制度手続き・生活支援・教育体制をワンストップでサポートしています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
石材施工分野の技能実習について
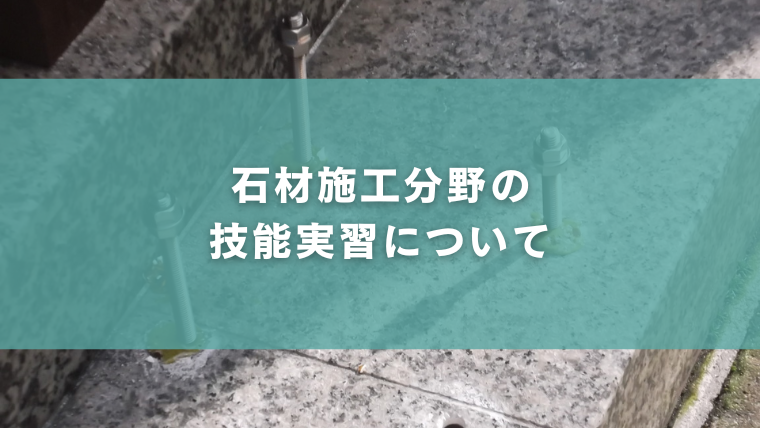
石材施工分野が技能実習制度に含まれる理由
石材施工は、建設や製造分野の中でも高い精度と経験を要する専門技能の一つです。日本では墓石・外構材・建築装飾材など多様な石材加工技術が発展しており、これらの技能を国際的に移転することが制度目的とされています。
外国人技能実習制度における石材施工は、「石材加工作業」「石材施工作業」の2作業が対象とされ、技能移転を通じた国際協力の一環として位置づけられています。実習生は、石材の切断・研磨・据え付けなど、実地訓練を通して専門技能を学び、母国での産業発展に活かすことが期待されています。
制度の目的と特徴(技能移転としての国際協力)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)は、単なる労働力供給を目的とせず、開発途上国への技能移転による国際協力を目的としています。
技能実習生は、一定期間の日本企業での実習を通じて、石材加工・施工技術を体系的に習得します。制度上、技能実習1号(基礎習得段階)から2号(応用段階)、さらに条件を満たせば3号(高度段階)へと進むことができます。
また、制度運用においては、監理団体による監査・支援体制が義務づけられており、企業単独での受け入れではなく、団体監理型を通じた適正運用が原則とされています。
石材施工の職種・作業区分と具体例
技能実習制度で認定されている石材施工の職種区分は、以下の2作業です。
- 石材加工作業:原石を切断し、研磨や穴あけを行い、墓石・壁材などに加工する工程
- 石材施工作業:加工された石材を現場で据え付け、仕上げ、固定する工程
これらの作業は、建設分野(22職種33作業)の中に位置づけられています。
2025年度(令和7年)改正での変更点
令和7年4月1日施行の制度改正では、監理団体の監査期間の短縮や、健康診断・結核スクリーニングの義務化、宿泊施設基準の見直しなどが盛り込まれています。石材施工分野でも、安全衛生管理と実習環境の整備がより厳格に求められるようになります。
また、深夜労働の認定要件が明確化され、現場作業の安全配慮義務も強化されました。今後、実習計画作成時には、法令遵守・労働時間管理・宿舎整備の3点が重点確認項目です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
石材施工で技能実習生を受け入れるための要件
実習実施者(受け入れ企業)の認定要件
実習生を受け入れる企業は「実習実施者」としての認定が必要です。認定には、過去に労働基準法違反がないこと、適正な労働環境を維持できる体制が整っていることなどが求められます。
また、指導体制・作業設備・安全衛生管理の3点が審査対象となり、現場ごとの管理体制を明文化した技能実習計画の認定申請を行う必要があります。
必要な設備・安全衛生管理体制
石材施工では、重量物の取り扱いや切断・研磨機器の使用など、労働安全上のリスクが伴います。企業は、労働安全衛生法に基づく機械設備の点検や防護具の支給、教育訓練を徹底しなければなりません。
特に研磨装置や切断機器などの使用時には、粉じん・騒音への対策が不可欠です。監理団体も、現場巡回で安全対策の実施状況を確認し、改善指導を行います。
指導員・生活指導員の配置義務と支援内容
技能実習法では、指導員・生活指導員の配置が義務づけられています。
- 技能指導員:実習生に対して技能・作業手順を教える
- 生活指導員:住居・食事・健康管理など日常生活を支援する
これらの担当者が連携し、職場での指導・生活のフォローを行うことで、実習生が安心して技能を学べる環境が整います。監理団体は定期的に面談を実施し、課題の早期把握と改善を支援します。
このように、受け入れ要件を満たすことが技能実習制度の適正運用の前提条件です。
併せて読みたい ▶ 技能実習生の生活指導員とは?講習の内容・役割・配置義務までわかりやすく解説
技能実習の流れと石材施工における評価試験
入国前後講習と実習ステップ(1号→2号→3号)
石材施工の技能実習は、入国前と入国後の講習を経て、段階的に技能を習得する仕組みです。
入国前には、送出し国で日本語や生活基礎を学ぶ事前教育が行われます。入国後には、労働安全や生活ルールに関する講習(31時間以上)が義務づけられています。
技能実習は、以下の3段階で構成されます。
- 技能実習1号:基礎的技能を学ぶ(1年以内)
- 技能実習2号:応用的技能の習得(2年または3年)
- 技能実習3号:優良企業のみ認定される高度実習(最長2年)
このように段階的に学ぶことで、技能移転の目的を実践的に達成できます。
石材施工の技能評価試験(基礎級/随時3級/随時2級)
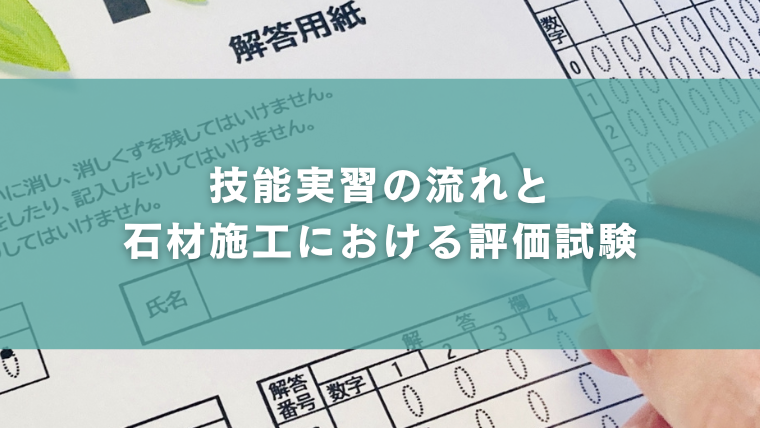
石材施工分野の技能評価試験は、技能実習生の能力を客観的に確認するために実施されます。試験区分は「基礎級」「随時3級」「随時2級」と定められており、石材加工作業・石材施工作業の両方で実施されます。
各級の概要は以下の通りです。
- 基礎級:入国後の初期段階で受験。切断・研磨などの基礎動作を評価
- 随時3級:技能実習2号移行時の必須試験。製品精度や作業効率を評価
- 随時2級:技能実習3号認定に必要な上級試験。施工管理・仕上げ品質を評価
これらの試験に合格すると、制度上のステップアップが可能になります。
石材施工における主な作業内容と周辺業務
石材加工作業の具体例(切断・研磨・穴あけ)
石材加工作業では、原石を用途に応じて加工し、建築や墓石、装飾用途に仕上げます。主な工程は次の通りです。
- 原石の切断(大型カッターやワイヤーソーを使用)
- 研磨・表面仕上げ(艶出しやマット仕上げなど)
- 穴あけ・溝加工(装飾部材や組立用パーツに対応)
- 寸法・表面品質の確認(検査業務を含む)
これらの工程では、精度・安全性・機械操作スキルが求められます。実習生は、これらの技能をOJT形式で習得します。
石材施工作業の流れと現場での役割
石材施工作業は、加工済みの石材を現場で設置し、建築物やモニュメントなどを仕上げる工程です。現場では、図面に基づいて基礎据え付けを行い、接着・目地仕上げ・清掃まで一連の作業を担当します。
特に、重量物の取り扱いやクレーン作業を伴うため、安全確認とチーム作業の連携が欠かせません。施工現場では、安全衛生業務の遵守が最も重要なポイントになります。
監理団体と企業の連携ポイント
団体監理型のサポート内容と監査体制
石材施工分野の技能実習は、団体監理型で運用されるのが原則です。監理団体は、企業が実習計画を適正に実施しているかを定期的に確認し、制度遵守を支援します。主な監査内容は次のとおりです。
- 実習生の労働時間・報酬・勤務内容の確認
- 安全衛生管理・宿舎環境の点検
- 技能指導・教育計画の整合性確認
- 実習生との面談および相談対応
監理団体は、こうした監査と併せて、実習生と企業の間のトラブルや不安の早期把握・調整も担います。 労働条件・生活環境・人間関係などに関する相談窓口を常設し、必要に応じてOTITや行政機関と連携し、法令違反や人権侵害の防止に努めます。
これにより、企業の運用リスクが低減し、実習生が安心して技能を習得できる環境が維持されます。監理団体の監査と相談体制は、制度の透明性と信頼性を支える重要な仕組みです。
監理団体選定時のチェックポイント
監理団体を選定する際は、以下の項目を必ず確認しておくことが重要です。
□ 外国人技能実習機構(OTIT)に正式登録されているか
□ 定期監査や巡回報告の実績があるか
□ 通訳体制・生活支援など多言語対応が整っているか
□ 行政指導や処分歴がないか
これらを確認することで、法令遵守と支援力の高い団体かどうかを判断できます。特に、
報告体制・相談対応力・教育支援の3点は評価の基準となります。
管理団体について詳しく知りたい方はこちら ▶ 監理団体とは?技能実習制度における役割や業務、安心できる監理団体の選び方を解説
石材施工分野での受け入れ手続きと必要書類
技能実習計画認定の申請フロー
技能実習の開始には、受け入れ企業が作成した技能実習計画を監理団体経由で外国人技能実習機構(OTIT)に提出し、認定を受ける必要があります。主な流れは次のとおりです。
- 技能実習計画の作成(実習内容・指導体制・安全衛生・評価の方法を明記)
- 監理団体による確認・添削
- OTITへの提出・審査
- 認定通知の受領後、在留資格手続きへ進行
在留資格認定証明書交付申請の手順
計画認定後、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います(監理団体が代理提出するのが一般的です)。提出書類の例は、登記事項証明書、雇用契約書、技能実習計画の認定通知書などです。交付後は、送出し国での査証申請・入国手続きに進みます。書類の整合性と最新様式の確認が遅延防止のポイントです。
書類準備とOTITへの届出・受け入れ準備のポイント(統合)
OTIT提出・各種届出と並行して、受け入れ準備を計画的に進めます。審査・監査で確認されやすい書類は次のとおりです。
- 実習生名簿、雇用契約書
- 技能実習責任者・技能指導員・生活指導員の任命書
- 労働保険・社会保険の加入確認書類
- 宿舎契約書、安全衛生計画、教育計画(日本語・安全)
上記の書類整備と同時に、現場側の受け入れ準備も必須です。宿舎と生活用品の確保、日本語講習・安全教育の日程調整、OJT開始日の設定、医療機関と緊急連絡体制の確認を監理団体と共有し、入国日から実習開始までの段取りを前倒しで固めます。書類の精度と現場準備の両立が、入国後の混乱を防ぎ適正運用につながります。
この手続きと準備が整えば受け入れの土台は完成です。
技能実習生の安全管理とリスク回避のポイント
安全衛生業務の基本と法令遵守
石材施工分野は、重量物や切断機器を扱うため、安全衛生管理が最重要課題です。
企業は、労働安全衛生法に基づき、危険源の特定・防止措置・教育訓練を体系的に行う必要があります。
参照 ▶ 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索
具体的には、以下のような取り組みが求められます。
- 粉じん・騒音対策(集塵機の設置、防音設備)
- クレーン・フォークリフト等の有資格者による作業管理
- 安全帯・保護具の着用徹底
- 作業開始前ミーティングでの危険予知活動(KY活動)
監理団体は、これらの安全対策が適切に実施されているか定期的に巡回確認し、改善指導を行います。安全確保は実習生の信頼と定着につながる最も重要な要素です。
文化・言語への配慮と生活支援
技能実習生が安心して働くためには、文化的・言語的な配慮も欠かせません。
石材施工はチームでの協働作業が中心のため、コミュニケーションの円滑化が職場安全にも直結します。
多言語対応マニュアルの整備、翻訳アプリの活用、休日の生活支援などを行うことで、実習生の孤立を防ぎ、定着率の向上につながります。
また、生活指導員が日常の困りごとを早期に把握できるよう、週1回以上の面談体制を設けることが推奨されます。
石材施工分野では、技術面の教育と同じくらい、安全・人権・文化配慮の管理が重要です。参照 ▶ 厚生労働省「技能実習指導員に関するもの」
まとめ|石材施工分野の技能実習を適正に運用するために
石材施工分野の技能実習は、加工・施工技術の国際移転を通じて産業の発展に寄与する重要な制度です。
企業は、制度の目的を理解した上で、受け入れ要件・安全衛生・教育体制を整え、監理団体と密に連携することが求められます。
制度を適正に運用し、技能移転を実現することが、企業の信頼向上と国際的な人づくり支援につながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/