建設現場で重要な仕上げ工程を担うタイル張り作業。
この分野で外国人技能実習生を受け入れたいと考える企業も増えていますが、実際には次のような疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。
- タイル張りの技能実習ではどんな作業を行うのか
- 技能評価試験の内容や合格基準はどうなっているのか
- 企業が受け入れる際に必要な条件や注意点は何か
この記事では、タイル張り分野の技能実習制度の概要から、実習内容・評価試験・受け入れの流れまでをわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、安心して受け入れ準備を進めるための実務ポイントを整理しました。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
タイル張り作業とは?技能実習制度での位置づけ

技能実習制度における「タイル張り作業」の位置づけ
タイル張り作業は、建設分野の中で技能実習制度上認められた作業の一つです(建設22職種33作業の中の作業区分に含まれます)。技能実習制度は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき運用され、目的は技能移転を通じた国際協力です。
タイル張り作業の実習では、壁・床面のタイル施工、下地調整、モルタルや接着剤の使用、仕上げ精度の確認など、施工品質を重視した技能を学びます。特に、水平・垂直・目地幅の均一性など、精密な作業が評価の中心となります。
実習生が学ぶ技能範囲と必要な知識
実習で学ぶ内容は、材料知識・安全衛生・施工精度の3点を軸に体系化されています。初期段階では、タイル材や接着剤の取り扱い、安全確認などの基礎技能を、2号以降では施工計画や品質管理などの応用技能を習得します。
技能実習生が行うタイル張り作業の実習内容と流れ
入国後講習と日本語・安全教育
技能実習生は来日後すぐに、31時間以上の入国後講習を受けます。この講習は、技能実習法(正式名称:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)に基づく義務教育であり、すべての実習生に共通して実施されます。
講習内容は以下の通りです。
- 日本語基礎教育(あいさつ、作業指示の理解)
- 労働安全衛生の基礎(建設現場での危険回避方法)
- 法令遵守・人権保護・生活ルール
- 緊急時対応(災害・労災・健康管理)
この段階で「日本の働き方」「安全文化」「ルール遵守」の基本を理解させることが目的です。
タイル張り作業においては、特に高所作業や重量物の扱いがあるため、安全教育の徹底が不可欠です。
現場でのOJT(実地訓練)と指導体制
講習を終えると、技能実習生は受け入れ企業に配属され、OJT(On-the-Job Training:実地訓練)が始まります。
現場では、日本人の技能指導員が1名以上配置され、タイルの切断・接着・仕上げなど、工程ごとに段階的に指導を行います。
OJTでは以下のような内容が重点的に行われます。
- タイルの配置・割付け・貼付け手順の習得
- モルタル・接着剤の調合と塗布量の調整
- 作業後の検査・仕上げ確認(通り・目地のチェック)
- 廃材処理と現場清掃など、施工管理の一環
指導員は、文化や言語の違いを理解した上で、実技指導に加え安全面・生活面の相談役も担います。
監理団体も定期的に現場を巡回し、作業環境・安全対策・労働時間の適正性を確認しています。
技能実習1号・2号・3号の目的と違い
技能実習制度では、タイル張り作業を含むすべての職種において、1号→2号→3号という3段階の実習構造が定められています。
| 区分 | 主な目的 | 期間 | 修了・移行要件 |
| 技能実習1号 | 基礎技能の習得 | 1年以内 | 基礎級評価試験の合格 |
| 技能実習2号 | 応用技能の実践 | 2〜3年目 | 随時3級合格+適正実習報告 |
| 技能実習3号 | 熟練技能の実証 | 最大5年目 | 随時2級合格+優良団体の認定 |
実習が進むごとに作業範囲や責任が広がり、「技能の再現性」と「安全性」の両立が重視されます。
3号実習は、法務省・厚生労働省の定める優良監理団体・優良企業のみが実施可能です。
タイル張り作業における技能評価試験と合格のポイント
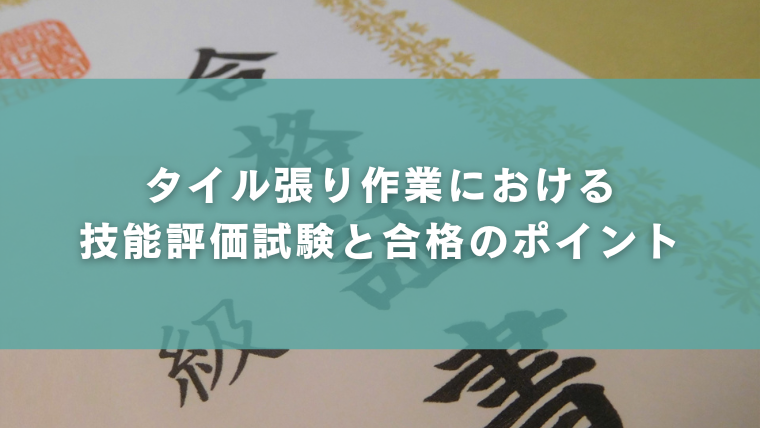
試験の体系と実施機関
タイル張り作業における技能評価試験は、中央職業能力開発協会が監修し、各地域の職業能力開発協会が実施します(JAVADAはこの試験の主管機関ではありません)。
試験体系は、実習段階に合わせて以下の3段階に分かれています。
| 試験区分 | 対応する実習段階 | 目的 | 主な内容 |
| 基礎級 | 技能実習1号修了時 | 基礎技能の確認 | タイル切断・貼付け・目地処理などの基本作業 |
| 随時3級 | 技能実習2号移行時 | 応用技能の評価 | 壁面・床面施工、施工精度・段取り確認 |
| 随時2級 | 技能実習3号移行/特定技能移行時 | 熟練技能の評価 | 図面読解、下地調整、仕上げ精度、作業管理 |
この試験は、外国人技能実習生専用の技能評価試験として設計されており、日本人が受ける「技能検定」とは異なります。
評価の目的は、実習生が習得した技能を客観的に測定し、次のステップ(上位号または特定技能)に進むための判断材料とすることです。
試験の内容と評価基準
技能評価試験は、実技試験と学科試験の2部構成です。
実技試験では、定められた時間内に与えられた課題を正確に施工できるかが評価されます。
実技試験の評価項目例
- タイルの割付け・通りの精度
- 下地処理の正確さ(段差・平滑度の確認)
- 接着剤・モルタルの使用量・均一性
- 仕上げ面の美観・強度・目地の均一性
- 工具使用・安全対策の適正
学科試験の評価項目例
- 材料知識(タイル種類・吸水率・寸法誤差)
- 作業工程の順序と施工管理
- 安全衛生法規・防火対策
- 品質検査・保守・補修方法
学科は筆記(択一式)で、級ごとに出題数・合格基準が異なります。
合否は、実技・学科それぞれ60点以上が一般的な合格ラインです。
合格に向けた勉強方法と対策
タイル張り作業の評価試験は「時間配分」「精度」「段取り力」が合否を左右します。
特に実技では、限られた時間の中でどれだけ正確に貼付けと仕上げを行えるかが評価されます。
効果的な学習・練習方法として以下のポイントが挙げられます。
- 実技練習の反復:施工の順序・道具の扱い・仕上げ精度を体で覚える。
- 模擬試験の実施:実際の制限時間を想定し、手順と仕上げを確認する。
- 過去問題の分析:出題傾向を把握し、重点項目を重点練習する。
- 評価基準の理解:中央職業能力開発協会が公開している基準に沿って採点を想定する。
実習生にとって、試験合格は単なる通過点ではなく、技能移転を実証する重要な成果でもあります。
企業が技能実習生を受け入れる際の要件と注意点
団体監理型の受け入れ体制と監理団体の役割(統合後)
タイル張り分野を含む建設業の技能実習は、団体監理型によって運用されています。監理団体が受け入れ企業(実習実施者)を支援し、制度が適正に実施されるよう監査・指導を行う仕組みです。
実習受け入れの基本的な流れは以下のとおりです。
- 企業が監理団体へ受け入れ相談・依頼
- 実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ申請
- 審査後、入国・講習・配属の手続きへ進行
- 監理団体が定期巡回し、労働環境・安全・生活支援を確認
監理団体は、制度遵守・教育体制・トラブル防止の要として機能します。企業単独では対応が難しい書類管理や行政手続きも、監理団体の支援によって適正に進められます。
一方で企業は、技能指導員の配置、安全衛生管理、教育計画の実施など、現場運営の主体を担います。双方が情報共有を密に行うことで、実習生の学習効果と安全性を高めることができます。
受け入れ企業に求められる基準と責務
受け入れ企業には、技能実習法に基づき以下の義務が課せられています。
- 安全・衛生環境の確保(労働安全衛生法準拠)
- 技能指導員の配置(実務経験5年以上の技能者)
- 労働条件の適正提示(賃金・休暇・就業時間)
- 教育計画・技能評価の実施
技能実習は労働力確保を目的とせず、教育的視点からの受け入れが求められます。したがって、長時間労働や不当な命令は厳禁です。また、日本人と同等以上の待遇を保証することが制度上の原則です。
受け入れ手続きと必要書類
タイル張り分野の受け入れでは、監理団体の指導を受けながら段階的に手続きを進めます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 技能実習計画書(様式第1号)
- 実習実施者届出書
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 技能指導員一覧表・教育体制図
- 宿舎・生活支援体制の確認書類
受け入れスケジュール例
- 監理団体との契約・相談(1か月)
- 書類作成・申請(2〜3か月)
- 現地面接・在留資格認定(1〜2か月)
- 入国後講習・企業配属(1か月)
オープンケア協同組合では、受け入れ相談・書類支援・講習管理を一括でサポートしています。法令準拠の教育体制を整えたい企業様は、ぜひご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習から特定技能への移行とキャリア形成
技能実習修了後の進路と制度上の位置づけ
タイル張り分野で技能実習を終えた実習生は、一定の条件を満たすことで特定技能制度へ移行することが可能です。
技能実習制度は「技能移転を目的とした教育制度」、一方で特定技能制度は「熟練した技能を持つ外国人の就労を認める制度」として運用されています。
両制度は別の在留資格ですが、技能実習で得た経験と評価試験の合格が移行の前提条件となります。
この移行により、実習生は再び日本で働く機会を得るだけでなく、より高度な技能の発揮・国際的キャリア形成を目指すことができます。
特定技能1号への移行条件と試験要件
特定技能1号へ移行するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること(3年間の実習終了報告を含む)
- 技能評価試験「随時3級」に合格していること
これらの条件を満たすことで、出入国在留管理庁への申請が可能になります。
タイル張り作業は特定技能の対象職種に含まれており、建設分野(16分野の1つ)として、一定の監督下で在留資格「特定技能1号」への移行が認められています。
ただし、制度上は分野ごとの要件が細かく定められており、移行の可否や必要書類は時期・地域によって異なる場合があります。申請前に監理団体または行政書士へ確認することが推奨されます。
技能移転とキャリア形成の意義
技能実習と特定技能を通じて得られる経験は、実習生自身の成長だけでなく、母国への技能移転という社会的意義も持っています。
実際、帰国後に日本で学んだ施工技術や安全基準を現地の建設業で活用したり、後進指導に携わるケースも多く見られます。
また、特定技能で継続して日本で働く場合、より高度な業務(施工管理・指導・品質検査など)に携わることが可能となり、職業的キャリアアップにもつながります。
タイル張りという専門技能を通じた国際的な人材循環は、技能実習制度の本来目的である「相互発展と国際協力」を体現するものです。
技能実習から特定技能への移行は、単なる制度上の変更ではなく、技能を軸にした長期的なキャリア形成の選択肢です。
まとめ
タイル張り分野の技能実習は、建設技術の中でも特に精度と安全性が求められる専門職種です。
制度は「技能移転による国際協力」を目的としており、実習生は日本の高度な施工技術を学び、母国での産業発展に役立てることが期待されています。
本記事で解説したように、
- 技能評価試験(基礎級・随時3級・随時2級)による段階的評価制度
- 団体監理型による企業・監理団体の連携体制
- 特定技能制度への移行と国際的キャリア形成の可能性
これらが、タイル張り技能実習の柱となっています。
制度の正しい理解と適正な受け入れを行うことで、企業にとっても技能継承の良い機会となり、実習生にとっても将来の成長につながります。
オープンケア協同組合では、監理団体として法令準拠・教育体制の整備・生活支援までを一貫してサポートしています。
技能実習や特定技能の導入をご検討中の企業様へ
タイル張り分野での受け入れや実習計画のご相談は、専門スタッフが丁寧に対応いたします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/













