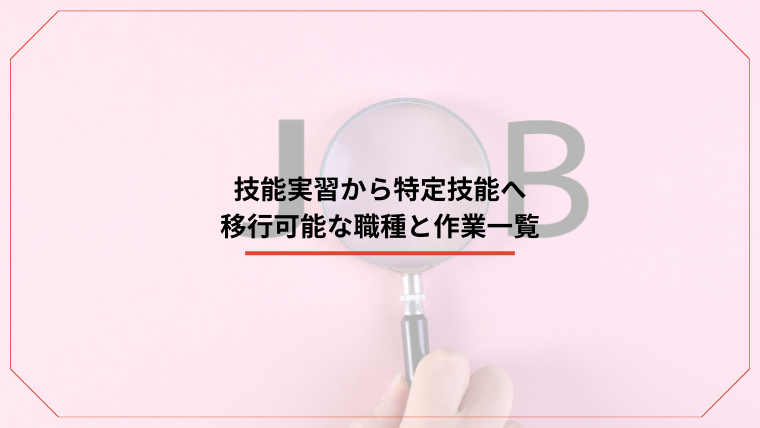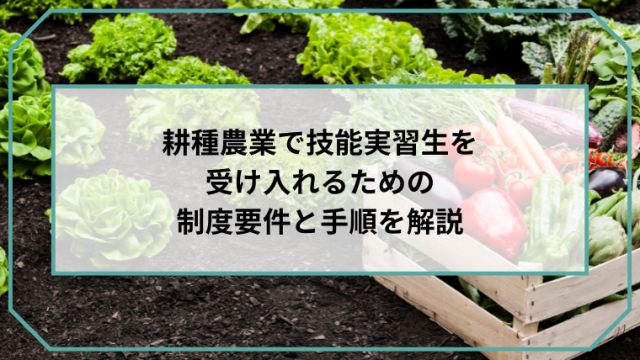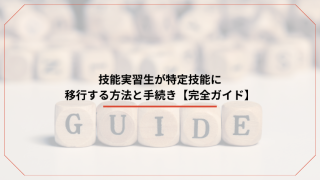技能実習から特定技能へ移行できる職種とは?
技能実習制度と特定技能制度は、それぞれ目的が異なります。技能実習は母国への技術移転を目的としているのに対し、特定技能制度は日本の人手不足を補うための即戦力の確保が目的です。そのため、すべての技能実習生が特定技能へ移行できるわけではなく、移行可能な職種が限定されています。
技能実習生が特定技能1号へ移行するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 特定技能の対象産業分野に該当する職種・作業であること
- 受け入れ企業が特定技能1号の基準を満たしていること
次に、特定技能の対象となる16の産業分野と、技能実習からの移行が可能な職種の基本条件について詳しく見ていきます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
特定技能の対象産業分野と移行の基本条件
特定技能1号は、日本の人手不足が深刻な16の産業分野で認められています。これらの分野は、技能実習制度と重なる部分が多いため、技能実習2号を修了した実習生が特定技能に移行しやすい職種も多数存在します。
以下は、特定技能の対象産業分野と、技能実習から移行する際の基本条件です。
| 産業分野 | 移行の基本条件 |
| 製造業(機械・金属・電子・プラスチック) | 技能実習での作業が特定技能の業務範囲に含まれていること |
| 建設業 | 技能実習時の職種と同一の業務であること |
| 食品製造業(ハム・ソーセージ・加工食品など) | 食品の加工・製造業務を技能実習で経験していること |
| 漁業・農業分野 | 養殖業務・農作業の経験があること |
| 介護・宿泊業・外食業 | 技能試験や日本語能力の要件を満たしていること |
技能実習から特定技能へ移行するには、在留資格の変更が必要となります。その際、業務内容の適合性や雇用契約の条件が特定技能の基準を満たしているかを確認することが求められます。
次に、特定技能1号で移行可能な職種の詳細について、産業分野ごとに詳しく解説します。
製造業(機械・金属・電子・プラスチック)での移行職種
製造業は、日本国内の労働力不足が深刻な分野の一つであり、特定技能1号の対象に含まれています。特に、機械加工、金属加工、電子部品製造、プラスチック成形などの分野では、技能実習2号を修了した外国人が特定技能に移行しやすい職種が多く存在します。
移行可能な職種一覧
製造業における特定技能1号の移行対象となる職種は、以下の通りです。
| 分野 | 移行可能な職種 | 主な業務内容 |
| 機械 | 機械加工 | 旋盤、フライス盤、マシニングセンターを使用した金属部品の加工 |
| 機械組立 | 機械や設備の組立・調整・検査作業 | |
| 金属 | 鋳造 | 溶解した金属を型に流し込んで部品を成形 |
| 鍛造 | 金属を加熱し、圧力をかけて成形 | |
| 溶接 | 鉄・アルミ・ステンレスなどの溶接作業 | |
| 電子 | 電子機器組立て | 半導体・電子部品の組立・はんだ付け・検査 |
| プラスチック | プラスチック成形 | 射出成形機を使用した樹脂製品の製造 |
移行の基本条件
技能実習2号から特定技能1号に移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 在留資格の変更を申請する際、技能実習2号の修了証明が求められます。
- 技能検定基礎級または随時3級の合格が必要。
- 特定技能の業務内容と一致すること
- 技能実習で従事していた業務が、特定技能1号の業務範囲に含まれている必要がある。
- 例:技能実習で「機械加工」を行っていた場合、特定技能1号でも同じ「機械加工」の業務に従事することが求められる。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 受入れ企業は、外国人支援計画の策定が義務付けられています。
- 労働条件が日本人と同等以上であることが必要。
受け入れ企業が注意すべきポイント
- 業務内容の適合性を事前に確認する
- 技能実習で経験した作業と、特定技能1号での業務内容が一致しているかを確認することが重要。
- 受け入れ計画を適切に策定する
- 特定技能の外国人材を受け入れる際には、生活支援や教育プログラムを含めた計画を作成する必要がある。
- 特定技能1号の労働条件を遵守する
- 技能実習制度と異なり、特定技能1号では転職が可能なため、労働環境や賃金水準が適正でないと離職のリスクが高まる点に留意する必要がある。
製造業では、特定技能1号の移行が比較的スムーズに進むケースが多いですが、業務内容の適合性や受け入れ企業の体制を十分に確認した上で移行を進めることが重要です。
建設業での移行職種
建設業は、特定技能1号の対象分野の中でも特に人材不足が深刻な分野の一つです。技能実習制度から特定技能1号へ移行できる職種が多く、技能実習2号を良好に修了すれば、試験を受けずに移行が可能となるケースもあります。
移行可能な職種一覧
建設分野で技能実習から特定技能へ移行できる主な職種は以下の通りです。
| 分野 | 移行可能な職種 | 主な業務内容 |
| 型枠施工 | 型枠大工 | 建物のコンクリート部分を形成する型枠の組立・解体 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋工 | 鉄筋の加工・組立・設置 |
| とび工 | 足場組立作業員 | 建設現場での足場や支保工の設置・撤去 |
| 左官 | 左官工 | 建築物の壁や床をモルタルや漆喰で仕上げる作業 |
| 内装仕上げ施工 | 内装工 | クロス貼り、床仕上げ、天井工事 |
| 土工 | 土木作業員 | 建設工事の掘削・埋戻し・整地作業 |
| 建設機械施工 | オペレーター | ショベルカーやブルドーザーなどの重機操作 |
移行の基本条件
建設業で特定技能1号へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定基礎級または随時3級の合格が必要。
- 在留資格変更時に技能実習修了証明書の提出が求められる。
- 特定技能の業務と一致すること
- 技能実習で経験した作業内容が、特定技能1号の業務範囲と一致している必要がある。
- 例:技能実習で「鉄筋施工」を行っていた場合、特定技能でも「鉄筋施工」として働く必要がある。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 建設分野では、国土交通省の登録機関(建設技能人材機構:JAC)への登録が義務付けられている。
- 外国人技能者受入計画の作成と提出が必要。
受け入れ企業が注意すべきポイント
- JACへの登録と受入計画の作成が必要
- 特定技能1号で建設業の外国人材を受け入れる企業は、事前にJAC(建設技能人材機構)への登録が義務付けられている。
- 受入れ計画の承認が下りなければ、特定技能1号の申請はできないため、事前の準備が不可欠。
- 業務内容が技能実習と一致しているか確認
- 技能実習で経験した職種と異なる業務に従事させることは不可。
- 例:型枠施工の実習を行っていた技能実習生を、特定技能1号の鉄筋施工職として雇用することは認められない。
- 適正な労働環境を整える
- 特定技能1号の労働条件は、日本人と同等以上である必要がある。
- 長時間労働や危険作業が伴うため、適切な安全管理や福利厚生の整備が求められる。
建設業では、技能実習から特定技能へ移行しやすい職種が多いものの、JACへの登録や受入計画の作成といった特有の手続きが必要です。企業側が適切な準備を行い、受け入れ体制を整えることで、スムーズな移行が可能となります。
食品製造業(ハム・ソーセージ・加工食品など)の移行職種
食品製造業は、日本国内の食料品加工・製造の分野で深刻な人手不足が続いており、特定技能1号の対象となる産業の一つです。特に、ハム・ソーセージ・ベーコンなどの加工食品製造や、パン・菓子製造、飲料製造などの職種では、技能実習2号を修了した外国人が特定技能へ移行しやすいことが特徴です。
移行可能な職種一覧
食品製造分野で技能実習から特定技能へ移行できる主な職種は以下の通りです。
| 分野 | 移行可能な職種 | 主な業務内容 |
| 食肉加工 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 原料処理、調味、成形、加熱・燻製、包装 |
| 水産加工 | 魚肉練り製品製造 | かまぼこ・ちくわ・はんぺんの加工・成形・包装 |
| 乳製品製造 | チーズ・ヨーグルト製造 | 乳の殺菌、発酵、熟成、包装 |
| パン・菓子製造 | パン・ケーキ・焼菓子製造 | 生地の仕込み、成形、焼成、仕上げ、包装 |
| 調味料製造 | しょうゆ・味噌・ソース製造 | 原料処理、発酵管理、充填・包装 |
| 飲料製造 | 清涼飲料・アルコール飲料製造 | 原料処理、発酵、濾過、充填・包装 |
移行の基本条件
食品製造業で特定技能1号へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定基礎級または随時3級の合格が必要。
- 在留資格変更時に技能実習修了証明書の提出が求められる。
- 特定技能の業務内容と一致すること
- 技能実習で経験した作業と、特定技能1号の業務内容が一致している必要がある。
- 例:技能実習で「ハム・ソーセージ製造」に従事していた場合、特定技能でも同じ作業に従事することが求められる。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 受入企業は、適正な雇用契約と支援計画を整備することが義務付けられている。
- 労働条件は日本人と同等以上である必要がある。
受け入れ企業が注意すべきポイント
- 業務内容の適合性を事前に確認する
- 技能実習で経験した業務と異なる作業を任せることは不可。
- 例:技能実習で「水産加工」を行っていた技能実習生を、「パン製造」の特定技能1号として雇用することはできない。
- 食品衛生管理体制を整備する
- 食品製造業では、HACCP(ハサップ)などの衛生管理基準が厳格に適用されるため、外国人労働者向けの衛生教育が必要。
- 企業側は、日本の食品衛生法に基づく適切な指導を行うことが求められる。
- 特定技能1号の労働条件を遵守する
- 技能実習制度と異なり、特定技能1号では転職が可能なため、賃金水準や労働環境を適正に整えないと離職のリスクが高まる。
食品製造業では、特定技能1号の移行が比較的スムーズに進む職種が多いですが、業務内容の適合性や食品衛生管理の徹底が求められます。企業側が適切な受け入れ体制を整えることで、安定した雇用の維持が可能となります。
漁業・農業分野の移行職種
漁業・農業分野は、日本の食料供給を支える重要な産業ですが、高齢化や担い手不足が深刻な課題となっており、特定技能1号の対象に指定されています。 技能実習2号を修了した外国人が特定技能へ移行することで、長期間の就労が可能となり、安定的な労働力確保につながるため、多くの企業が受け入れを進めています。
移行可能な職種一覧
| 分野 | 移行可能な職種 | 主な業務内容 |
| 漁業 | 沿岸漁業作業 | 漁船を使用した漁業(網漁・釣漁・貝類採取など) |
| 沖合漁業作業 | 大型漁船での漁獲作業、魚の選別・保管 | |
| 養殖業務 | 魚類・貝類・海藻の養殖、給餌・水質管理 | |
| 農業 | 露地栽培 | 野菜・果樹の植付け、管理、収穫作業 |
| 施設栽培 | ビニールハウス・温室での農作物の育成・管理 | |
| 畜産業 | 牛・豚・鶏の飼育、餌やり、繁殖管理 |
移行の基本条件
漁業・農業分野で特定技能1号へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定基礎級または随時3級の合格が必要。
- 在留資格変更時に技能実習修了証明書の提出が求められる。
- 特定技能の業務内容と一致すること
- 技能実習で経験した作業が、特定技能1号の業務範囲と一致している必要がある。
- 例:技能実習で「養殖業務」を行っていた場合、特定技能でも「養殖業務」として働く必要がある。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 受け入れ企業は、特定技能支援計画を策定し、外国人労働者が働きやすい環境を整える必要がある。
- 労働条件は日本人と同等以上でなければならない。
受け入れ企業が注意すべきポイント
- 業務内容の適合性を事前に確認する
- 技能実習で経験した職種と異なる業務を任せることは不可。
- 例:技能実習で「施設栽培」を行っていた技能実習生を、「畜産業」の特定技能1号として雇用することは認められない。
- 安全対策と労働環境の整備を徹底する
- 漁業では、天候や海の状況による作業の危険性が高いため、安全管理が重要。
- 農業では、長時間労働や重労働にならないよう配慮し、適切な休憩時間の確保が必要。
- 特定技能1号の労働条件を遵守する
- 特定技能1号では転職が可能なため、賃金や労働環境が適正でないと離職のリスクが高まる。
漁業・農業分野では、特定技能1号の移行が比較的スムーズに進む職種が多いですが、安全対策や労働環境の整備を徹底することが重要です。企業側が適切な受け入れ体制を整えることで、長期的な雇用の維持が可能となります。
介護・宿泊業・外食業での移行職種
介護・宿泊業・外食業は、日本国内の労働力不足が特に深刻な分野であり、技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号へ移行しやすい職種が多く含まれています。 これらの業種では、基本的な接客対応や業務スキルに加え、日本語能力が求められるため、移行時の条件や必要資格を事前に確認しておくことが重要です。
移行可能な職種一覧
| 分野 | 移行可能な職種 | 主な業務内容 |
| 介護 | 介護職員 | 高齢者・障がい者の食事介助、入浴介助、排泄介助、生活支援 |
| 宿泊業 | ホテルスタッフ | フロント業務、客室清掃、配膳、接客対応 |
| 料飲サービススタッフ | レストラン・宴会場での配膳、接客、オーダー受付 | |
| 外食業 | 調理スタッフ | 飲食店での調理、仕込み、食材管理 |
| ホールスタッフ | 注文受付、配膳、レジ業務、顧客対応 |
移行の基本条件
介護・宿泊業・外食業で特定技能1号へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定基礎級または随時3級の合格が必要。
- 在留資格変更時に技能実習修了証明書の提出が求められる。
- 特定技能の業務内容と一致すること
- 技能実習で経験した作業が、特定技能1号の業務範囲と一致している必要がある。
- 例:技能実習で「ホテルの客室清掃」を行っていた場合、特定技能でも「宿泊業」の業務として働くことが求められる。
- 日本語能力試験の合格が必要な場合がある
- 介護分野では、日本語能力試験(JLPT N4以上)または介護日本語評価試験の合格が必須。
- 宿泊業・外食業では、業務上の指示を理解するために、日本語でのコミュニケーション能力が求められる。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 受け入れ企業は、外国人支援計画を策定し、労働者が適切な環境で働ける体制を整える必要がある。
- 労働条件は日本人と同等以上でなければならない。
受け入れ企業が注意すべきポイント
- 業務内容の適合性を事前に確認する
- 技能実習で経験した職種と異なる業務を任せることは不可。
- 例:技能実習で「調理補助」を行っていた技能実習生を、「ホールスタッフ」として雇用することは認められない。
- 日本語能力向上のサポートを行う
- 介護分野では、日本語での意思疎通が特に重要なため、企業側が日本語学習の機会を提供することが望ましい。
- 特定技能1号の労働条件を遵守する
- 特定技能1号では転職が可能なため、適正な賃金や労働環境を整えないと、離職のリスクが高まる。
介護・宿泊業・外食業では、日本語能力が求められる場面が多いため、企業側も受け入れ準備を整えた上で移行を進めることが重要です。特に、介護分野では資格取得が必須となるため、移行条件をしっかり確認することが求められます。
移行可能な職種の確認方法と企業が注意すべき点
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号へ移行できるかどうかを判断する際、移行可能な職種の確認が重要なポイントとなります。特定技能1号の対象となる業務は限定されており、技能実習で従事していた職種と特定技能での業務が一致していなければ移行は認められません。
また、企業側は受け入れを進める際に、適切な職種の選定や移行要件の確認を行い、スムーズな手続きを進めることが求められます。
技能実習の職種と特定技能の職種が一致する条件
技能実習から特定技能への移行を認められるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定基礎級または随時3級の試験に合格していること。
- 技能実習修了証明書の提出が求められる。
- 技能実習で経験した業務が特定技能の職種と一致していること
- 技能実習で経験した職種が、特定技能1号の業務範囲内であることが必須。
- 例:技能実習で「自動車整備」を行っていた場合、特定技能でも「自動車整備士」としての業務に従事する必要がある。
- 異なる職種への移行は原則不可。 例えば、技能実習で「食品加工」を経験した外国人が「介護」の特定技能資格を取得することは認められない。
- 企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていること
- 企業が特定技能外国人を雇用する際、労働条件や職務内容が適正であることを示す必要がある。
- 受け入れ企業は、外国人支援計画を策定し、生活サポートや労働環境の整備を行う義務がある。
企業が職種の適合性を確認する方法
企業が、技能実習から特定技能への移行が可能かどうかを確認する方法は以下の通りです。
1. 法務省・出入国在留管理庁のガイドラインを確認する
- 特定技能1号の対象となる職種一覧を事前に確認し、技能実習での業務と照らし合わせる。
- 公式サイトで最新の移行可能職種をチェックすることが重要。
2. 技能実習の職種コードと特定技能の職種コードを照合する
- 技能実習制度と特定技能制度では、それぞれ職種ごとに職種コードが割り当てられている。
- 企業は、技能実習での職種コードと特定技能での職種コードが一致しているかを確認し、移行の適合性を判断する。
3. 行政書士や監理団体に相談する
- 法的な手続きや、移行可能な職種の確認について専門家のアドバイスを受ける。
- 特定技能の申請実績がある監理団体や行政書士に相談すると、移行の可否を正確に判断できる。
企業が注意すべきポイント
企業が特定技能外国人を受け入れる際には、適切な準備と管理体制を整えることが求められます。 以下のポイントに注意しながら、移行を進めることが重要です。
- 技能実習時の業務内容を正確に把握する
- 技能実習での職務内容が特定技能の業務と合致しているか事前に確認する。
- 異なる業務への配置転換は認められないため、移行後の業務内容を明確にすることが必要。
- 必要な書類を正しく準備する
- 技能実習修了証明書、技能検定合格証、雇用契約書など、移行手続きに必要な書類を正確に揃える。
- 適切な労働環境を提供する
- 特定技能1号の労働条件は、日本人と同等以上であることが義務付けられている。
- 長時間労働や低賃金の問題が発生しないように、適正な労務管理を行う。
企業が事前に職種の適合性を確認し、適切な受け入れ体制を整えることで、スムーズな移行と長期的な雇用維持が可能になります。
雇用可能な人数と企業の受け入れ計画
特定技能1号の外国人を雇用する際、企業は雇用可能な人数の上限や受け入れ基準を確認し、適切な受け入れ計画を策定することが求められます。 各業種には、受け入れ可能な人数の制限が設けられている場合があり、事前に業種ごとの規定を理解することが重要です。
また、特定技能1号の受け入れ企業は、労働条件や生活支援を含む計画を作成し、外国人労働者が安心して働ける環境を整える必要があります。
業種ごとの雇用枠と受け入れ企業の義務
特定技能1号の外国人労働者を受け入れる際、業種ごとに雇用可能な人数枠(上限)や義務が異なります。 企業は、自社が受け入れ可能な人数を把握し、適切な管理を行うことが求められます。
1. 業種ごとの雇用可能人数の基準
以下は、特定技能1号における主な業種ごとの雇用枠の目安です。
| 業種 | 雇用可能な人数の基準 | 特記事項 |
| 介護 | 制限なし(施設の受け入れ能力に応じる) | 日本語能力試験(JLPT N4以上)が必要 |
| 建設 | 企業の事業規模に応じた制限あり | 国土交通省の認定が必要 |
| 製造業 | 業種ごとに定められた上限あり | 詳細は業界団体のガイドラインを確認 |
| 食品製造業 | 企業の事業規模に応じた制限あり | HACCP(ハサップ)対応が求められる |
| 外食業 | 人手不足の状況に応じて受け入れ可能 | 日本人と同等以上の待遇が必須 |
| 宿泊業 | 施設の規模に応じて制限あり | 接客業務では一定の日本語能力が求められる |
| 農業・漁業 | 事業規模に応じた受け入れが可能 | 季節雇用も認められる |
特定技能1号の雇用枠は、業界ごとの人手不足の状況や政府の政策により、変更される可能性があるため、最新情報を定期的に確認することが重要です。
2. 企業の受け入れ義務と責任
企業が特定技能1号の外国人を雇用する場合、以下の義務を遵守する必要があります。
- 日本人と同等以上の労働条件を確保する
- 給与、労働時間、福利厚生が日本人と同等以上であることが義務付けられています。
- 最低賃金を下回る給与設定は禁止されており、社会保険・雇用保険への加入も必要です。
- 外国人支援計画を作成し、適切な生活支援を行う
- 住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習支援などのサポートを提供することが求められます。
- 企業が直接支援を行う場合と、登録支援機関へ委託する場合の2つの方法があります。
- 雇用管理の適正化と報告義務を遵守する
- 定期的に特定技能外国人の就労状況を報告する義務があります。
- 受け入れた外国人が適正に働いているかどうか、出入国在留管理庁や業界団体の審査を受けることがあります。
- 過去に不正行為を行っていないことを証明する
- 技能実習制度や労働基準法に違反した企業は、特定技能の受け入れが認められない可能性が高いです。
- 転職の自由を認めること
- 特定技能1号では、同じ業種内での転職が可能です。
- 企業は雇用契約の内容を適切に設定し、長期的に働いてもらうための環境を整えることが求められます。
まとめ:技能実習から特定技能への移行を成功させるために
技能実習から特定技能1号へ移行することで、企業は即戦力となる外国人材を継続的に雇用できるようになります。しかし、スムーズに移行を進めるためには、職種の適合性、企業の受け入れ基準、必要な手続きを事前に確認し、適切な準備を行うことが重要です。
特定技能制度では、労働者の転職が可能であるため、企業側が適正な雇用条件やサポート体制を整えなければ、人材が流出するリスクがあります。そのため、受け入れ企業は法令を遵守し、労働環境や支援計画を適切に整備することが求められます。特定技能1号への移行をスムーズに進めるためには、計画的な準備と適切な対応が不可欠です。 企業が事前の準備を徹底し、適切な受け入れ環境を整えることで、外国人労働者の定着率を高め、安定した雇用を実現できます。
特定技能へ移行する際の詳しい解説については技能実習生が特定技能に移行する方法と手続き【完全ガイド】をご参照ください。