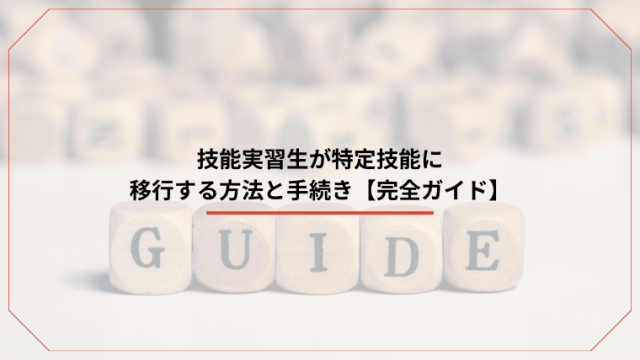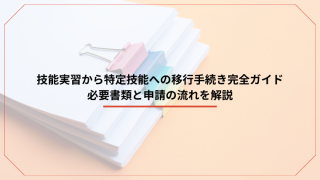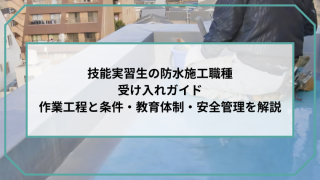技能実習生を日本で受け入れるにあたっては、在留資格の取得をはじめとする複数の重要な手続きを正確に理解する必要があります。特に、技能実習1号・2号・3号の違いや在留期間の管理、申請に必要な書類や審査基準など、対応すべき項目は多岐にわたります。本記事では、技能実習制度の基本から、適切な在留資格の選定、受け入れに必要な準備、さらには制度変更や特定技能への移行まで、実務担当者が押さえておくべきポイントを丁寧に解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習制度の基本概要と目的
技能実習制度は、外国人が日本で技能・技術を実践的に学ぶ制度です。人材育成を目的とした制度であり、労働力確保が主目的ではない点に注意が必要です。制度を正しく理解することが、適切な受け入れと運用につながります。
技能実習制度の成り立ちと背景
技能実習制度は1993年に創設され、当初は「外国人研修制度」として始まりました。その後、制度の不備が指摘され、1997年に労働法令の適用対象となる「技能実習制度」へと再編されました。
この制度の背景には以下のような要因があります。
- 日本の少子高齢化に伴う中小企業の人手不足
- 発展途上国への技術移転による国際貢献
- 外国人労働者の雇用管理の適正化
技能実習生は労働者として保護される立場となり、労働基準法、最低賃金法などの法令も適用されます。現在では監理団体の支援のもと、制度の透明性と適正な運用が求められています。
技能実習制度の主な目的と対象分野
技能実習制度の中心的な目的は、開発途上国の人材に対して日本の技術・技能・知識を移転することです。単なる労働力確保ではなく、国際協力の一環として制度が運用されています。
対象となる分野は以下の通り、幅広い産業にわたって制度化されています(※2025年3月時点)
1. 農業関係
耕種農業(施設園芸、畑作、稲作)
畜産農業(養豚、養鶏、酪農)
2. 漁業関係
沿岸漁業(定置網、小型底びき網など)
漁船作業(機関整備、漁具修理など)
水産加工(冷凍処理、塩干品製造、選別包装など)
3. 建設関係
型枠施工、とび、配管、左官、鉄筋施工、内装仕上げ、屋根ふき、防水、電気配線、建具製作、建設機械施工 など
4. 機械・金属関係
普通旋盤、マシニングセンタ、フライス盤、機械検査、金属プレス加工、鋳造、鍛造、溶接、ダイカスト、仕上げ、工業包装 など
5. 自動車整備関係
自動車整備(ガソリン、ディーゼル車の整備など)
6. 電気・電子関係
電子機器組立、プリント配線板製造、機械組立、電気機器組立、半導体製造、塗装(電着、粉体など)
7. 食品製造関係
ハム・ソーセージ・ベーコン製造、冷凍調理食品製造、味噌・醤油製造、パン・菓子製造、缶詰巻締、つくだ煮製造 など
8. 繊維・衣服関係
婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、染色(糸・織布)、裁断、縫製、仕上げ、編物、刺繍、織布整理 など
9. 印刷関係
オフセット印刷、製本、製版、スクリーン印刷
10.木材加工関係
製材、木製建具製作、家具製作、木工機械作業など
11. プラスチック加工関係
射出成形、押出成形、ブロー成形、プラスチック製品仕上げなど
12. ゴム製品製造関係
ゴム加硫、ゴム混練り、ゴム製品仕上げなど
13. 紙加工関係
紙器・段ボール製造、製袋加工など
14. 陶磁器製造関係
陶磁器素地成形、施釉、絵付けなど
15. その他製造関係
貴金属装身具製作、仏壇製作、履物製造、義肢・装具製作など
16. 介護
高齢者介護、身体介助、生活支援、レクリエーション支援など
17. 宿泊
フロント業務、客室清掃、接客補助、館内整備、ベッドメイキング、浴場管理など
18. リネンサプライ・クリーニング関係
リネンサプライ仕上げ作業
一般家庭用クリーニング作業
これらの分野では、技能実習1号から2号、さらに3号への移行が制度上可能な職種もあります。ただし、すべての職種が3号まで移行できるわけではなく、2号止まりとなる職種も存在しますので注意が必要です。
対象職種や作業の見直しは随時行われており、今後も柔軟な制度運用や新たな分野の追加が進められる予定です。制度の活用にあたっては、最新の制度情報を常に確認することが重要です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/
技能実習生の在留資格の種類と特徴
技能実習生の在留資格には複数の種類があり、それぞれの活動内容や在留期間、申請条件が異なります。受け入れ企業や監理団体は、制度を正確に理解し、適切な段階での受け入れを行う必要があります。
技能実習1号・2号・3号の在留期間と活動内容
技能実習制度は段階的に構成されており、1号・2号・3号の3段階があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 技能実習1号:入国から1年間。座学講習と基本的な実務訓練が中心。
- 技能実習2号:最長2年間。より高度な業務への従事が可能。
- 技能実習3号:最長2年間の延長が認められる。企業での信頼実績が条件。
それぞれの段階において、技能検定の合格や実務能力の評価が必要になります。3号への移行には、2号の修了状況に加え、監理団体の実績や企業評価も審査対象となります。
在留資格の種類ごとの申請要件と審査ポイント
各在留資格を取得するには、所定の申請手続きと条件を満たす必要があります。審査では、以下のような点が重視されます。
- 技能実習計画の内容と整合性
- 実習先企業の労働環境・就労管理体制
- 監理団体や企業の過去の実績
- 技能実習生の職種・分野との適合性
特に、実習内容と受け入れ職種との一致は重要な審査ポイントです。また、外国人技能実習機構(OTIT)による事前確認や、地方出入国在留管理局の審査も行われます。
制度上、在留資格ごとに更新・移行・変更の可能性があるため、常に最新の制度情報に基づいて準備を進める必要があります。
技能実習生受け入れの流れと必要な手続き
技能実習生を正式に受け入れるには、入国前から帰国に至るまで、複数の法的手続きと準備事項が発生します。企業や監理団体は、制度に沿った流れを把握し、適切に対応する必要があります。
在留資格認定証明書申請の流れと必要書類
外国人が技能実習生として日本に入国するためには、**在留資格認定証明書(COE)**の取得が不可欠です。この証明書は出入国在留管理庁に申請し、交付されるまでには通常1〜3か月を要します。
申請の流れは以下の通りです
- 技能実習計画の作成と外国人技能実習機構への認定申請
- 在留資格認定証明書の申請(出入国在留管理庁へ提出)
- 証明書の交付後、母国にて査証(ビザ)の申請
- 日本への入国手続き
申請に必要となる主な書類は以下の通りです。
技能実習生本人に関する書類
- 旅券(パスポート)のコピー
- 履歴書(本人が記入)
- 顔写真(4cm×3cm、6か月以内に撮影)
- 最終学歴証明書(必要な場合)
- 関連する技能資格の証明書(該当する場合)
受け入れ機関に関する書類
- 実習実施者の登記簿謄本
- 決算報告書(直近の会計年度)
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 健康保険・厚生年金適用証明(適用事業所証明書など)
- 税務署への届出書(給与支払事務所等の届出)
監理団体および技能実習計画に関する書類
- 認定済の技能実習計画書
- 監理団体との契約書
- 監理団体の許可証・団体概要資料
- 技能実習責任者・指導員・生活指導員の配置図と職務内容
- 支援体制に関する説明資料(日本語教育、生活支援など)
これらの書類は、在留資格の種類や実習内容、実施場所、受け入れ形態によって一部異なる場合があります。審査を円滑に進めるためには、正確かつ漏れのない書類準備が不可欠です。また、監理団体が一部書類の作成支援や確認を行うケースも多いため、事前の連携が重要です。
入国前後に行うべき企業側の対応と準備
在留資格の取得後も、受け入れ企業や監理団体には多くの対応が求められます。特に、入国直後の支援体制の整備は義務化されており、準備不足は制度違反に該当します。
入国前の対応
- 宿舎の手配、安全衛生の準備
- 通訳体制の構築
- 技能実習計画の社内共有
- 入国日程の管理と交通手段の確保
入国後の対応
- 生活オリエンテーションの実施(入国後講習)
- 在留カードの取得と住民登録手続き
- 雇用開始前の社内手続き(雇用保険、労災など)
また、技能実習生の支援には、生活面の指導や日本語教育も含まれます。受け入れ企業が直接対応するほか、監理団体による定期的な巡回指導も必要です。
技能実習計画と監理団体・企業単独型の違い
技能実習を実施するには、事前に技能実習計画の作成と認定取得が必要です。また、実習の実施形態として「団体監理型」と「企業単独型」の2種類が存在し、運用面においてそれぞれ特徴があります。
技能実習計画書の作成と認定のポイント
技能実習計画は、技能実習の目的や内容を明確に記載し、外国人技能実習機構(OTIT)による認定審査を受ける必要があります。
計画書に含めるべき内容
- 実習の目的と対象職種
- 実習期間と日別スケジュール
- 教育訓練の内容と実施方法
- 実習実施者の体制(指導員、職場環境など)
- 労働条件と賃金、福利厚生の整備状況
認定の審査基準では、適正な労働環境・安全衛生管理・教育体制の有無が重視されます。さらに、過去の不適正事例や、監理団体の実績なども評価対象となります。
認定取得後、計画通りに実習が行われているかは定期的にチェックされ、違反がある場合は是正命令や認定取消が行われる場合もあります。
団体監理型・企業単独型の制度比較と適用条件
技能実習制度には2つの受け入れ形態があり、それぞれ次のような特徴があります。
団体監理型
- 監理団体(主に商工会や協同組合など)が技能実習生の受け入れを支援、企業が技能実習を適切に実施できるよう監査や指導を行う
- 一般的に中小企業の利用が多い
- 教育・生活支援・監査などを監理団体が実施
- 監理費が発生する
企業単独型
- 大企業などが、海外の現地法人や提携先から直接受け入れる形式
- 実習生の教育・管理を企業が単独で行う
- 実施責任と管理体制の整備が必須
適用条件は以下のとおりです
- 団体監理型:原則、監理団体の許可・登録が必要
- 企業単独型:一定の規模や海外拠点との提携が求められる
どちらの形式を採用するかは、企業の体制、経験、人材ニーズに応じて判断する必要があります。
技能実習の更新・変更・移行手続き
技能実習制度は段階的に構成されており、一定条件を満たせば更新や変更、さらには特定技能への移行も可能です。これらの手続きには、事前準備と制度への正確な理解が不可欠です。
技能実習期間の更新・延長の条件と流れ
技能実習2号を修了した技能実習生が、さらに2年間の実習を希望する場合、技能実習3号への移行が可能です。ただし、以下のような要件をすべて満たす必要があります。
技能実習3号移行の主な要件
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能検定(随時3級または基礎2級)に合格していること
- 受け入れ企業(実習実施者)が「優良認定」を受けていること
- 監理団体が「優良監理団体」であること
- 引き続き同一職種・作業での実習であること
- 3号技能実習計画の認定を受けていること
- 実習生本人の継続意思と健康状態の確認
- 出入国在留管理庁による在留資格の変更許可
申請の流れ
- 技能実習3号の技能実習計画を新たに作成
- 外国人技能実習機構へ認定申請
- 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁へ提出
この手続きを経て、在留カードの更新が認められると、実習期間を延長することができます。更新に際しては、技能実習制度の目的に即した実習であることが引き続き求められます。
技能実習から特定技能への移行要件と評価試験
技能実習制度を修了した後に、より高度な業務への就労を希望する場合は、「特定技能」への移行が可能です。この制度は、深刻な人手不足分野における即戦力の確保を目的としたもので、技能実習修了者は一定の条件下で試験免除が認められます。
主な移行要件は以下のとおりです
- 技能実習2号または3号を修了していること
- 特定技能の対象分野に一致していること
- 日本語能力試験(N4以上)または相当の試験に合格していること(分野による)
特定技能に移行するには、「技能評価試験」および「日本語試験」の合格が必要ですが、技能実習を一定期間修了した者は、試験の一部免除が認められる場合があります。分野ごとに定められた評価方法を確認し、正確な手続きを経て移行申請を行うことが重要です。
まとめ:技能実習生の在留資格取得と受け入れに必要なポイント
技能実習生の受け入れには、在留資格の正確な取得手続きと、制度全体の理解が不可欠です。技能実習1号から3号までの段階や在留期間の違い、必要書類の準備はもちろん、団体管理型と企業単独型の違いや技能実習計画の認定要件など、多くの実務的ポイントがあります。さらに、実習終了後には特定技能への移行も視野に入れる必要があります。関係法令や最新情報を確認しながら、適切な体制での受け入れを進めていくことが重要です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績
- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制
- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)
「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。
\お客様相談センター(06-7669-9341)/