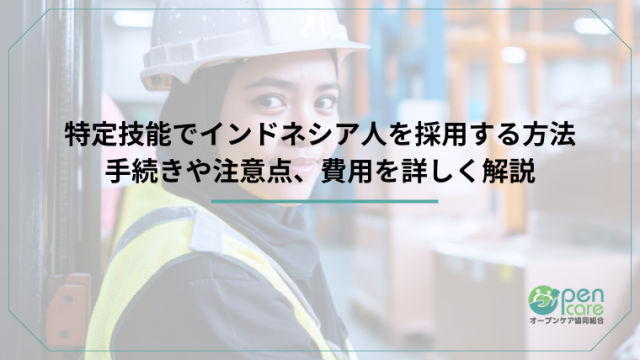初めての特定技能採用は、要件確認や支援体制づくり、在留資格申請までやることが多く迷いやすいものです。抜け漏れなく進めるために、次を簡潔に整理します。
- 制度と受け入れ要件の要点
- 募集から在留資格申請までの実務フロー
- 定着を見据えた支援体制の作り方
読むだけで準備の全体像と最初の一歩が明確になります。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を背景に、特定の業種で外国人材の就労を可能にした在留資格制度です。しかし、採用準備には制度理解、企業側の要件確認、支援体制の整備、在留資格申請など多くのステップがあり、初めて取り組む企業にとっては複雑です。
本記事では、制度の要点・採用までの流れ・定着につながる支援体制づくりをわかりやすく解説します。次章では、まず全体像を把握し、採用計画の道筋を明確にしていきます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能採用準備の全体像

準備の流れと期間目安
特定技能採用は、以下の5ステップで進みます。
- 制度理解
- 受け入れ条件確認
- 募集・採用活動
- 支援体制構築
- 在留資格申請・受け入れ準備
初めての場合、準備開始から受け入れまで数週間〜数か月程度かかります。経験やネットワークがあれば短縮できますが、法令や手続きの確認には十分な時間を確保しましょう。
関係機関と役割
採用準備には、出入国在留管理庁・地方入管、登録支援機関、現地送出機関、行政書士など複数の関係者が関わります。それぞれの役割を理解することで、手続きの遅延や不備を防げます。
全体像を把握するメリット
全体像を把握することで、各工程の優先順位や必要なリソースが明確になります。結果として、採用計画の精度が上がり、関係者との調整もスムーズになります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度の理解
特定技能1号の対象分野と概要
特定技能1号は、介護・外食・農業・建設など16分野で就労可能な在留資格です。各分野で定められた技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)に合格した外国人が対象です。
2025年9月時点で、特定技能1号の対象は16分野とされています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
在留期間・更新・家族帯同条件
特定技能1号は最長5年まで更新可能で、原則家族帯同は不可です。一方、特定技能2号に移行すれば更新回数制限がなく、家族帯同が認められる場合があります。
特定技能2号との違い
特定技能2号は現在、建設・造船舶用工業など限られた分野のみ対象で、より高度な技能を有する人材が対象です。長期雇用を見据える企業は、2号への移行も視野に入れるとよいでしょう。
技能実習からの移行条件
技能実習2号を良好に修了し、その業務が特定技能1号の同一分野または関連業務である場合には、技能試験および日本語試験が免除される特例措置が適用されます。一方で、関連性がない業務への移行では、日本語試験のみが免除となり、技能試験は必要になる場合があります。(参照:出入国在留管理庁)
この制度を活用すると、試験準備や手続きの工数・コストを削減できる可能性があります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能外国人を受け入れ企業の条件確認
法令遵守と労働条件
企業は労働基準法、最低賃金法、社会保険加入など日本の労働法規を順守し、特定技能外国人にも日本人と同等の労働条件を提示しなければなりません。
同等報酬義務と待遇確保
同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務です。これには基本給だけでなく、手当や賞与、福利厚生も含まれます。
住居確保と生活環境整備
住居の確保は、「1号特定技能外国人支援計画」における義務的支援項目の一つで、在留資格申請にも必要です。社宅や民間住宅の斡旋、生活用品の提供などが求められます。
安全衛生体制と職場環境
職場の安全衛生管理やハラスメント防止策も重要です。これらが整っていないと、労働環境の不備として入管審査で不利になる可能性があります。
ここまで確認できれば、次は実際の募集・採用活動に進めます。
特定技能外国人の求人募集と採用フロー

国内採用と海外採用の選択肢
特定技能人材は、国内在住者と海外在住者のどちらからも採用できます。国内採用は既に在留資格を持つ人材が対象のため、就業までが早く、渡航手続きも不要です。一方、海外採用は現地送出機関との連携が必要ですが、母国での試験合格者を直接採用できるメリットがあります。
求人票作成の必須項目
求人票には、以下の内容を明確に記載します。
- 業務内容と就業場所
- 就業時間、休日、残業の有無
- 賃金(基本給、各種手当、賞与)
- 福利厚生(社宅、食事補助、交通費など)
- 契約期間と更新条件
曖昧な記載はミスマッチを生みやすく、早期離職の原因となります。
応募者の資格要件
応募者は、対象分野の技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)に合格している必要があります。技能実習2号修了者は、対象分野に限り試験免除の場合があります。
事前面談とマッチング精度向上
事前面談では、日本語での意思疎通、業務理解度、生活適応力などを確認します。オンライン面談を活用すれば、海外人材とも容易に面談が可能です。
支援体制の構築
登録支援機関の選び方
登録支援機関は、生活支援や日本語学習支援など、企業が担うべき支援業務を代行します。選定時は、支援実績、対応言語、緊急時対応能力、料金体系を比較し、自社の受け入れ体制や対象分野に適した機関を選びましょう。
自社支援の場合の義務
企業が直接支援を行う場合、法律で定められた10項目の義務的支援をすべて実施しなければなりません。これには、生活オリエンテーション、住居契約補助、役所手続き同行、日本語学習機会の提供などが含まれます。
日本語教育と生活支援
業務の円滑な遂行には、日本語能力の向上が不可欠です。また、公共交通機関の利用方法や買い物、医療機関受診など、日常生活の適応支援も重要です。地域の日本語教室やオンライン学習の活用も有効です。
緊急対応と地域連携
病気や事故、災害などの緊急事態に対応できる体制を整えます。地域の多文化共生センターや外国人相談窓口、NPOとの連携により、より安心して働ける環境を構築できます。
在留資格申請と受け入れ準備
申請手続きの流れ
在留資格「特定技能1号」の申請は地方出入国在留管理局にて行われます。在留資格認定証明書の交付には1〜3か月、資格変更許可には2週間〜1か月、在留期間更新には2週間〜1か月程度が平均的な処理期間です。採用スケジュールには十分な余裕を持った計画が必要です。
必要書類と提出先
必要書類には、雇用契約書、支援計画書、技能試験・日本語試験の合格証明書に加えて、税務や社会保険関連の資料、法人関係書類など、多岐にわたる場合があります。詳細は出入国在留管理庁の「提出書類一覧」で確認を。書類不備による審査遅延を避けるために、行政書士など専門家のチェックを受けることをおすすめします。
渡航・入国準備
海外人材の場合、ビザ発給後に航空券や空港送迎の手配を行います。入国直後の住居設営や生活案内を含めた事前準備が重要であり、現地担当者との連携がカギとなります。
入国後の生活立ち上げ
住居案内、住民票登録、銀行口座や携帯電話契約といった生活基盤を速やかに整えることで、就業開始後の不安を軽減できます。
特定技能外国人の採用準備でよくある失敗と回避策

条件と業務内容の不一致
求人票と実際の業務内容が異なると、不満や早期離職の原因になります。条件設定時に業務内容を正確に反映させましょう。
支援体制の不備
生活支援やコミュニケーション不足は、定着率の低下につながります。登録支援機関や社内担当者の役割分担を明確にし、支援計画を実行できる体制を整えます。
申請不備による受け入れ遅延
書類不足や記載ミスは審査遅延の大きな原因です。申請前に第三者チェックを行いましょう。
社内理解不足
現場スタッフの理解不足は、外国人材との関係構築に悪影響を及ぼします。事前に文化・制度に関する社内研修を行い、受け入れ意識を高めましょう。
採用を成功させるためのチェックリスト
制度最新情報の確認
特定技能制度は、制度改正や対象分野拡大などの変更が行われます。採用準備前には出入国在留管理庁や厚生労働省の公式情報を確認し、最新条件に沿った準備を行いましょう。
専門家との連携
行政書士や社会保険労務士、登録支援機関など、専門家の知見を活用することで申請や契約条件のミスを防げます。費用はかかりますが、スムーズな受け入れにつながります。
中長期雇用計画
短期的な人員補充だけでなく、数年先を見据えた雇用計画を立てることで、特定技能2号への移行やキャリアパス設計が可能になります。
社内研修と受け入れ意識醸成
文化的背景や宗教、生活習慣の違いを社内で共有し、異文化理解を深める研修を行います。現場の協力体制は定着率向上の鍵です。
まとめ
特定技能の採用準備は、制度理解・企業条件の確認・採用活動・支援体制構築・在留資格申請という5つの柱を計画的に進めることが成功の鍵です。これにより、ミスマッチや受け入れ遅延を防ぎ、安定した雇用関係を築けます。
次のステップとして、自社の現状と照らし合わせ、どの段階から着手すべきかを明確にしましょう。必要に応じて専門家や登録支援機関と連携し、制度改正にも柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/