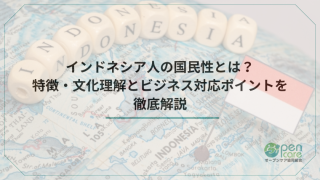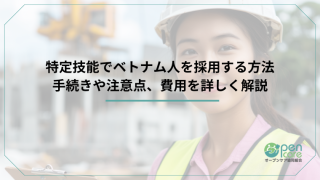- 「特定技能外国人って、どこの国から採用できるの?」
- 「国によって日本語力や適性に違いがあるのでは?」
- 「文化や宗教への配慮って、どの程度必要なんだろう」
そんな疑問や不安を感じていませんか?
本記事では、特定技能外国人の受け入れ可能な国と、最新の国別受け入れ実績を解説します。国籍ごとの特徴や採用時の注意点、採用までの流れも整理していますので、人材確保を検討する企業の参考になる内容です。
特定技能外国人の採用を検討している企業担当者の方に、ぜひ最後まで読んでいただきたい記事です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度と対象国の基本情報

特定技能制度とは?(在留資格と制度の目的)
特定技能制度は、2019年に創設された在留資格制度で、日本国内の深刻な人手不足を補う目的で導入されました。従来も高度専門職や技術・人文知識・国際業務などの在留資格はありましたが、特定技能では一定の技能と日本語能力を持つ外国人が中堅・中間層の即戦力として就労できるようになりました。対象は中小企業を含む幅広い業種で、人材確保の有効な選択肢となっています。
特定技能外国人を採用することは、慢性的な人手不足解消に直結する手段となります。自社で採用を検討している場合は、制度の全体像を正しく理解することが重要です。
特定技能1号の16分野と受け入れの仕組み
特定技能1号は、政府が定めた16の特定産業分野で就労を認める仕組みです。分野は以下の通りです。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
これらの分野では慢性的な人手不足が深刻化しており、特定技能外国人の活躍が期待されています。
特定技能の詳細については「特定技能の職種が拡大!新たに追加された4分野含む16分野の要件など詳細を解説!」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
二国間協定を結んでいる国とは?
特定技能の受け入れには、日本と送り出し国との間で「二国間協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)」が締結されていることが重要です。この協定により、送り出し機関の適正運営・監査、人材の保護、仲介業者の透明性、過剰な手数料の防止などが制度的に担保されます。出入国在留管理庁のウェブサイトにも、協定を結んだ国が随時更新されたリストとして公開されています。
協定を締結している国(アジア諸国)には、以下の国々が含まれます(2025年時点、出入国在留管理庁が公表している協定国の一覧より)
- ベトナム
- フィリピン
- インドネシア
- ミャンマー
- カンボジア
- ネパール等
これらの国々では、政府等が認定する送り出し機関を通じて人材を送り出すルートが整備されており、推薦表(または推薦者証明・推薦者欄など国により呼び方異なる)や出国前オリエンテーションなど、協定国ごとの独自ルールが設定されています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
2025年最新データ|特定技能外国人の国別受け入れ状況
ベトナム(最多の受け入れ国としての実績)
ベトナムは特定技能外国人の最多の受け入れ国です。特に製造業や介護分野での需要が高く、日本語教育の普及や技能実習からの移行のしやすさが強みです。
ベトナム人を採用する方法については「特定技能でベトナム人を採用する方法|手続きや注意点、費用を詳しく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
フィリピン(英語力や介護分野での強み)
フィリピンは英語力を活かし、介護や宿泊、観光接客業務での活躍が目立ちます。海外就労経験が豊富な人材が多く、異文化適応力も高い点が特徴です。
インドネシア(日本語教育の進展と建設分野での活躍)
インドネシアは日本語教育が進み、建設や自動車整備分野で活躍する人材が増えています。宗教や文化への配慮を尊重することで、定着率が向上しやすい傾向があります。
インドネシア人を採用する方法については「特定技能でインドネシア人を採用する方法|手続きや注意点、費用を詳しく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
ミャンマー(若年層人材が多く外食業でも増加)
ミャンマーからは20代~30代の若年層の人材が中心で、外食業や飲食料品製造業での採用が増加しています。国内の政治状況の影響で送り出しに変動があるため、最新情報の確認が重要です。
ネパール・カンボジアなど新興国の動向
ネパールやカンボジアからの人材は増加傾向にあり、介護や建設分野での就労が拡大しています。教育水準や日本語力に個人差があるため、採用前のスクリーニングが重要です。
最新の在留外国人数データ(出入国在留管理庁公表)
2025年時点の特定技能外国人数は、出入国在留管理庁が公開している統計で確認できます。国別の人数や分野別の推移を把握することで、今後の採用計画に活かせます。
国別の特徴と採用時の注意点
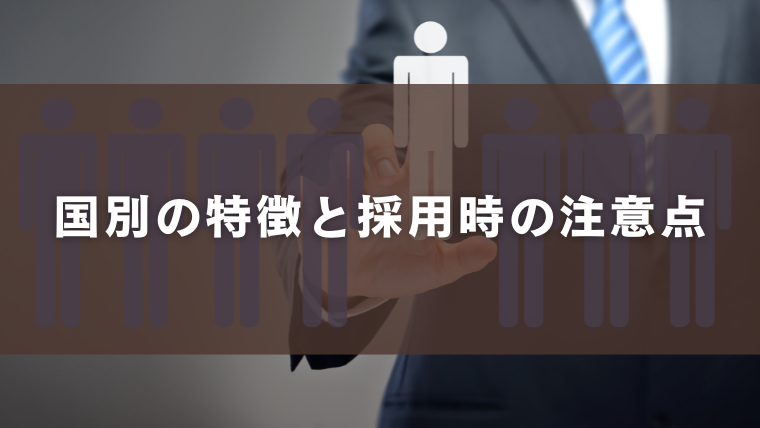
日本語能力・試験合格率の傾向
ベトナムやインドネシアは日本語教育が広がり、試験合格率も高い傾向にあります。一方、カンボジアやネパールは日本語力に差が出やすいため、採用時に資格試験の結果確認が必要です。
宗教・文化的背景と職場適応のポイント
インドネシアではイスラム教徒が多く、礼拝や食事制限に配慮する必要があります。文化的背景を尊重することで、定着率の向上につながります。
技能実習から特定技能への移行しやすさ
技能実習2号を修了した外国人は、分野試験を免除されて特定技能1号へ移行できます。そのため、すでに実習経験がある人材は採用後に即戦力として活躍しやすい利点があります。
二国間協定に基づく手続きの違い
協定国ごとに送り出し機関の運営方法や必要書類が異なります。企業は事前に確認し、トラブル防止に努める必要があります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能外国人の採用手続きと必要な準備
採用までのステップ(試験合格/技能実習2号修了 → 在留資格申請)
採用プロセスは大きく分けて以下の流れとなります。
- 特定技能試験と日本語試験に合格、または技能実習2号修了
- 日本企業との雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定後、入国・就労開始
特定技能の詳細については「特定技能外国人を受け入れる企業の要件とは?制度の基本と注意点をわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
ビザ申請に必要な書類と提出先
申請には在留資格認定証明書交付申請書、雇用契約書、支援計画書、登録支援機関関連の契約書などが必要です。提出先は地方出入国在留管理局となります。
企業側に義務付けられている支援内容(住居確保・生活支援)
特定技能外国人を雇用する際は、住居の確保や生活オリエンテーションの実施、相談体制の整備が義務化されています。これは任意ではなく、制度上の必須条件です。
登録支援機関を活用するメリット
登録支援機関は、採用企業に代わって生活支援や書類手続きをサポートします。制度理解に不安がある企業でも、安心して外国人採用を進められる利点があります。
まとめ|最新データを踏まえた国別採用戦略が重要
採用可能国の特徴を理解して比較検討する
国ごとに日本語力や職場適応の傾向が異なるため、自社の業種や職場環境に合う人材を選ぶことが大切です。
最新の受け入れ実績を把握して採用計画に活かす
出入国在留管理庁の統計をもとに、分野別・国別の最新データを確認し、長期的な採用計画に組み込むことが有効です。
安心・円滑な採用には専門機関への相談が有効
特定技能採用には法令遵守と実務的な知識が不可欠です。登録支援機関などの専門機関を活用することで、採用の成功率を高められます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/