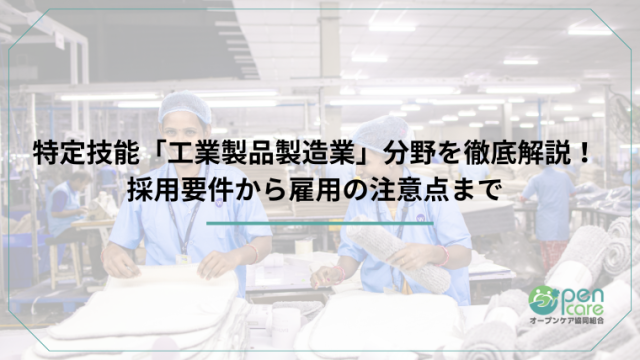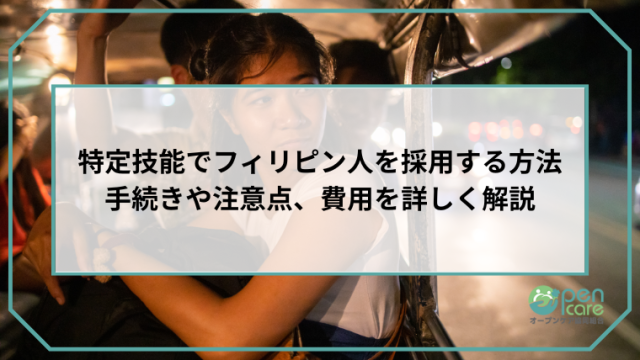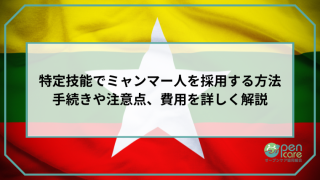- 「ミャンマー人はどんな性格なんだろう?」
- 「文化や宗教が仕事にどう影響するのか知りたい」
- 「採用後のコミュニケーションで気をつける点はある?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
本記事では、ミャンマー人の国民性や性格、宗教・家族観といった文化背景を詳しく解説します。さらに、日本企業が採用・育成・定着支援を行う際に押さえるべき実践ポイントや、円滑なコミュニケーションのコツも紹介しています。
特に、外国人雇用において「信頼関係づくり」を大切にしたい企業担当者の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
ミャンマーの基本情報と社会・宗教的背景について

東南アジアに位置する多民族国家ミャンマーの概要
ミャンマーは東南アジアの中央部に位置し、タイ・中国・インドなど5か国と国境を接する内陸国です。人口は約5,400万人で、首都はネピドー、最大都市はヤンゴンです。長い歴史を持つ多民族国家であり、国内には130以上の民族が存在します。その中でも「ビルマ族」が人口の約7割を占め、政治・経済・文化の中心的な役割を担っています。
このような多様な民族構成は、価値観や言語の違いを生み出す一方で、他者を尊重し共存する姿勢を育んできました。この点が、ミャンマー人の穏やかで協調的な国民性にもつながっています。
主要民族と宗教構成(ビルマ族・仏教徒中心の社会)
ミャンマーは人口の約9割が仏教徒であり、宗教が日常生活や人間関係に深く根づいています。多くの人が寺院での礼拝を欠かさず、感謝や奉仕を大切にする文化が根強く残っています。
仏教の教えは「思いやり」「忍耐」「謙虚さ」を重んじるもので、職場での人間関係にも強く影響します。日本企業においても、ミャンマー人社員が謙虚で感謝の言葉を多く使うのは、こうした文化的背景があるためです。
宗教的価値観を理解することは、信頼関係を築くうえで重要な第一歩となります。次は、その背景にある社会情勢と海外就労の傾向を解説します。
社会情勢と海外就労の背景
ミャンマーでは、2021年以降の政治的混乱や経済不安の影響で、海外への就労を希望する若者が増えています。特に日本・タイ・マレーシアなどへの出稼ぎが多く、日本は安定した雇用環境と高い給与水準から人気の渡航先となっています。
こうした背景を理解しておくことで、企業は「なぜミャンマー人が海外で働くのか」「何を重視して働いているのか」を把握できます。多くの人が家族への仕送りを目的としており、責任感や勤勉さにつながっています。
ミャンマー語と英語教育の普及レベル
ミャンマー語は国内の公用語であり、主要民族であるビルマ族が主に使用しています。一方で、教育現場やビジネスシーンでは英語も広く学ばれています。都市部の若者を中心に英語でのコミュニケーション能力を持つ人も多く、日本語学習への意欲も高いのが特徴です。
日本語能力試験(JLPT)N4〜N3レベルを目指す若者も増えており、特定技能制度によりさらに日本語教育が活発化しています。
このような背景を踏まえ、次ではミャンマー人の国民性と性格の特徴を詳しく見ていきます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
ミャンマー人の国民性と性格的特徴
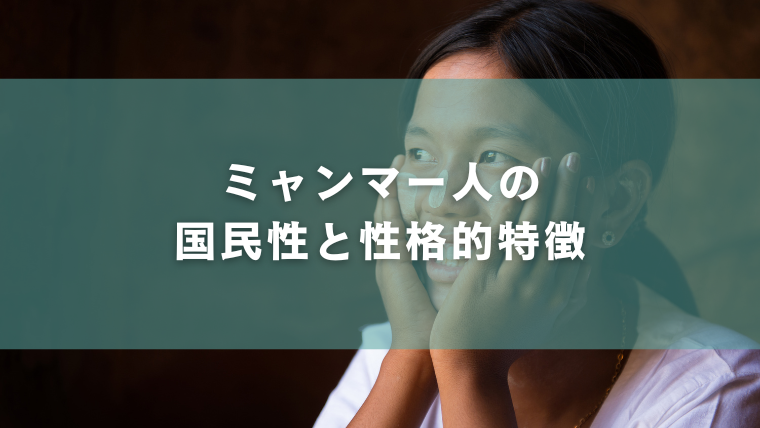
穏やかで協調性を重んじる性格
ミャンマー人は一般的に穏やかで争いを好まず、周囲との調和を大切にします。人前で強く主張することを避け、他者への配慮を優先する傾向があります。この協調性は職場でのチームワークにおいて大きな強みとなります。
一方で、曖昧な表現や遠回しな言い方を好むため、注意点を伝える際には明確な指示を心がけることが大切です。
家族を中心とした価値観と強い絆
ミャンマーでは家族のつながりが非常に強く、家族のために働くという意識が根づいています。
- 実家に仕送りをする
- 親や祖父母を敬う
- 家族行事を大切にする
このような価値観が、働く意欲や責任感の源になっています。企業としても、家族行事や宗教行事への配慮を示すことで信頼関係が深まり、定着率向上につながります。
宗教観に根づく勤勉さと感謝の文化
仏教の影響を受けているミャンマー人は、他人への感謝を忘れず、与えられた仕事を誠実にこなす傾向があります。遅刻や欠勤を避け、地道に努力する姿勢が特徴です。また、謙虚さと感謝の言葉を大切にし、上司や同僚に対して礼儀正しく接します。
日本人との共通点と相違点
ミャンマー人と日本人は、礼儀や協調性を重視する点で似ています。一方で、時間感覚や表現方法には違いがあります。日本人が「時間厳守」を重視するのに対し、ミャンマーでは柔軟さを重んじる場面も多く見られます。この差を理解し、双方が歩み寄る姿勢を持つことが重要です。
こうした特性を理解することで、企業はミャンマー人材の強みをより活かすことができます。次は、日本企業でミャンマー人雇用が増えている背景を解説します。
日本企業でミャンマー人雇用が増えている理由
特定技能制度による就労機会の拡大
2019年に創設された特定技能制度により、ミャンマー人の日本での就労機会が大きく広がりました。現在では製造業・外食業・建設業などさまざまな分野で受け入れが進んでいます。この制度により、技能実習生から特定技能1号への移行も可能となり、長期雇用が実現しやすくなりました。
高い学習意欲と日本語レベルの向上
ミャンマー人は日本文化への関心が高く、日本語を積極的に学ぶ若者が増えています。現地には日本語学校が多数あり、特定技能試験や日本語能力試験(JLPT)に挑戦する人も多いです。
言葉の壁を乗り越える努力を惜しまない点は、企業にとって大きな魅力といえます。
他国人材との比較にみる特性
ベトナム・インドネシアなど他国の人材と比べると、ミャンマー人は温厚で協調性が高い傾向があります。また、家族中心の文化や宗教心の強さから、真面目で安定した就労姿勢を示す人が多い点も特徴です。
企業にとってのメリットと留意点
ミャンマー人の採用は、安定した労働力確保に加えて、組織文化の多様化にもつながります。ただし、宗教行事や食習慣への配慮、日本語での細かなニュアンスの補足などが求められます。
この点を理解し、現場でのフォロー体制を整えることで、定着率を高めることができます。
次は、ミャンマー人社員とのコミュニケーションの具体的なポイントを解説します。
ミャンマー人社員と信頼関係を築くコミュニケーションのコツ
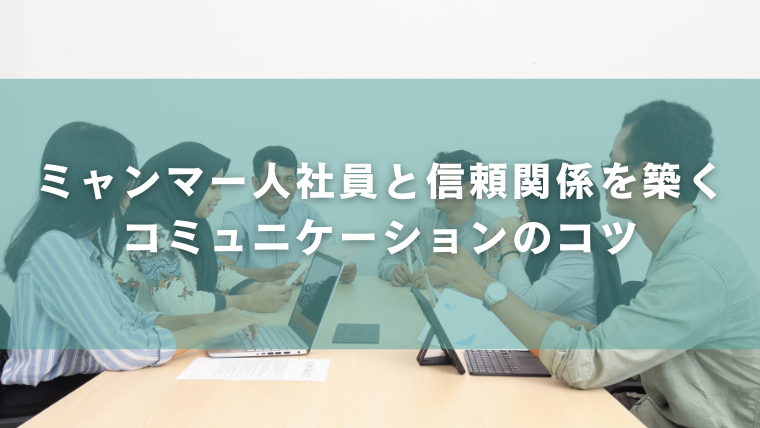
日本語・英語・ミャンマー語の使い分け方
ミャンマー人社員とのコミュニケーションでは、言語の使い分けが重要です。基本的には日本語を使用しますが、理解度に応じて英語を併用することで誤解を防げます。
ミャンマー語しか話せない場合でも、翻訳アプリや現場リーダーを介して意思疎通を図ることが可能です。
- 作業指示などの重要事項は「短く・簡潔に」伝える
- 図や写真を用いると理解が深まる
- あいさつや感謝の言葉は本人の母語で伝えると信頼関係が深まりやすい
このような配慮により、職場の雰囲気が良くなり、ミスやトラブルも減少します。
注意・指導時に配慮すべき文化的背景
ミャンマーでは「人前で叱責されること」は強い恥と感じられます。そのため、注意や指導を行う際は、人前で感情的にならず、個別に静かに伝えることが基本です。
また、意見を求めても「はい」と答えるのは同意ではなく、相手を尊重する意味を持つこともあります。この文化的背景を理解せずに一方的に判断すると、誤解が生じる可能性があります。
感謝・尊重を伝える適切な表現
ミャンマー人は他者からの感謝や称賛に強くモチベーションを感じます。特に、「ありがとう」「助かりました」といった言葉を日常的にかけることで、職場の信頼関係が深まります。
また、宗教的背景から「他者を敬う」「穏やかに話す」姿勢を持つため、対話時には声のトーンや言葉遣いにも配慮することが大切です。感謝や労いを形にすることで、仕事への意欲がさらに高まります。
宗教行事・家族事情への理解と支援
ミャンマーでは、仏教の行事や家族との時間を重視する文化があります。特に「水かけ祭り(ティンジャン)」や家族の法要などは大切にされており、可能な範囲で休暇や配慮を行うと信頼が深まります。
家族が病気の際に早退を希望する場合なども、理解を示すことで社員は安心して働くことができます。企業として宗教や家族を尊重する姿勢を持つことが、長期的な定着支援の鍵となります。
次に、実際にミャンマー人を雇用する際に必要な手続きとサポート体制について説明します。
ミャンマー人雇用に必要な手続きとサポート体制
特定技能・技能実習などの在留資格の基本
ミャンマー人を雇用する場合、主に「技能実習」または「特定技能1号」の在留資格で受け入れるケースが一般的です。
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした制度で、実習生として一定期間働きながら技術を学びます。
一方、特定技能1号は一定の技能水準と日本語能力を有する人材が即戦力として就労できる制度です。
特定技能1号の対象分野は16分野で、介護・ビルクリーニング・建設・宿泊などが含まれます。
制度の選択や申請方法は専門知識が必要なため、登録支援機関や監理団体を活用するとスムーズです。
受け入れ時の申請・登録支援機関の活用
外国人材の受け入れには、出入国在留管理庁への申請が必要です。特定技能の場合、企業は「支援計画」を策定し、生活・職業支援を行う義務があります。
登録支援機関を利用すれば、入国・在留手続き、生活サポート、日本語教育などを一括で支援してもらうことが可能です。
オープンケア協同組合のような監理団体では、インドネシア人材に特化していますが、同様に制度運用や生活支援のノウハウを持つ団体に相談することで、負担を軽減できます。
住居確保と生活支援の重要性
特定技能外国人を雇用する際、企業には住居の確保が求められます。これは任意ではなく、在留資格申請や受け入れ基準に含まれる重要な要件です。
- 住まいの確保(寮・社宅など)
- 通信環境や生活用品の整備
- 宗教上の配慮(礼拝スペース、食文化など)
これらを整備することで、安心して働ける環境を提供でき、離職防止にもつながります。
定着を促すマネジメントとフォロー体制
ミャンマー人材の定着には、採用後のサポート体制が欠かせません。
- 定期面談を通じて不安や悩みを早期に把握する
- 現場リーダーが文化や宗教を理解して指導にあたる
- 同国出身者同士の交流機会を設ける
こうした工夫により、企業への信頼感と働く意欲が高まります。
支援体制を整えることで、長期的な雇用関係の構築が可能になります。
まとめ|文化理解が信頼関係と職場定着につながる
ミャンマー人は穏やかで思いやりがあり、家族や信仰を大切にする国民性を持っています。こうした背景を理解し、文化や宗教への尊重を示すことで、日本企業はより良い職場環境を築くことができます。
特定技能制度の拡大により、今後もミャンマー人材との共働機会は増えると見込まれます。採用だけでなく、長期的な定着支援を見据えた体制づくりを行うことが、双方にとって持続可能な関係構築につながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/