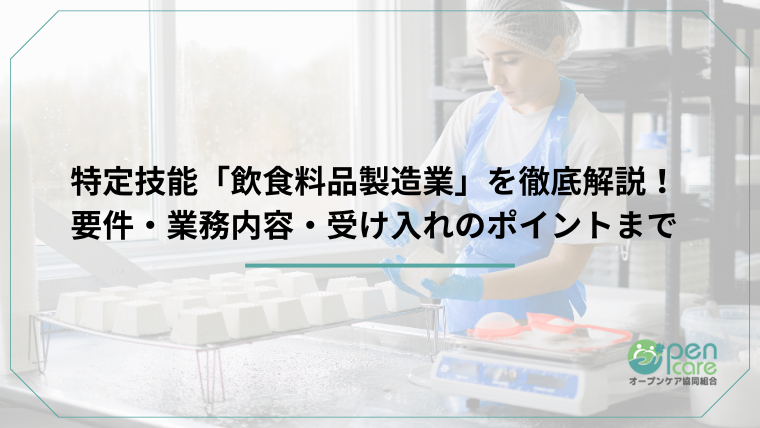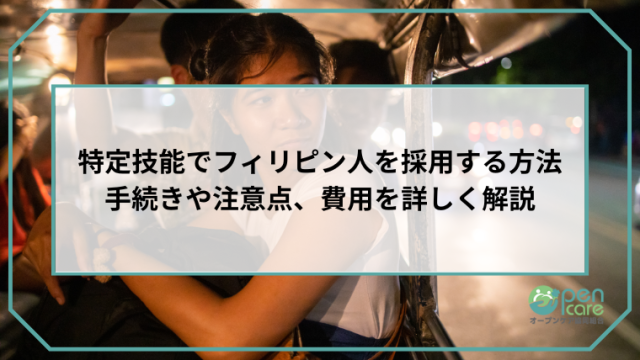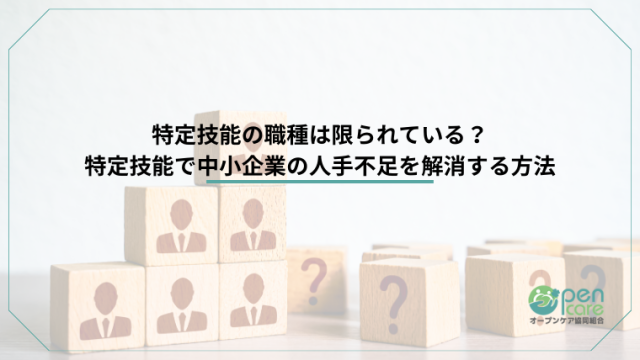飲食料品製造業では人手不足が続いており、2019年に始まった特定技能制度により、外国人の就労が可能となりました。この制度を活用すれば、日本人と同様に食品や飲料の製造工程に従事できます。
本記事では、特定技能「飲食料品製造業」分野の制度概要、業務範囲、受け入れ条件、在留資格取得の流れ、注意点などを整理し、導入を検討している企業向けにわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度と飲食料品製造業が対象となった背景
2019年に制度が創設された理由と社会的背景
日本国内では少子高齢化が進行し、多くの産業で人材不足が問題となっています。とくに、現場作業を中心とした業種では若年層の就業希望者が減少し、国内人材の確保が難しくなっていました。こうした背景から、即戦力となる外国人労働者を受け入れるために創設されたのが特定技能制度です。
この制度は2019年4月にスタートし、従来の技能実習制度とは異なり、労働力としての受け入れを前提とした制度設計が特徴です。特定技能制度は、日本語や業務知識の基礎がある外国人に対して、就労機会を開放することで、業界全体の人材確保を後押しすることを目的としています。
対象となる分野は、人手不足が顕著な業界に限定されており、製造業・農業・介護・建設などとともに、飲食料品製造業もその一つとして含まれています。
飲食料品製造業分野が加わった経緯と意義
飲食料品製造業は、日本国内における食品・飲料の製造を支える重要な分野です。小売・外食産業の拡大や、工場の24時間稼働体制などにより、生産ラインを支える労働力の需要は年々高まっています。
一方で、現場では以下のような課題がありました。
- 慢性的な人材不足により、求人を出しても応募が少ない
- シフト制や夜勤を含む勤務が敬遠されがち
- 作業内容が単純作業に見られがちで、若年層の就業定着が難しい
こうした実情を受け、飲食料品製造業は2019年の制度発足当初から、特定技能の対象分野に指定されました。これにより、外国人材の受け入れが制度的に可能となり、多くの企業が即戦力人材の確保に取り組み始めています。
制度の導入により、企業側は以下のようなメリットを得られるようになりました。
- 製造工程に必要な人材を安定的に確保できる
- 日本語能力や業務知識の水準を事前に確認した上で雇用できる
- 長期的な雇用や技能の継承も視野に入れた採用が可能
このように、飲食料品製造業分野における特定技能制度の活用は、生産体制の維持と将来の人材戦略の両面で意義のある選択肢となっています。
飲食料品製造業で従事できる業務と対象職種

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能1号で認められる主な業務内容
特定技能1号では、飲食料品製造業において実際の製造現場で行われる一連の作業に従事することが可能です。対象となる業務は「飲料や加工食品の製造」に関わるものが中心で、一定の衛生管理と作業手順を理解したうえで行える範囲が明確に定められています。
主な業務の例
- 食材のカット・計量・仕込み
- 機械による加熱・冷却・包装作業の操作補助
- 製品の検品・ラベル貼付・箱詰め
- 清掃・洗浄作業、使用機器の点検補助
これらの作業は、習熟に特別な資格を必要としない一方で、安全管理や衛生知識が必要とされるため、事前の研修や指導が重要です。特定技能外国人は、試験合格などによりこうした業務への理解力を証明したうえで採用されます。
日本人と同様に可能な作業の具体例
特定技能外国人は、制度上、日本人と同じ条件で現場作業に従事できることが前提とされています。つまり、単純な補助業務だけでなく、生産ラインの中核を担うような作業も任せることが可能です。
たとえば、以下のような作業が対象となります。
- 製造機械の操作とトラブル対応(簡易なもの)
- 衛生マニュアルに基づく点検や報告業務
- 作業手順書に沿ったライン管理や製品切り替え時の設定変更
もちろん、作業範囲は企業のマニュアルや本人のスキルレベルに応じて調整されますが、制度上は「できない作業」ではなく、一定の教育と支援があれば実施可能な業務として認められています。
このように、企業側の指導体制が整っていれば、日本人と同様の役割を持つスタッフとして活躍してもらうことが可能です。
技能実習との違いや2号移行の有無について
よく比較される制度として技能実習がありますが、両者には目的や期間、移行要件などの違いがあります。技能実習は「技能移転」が目的であるのに対し、特定技能は即戦力としての「労働力確保」が目的です。
特定技能1号では、基本的に以下のような特徴があります。
- 最長5年間の就労が可能(更新制)
- 技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で移行可能
- 飲食料品製造業分野では現在、特定技能2号への移行対象外
つまり、将来的な永続的雇用につながる「2号」資格への移行は現時点で想定されていないため、中長期的な雇用設計を前提に受け入れ計画を立てる必要があります。
特定技能の在留期間については「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
受け入れに必要な条件と在留資格取得の流れ
受け入れ企業が満たすべき主な要件
特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも明確な条件が設けられています。単に求人を出せばよいというわけではなく、制度に適合した体制の整備と、労働環境の適切な管理が求められます。
主な受け入れ要件
- 特定技能対象分野での事業実績がある(飲食料品製造業など)
- 日本人と同等以上の待遇で雇用契約を締結している
- 雇用契約の内容が適正であること(就業条件明示、支払方法など)
- 労働・社会保険への適切な加入と手続きが済んでいる
- 支援体制(自社または登録支援機関による)を構築している
これらを満たさない場合、在留資格の申請が受理されない、あるいは許可されないことがあります。採用の前段階で、必要な書類や社内体制を確認しておくことが重要です。
特定技能外国人が取得すべき試験と資格
外国人が飲食料品製造業分野で特定技能1号として働くには、所定の試験に合格することが必要です。これは制度上の要件であり、技能水準と日本語能力の両面が求められます。
必要な試験は主に以下の2つです。
ただし、過去に技能実習2号を良好に修了している場合、評価試験が免除されるケースもあります。この条件に該当するかどうかの確認は、受け入れ前に慎重に行う必要があります。
在留資格申請から雇用までの基本的な流れ
外国人を特定技能で雇用するためには、在留資格「特定技能1号」の申請が必要です。企業と本人が協力し、申請から許可、そして実際の雇用までに必要なステップを計画的に進めることが求められます。
基本的な流れは以下の通りです。
- 試験合格・技能実習修了など、外国人の受け入れ要件の確認
- 雇用契約の締結と支援計画の作成(支援機関と連携する場合あり)
- 出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」
- 許可後、外国人が日本へ入国し、就労開始
- 就労開始後、支援記録や勤務実績の報告が義務付けられる
この一連の流れは、制度に沿った書類の準備と期限管理がカギとなります。初めて受け入れる企業では、登録支援機関の協力を得ながら進めると、手続きの負担を軽減できます。
雇用・管理における注意点と支援体制

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
職場環境の整備と教育サポートの重要性
特定技能外国人を受け入れたあと、円滑な業務遂行のためには職場環境の整備と適切な教育体制が欠かせません。特に飲食料品製造業では、衛生管理やルール順守が重要視されるため、入社後の導入研修や日常的なフォロー体制が必要です。
注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 作業マニュアルや衛生管理手順を多言語または図解で用意する
- 作業内容だけでなく、日本での生活マナーや社内ルールも説明する
- 現場リーダーや教育担当者を明確にし、日常の相談先を設ける
- 定期的な面談や簡易テストで理解度を確認する
こうした取り組みを通じて、外国人労働者が早期に職場へ適応し、定着率の向上にもつながります。特に初めて受け入れる企業では、職場全体の意識共有も重要です。
登録支援機関や協力機関との連携方法
特定技能制度では、外国人労働者に対して生活支援や就労支援を行う責任が受け入れ側にあります。自社で対応できない場合は、登録支援機関へ業務を委託することが可能です。
登録支援機関と連携することで、以下のような支援が実施されます。
- 住居の確保、銀行口座・携帯電話契約の支援
- 生活オリエンテーションや日本語学習の支援
- 公的手続きの同行や通訳対応
- 悩みやトラブルへの相談対応と報告書の作成
これらは支援計画書として事前に作成・提出し、受け入れ企業が主体となって責任を持って実施する必要があります。委託した場合も、計画が適切に実行されているかどうかを企業自身が確認・管理する義務があります。
転職・途中離職が発生した場合の対応策
特定技能外国人の受け入れにおいて、契約期間中の離職や転職が発生することも想定しておく必要があります。制度上、外国人本人の希望によって転職することは可能ですが、正当な手続きが必要です。
離職が発生した場合の注意点
- 離職が決まったら速やかに出入国在留管理庁へ報告する
- 企業側は最終的な支援実績報告書を提出する
- 再就職先が見つかるまでの支援を、一定期間提供する必要がある
- 無断退職や音信不通の場合は、事実関係を文書で整理し報告
また、再雇用や人員補充のための準備も並行して進める必要があります。転職や離職が制度に与える影響を理解し、計画的な人材マネジメントを行うことが重要です。
特定技能外国人を受け入れるメリットと活用の広がり
人手不足の解消と安定した生産体制の実現
飲食料品製造業では、慢性的な人手不足が続いています。少子高齢化の影響や働き手の業界離れにより、現場では採用難が常態化しています。こうした状況のなかで、特定技能外国人の活用は、生産ラインの安定運用に貢献できる現実的な選択肢となっています。
特定技能制度を通じて、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 即戦力として一定の知識・技術を持った人材を採用できる
- シフト制や夜勤を含む柔軟な就業体制に対応できる
- 定着支援をしっかり行えば、長期的な人材確保も可能になる
実際に制度を活用している企業では、業務の効率化や生産性向上といった成果が出ている例も少なくありません。とくに繁忙期の人材確保や突発的な欠員対応など、リスクを抑える手段としても注目されています。
職場における多様性の向上と定着率への効果
外国人労働者の受け入れは、単に人数を補うだけでなく、職場に新たな視点や文化をもたらす効果も期待できます。さまざまな価値観を持つスタッフが共に働くことで、コミュニケーションの活性化や職場全体の意識改革にもつながるケースがあります。
また、以下のような環境整備を行うことで、外国人材の職場定着率を高める効果も見込めます。
- 明確なキャリアパスの提示(昇給・リーダー職の登用など)
- 日常的な相談体制の強化と評価制度の整備
- 社内イベントやレクリエーションを通じた交流の促進
特定技能制度は5年という在留期間の上限がありますが、制度を理解したうえで企業側が積極的に環境を整えることで、実質的な長期雇用も実現可能です。
外国人労働者との長期的な関係構築のポイント
特定技能制度を効果的に活用するには、単発の採用にとどまらず、継続的な受け入れと教育、制度理解の蓄積が欠かせません。単年度ごとの対応ではなく、複数年にわたる人材戦略として位置づけることが重要です。
企業が意識すべきポイントは以下の通りです。
- 支援体制を社内の仕組みとして定着させる
- 日本人スタッフとの相互理解を深める場をつくる
- 管理・支援の記録を継続的に蓄積し、次回以降の採用に生かす
こうした取り組みにより、単なる制度対応ではなく、外国人スタッフと企業が共に成長していける関係性の構築が可能になります。
制度を理解し、適切な受け入れで人材確保へつなげよう
飲食料品製造業分野における特定技能制度の活用は、人手不足の解消に加え、安定した生産体制の構築に役立ちます。受け入れには企業の体制整備や支援が不可欠ですが、制度を正しく理解し、外国人材との関係を大切にすることで、長期的な雇用と職場の活性化につながります。将来を見据えた人材戦略の一環として、特定技能の活用を検討してみてください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/