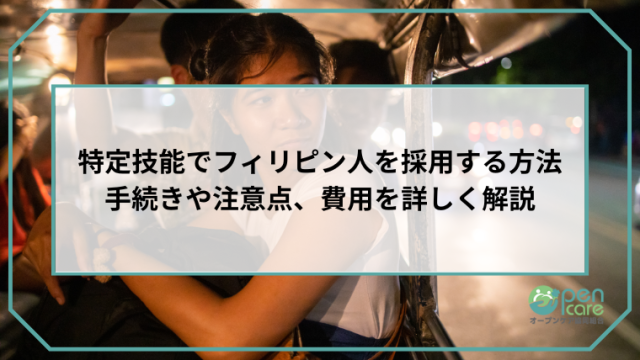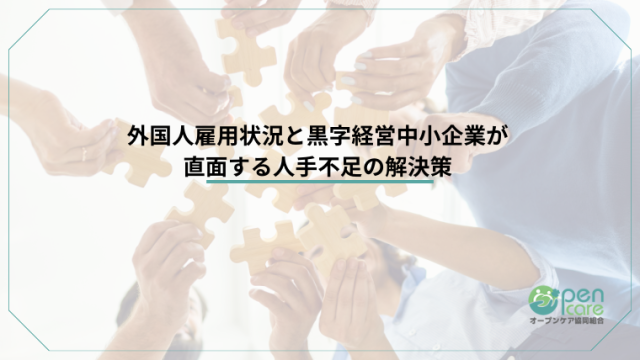空港業務や航空機整備の現場では、長年にわたり人手不足が深刻化しています。特に地上支援作業や機体の保守点検など、安全と正確さが求められる業務において、安定的な人材の確保が課題となってきました。こうした背景を受けて、即戦力となる外国人材を受け入れるために、特定技能「航空」分野が制度化されました。
本記事では、特定技能航空制度の基本的な仕組み、対応可能な業務や在留資格の取得要件、企業が満たすべき条件や注意点まで、採用・雇用の実務に役立つ情報を詳しく解説します。外国人材の活用を検討している航空関連事業者の方必見です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能航空分野の制度概要と導入の背景
航空業界では近年、人手不足が深刻化しており、空港の運営や航空機整備に支障をきたす事例も増加しています。 こうした課題に対応するため、2019年に施工された特定技能制度の対象分野として、航空分野が加えられました。
ここでは、その制度の背景と位置づけについて解説します。
航空業界における人手不足と制度創設の経緯
航空業界は、多くの作業が高い安全性と迅速な対応を要求される分野であり、整備や地上支援などの現場では高度な専門性と責任感が求められます。一方で、長時間労働や不規則な勤務形態が敬遠され、若年層の離職や人材確保の困難化が進んでいます。
とくに「空港グランドハンドリング」や「航空機整備」に従事するスタッフの不足は、運航スケジュールや空港機能全体の安定運営に影響を与える深刻な課題とされてきました。
このような背景から、即戦力となる外国人材の活用が検討され、「特定技能航空分野」として制度に組み込まれることになりました。政府は、制度を通じて現場で必要とされる技能を持つ外国人材の受け入れを促進し、航空分野の安定運営を支援する方針を打ち出しています。
特定技能制度における航空分野の位置づけ
特定技能制度は、特定の産業分野における人材不足を解消するために導入された在留資格制度です。その中で航空分野は、国土交通省の管轄のもとで運用されており、他の分野に比べても業務の専門性と安全性への対応が強く求められる特徴を持っています。
航空分野で就労可能な職種は大きく分けて以下の2つです。
- 航空機整備業務(エンジン、装備品などの保守・点検・修理)
- 空港グランドハンドリング業務(手荷物や貨物の搭降載、誘導、航空機の牽引など)
これらの業務に従事するためには、「航空分野特定技能評価試験」への合格や、必要な日本語能力の証明が求められます。また、企業側も「受け入れ機関の条件」を満たし、登録支援機関との連携や分野特定技能協議会への参加などが必要とされます。
この制度は、単なる労働力の補填ではなく、航空法や空港管理規則に基づいた体制のなかで、技能を持った人材が安全に従事できる仕組みを整えることを目的としています。今後の航空業界の発展には、こうした制度の適切な活用が不可欠といえるでしょう。
対応できる業務の種類と職種の違い
特定技能「航空」分野では、対応可能な職種が明確に定められており、誰もがあらゆる作業に就けるわけではありません。 特定技能外国人が従事できるのは、「航空機整備」と「空港グランドハンドリング」の2職種であり、それぞれに必要なスキルと条件があります。正しい理解のもと、適切な採用・配属が求められます。
航空機整備業務における対象作業と条件
「航空機整備業務」は、航空機の安全な運航を支える重要な役割を担っています。特定技能外国人が対応できる業務には、以下のような作業が含まれます。
- 機体やエンジン、装備品の定期点検
- 整備記録の作成と確認
- 故障箇所の修理・交換作業
- 清掃・塗装・軽微な改修作業
これらの作業は、航空法および関連する整備基準に基づいて実施される必要があり、専門知識と正確な作業が求められます。
航空機整備の現場では、整備士資格が必要な業務も多く含まれていますが、特定技能制度では「整備士資格が不要な範囲の整備作業」を担当することが想定されています。そのため、整備内容の範囲設定や教育体制の整備が受け入れ企業には求められます。
また、航空機整備業務に従事する企業は、国土交通省の認定を受けた整備事業者であることが必須となっており、登録支援機関を通じた支援計画の策定も必要です。
空港グランドハンドリング業務の内容と注意点
「空港グランドハンドリング業務」は、航空機の運航に直接関わる地上支援作業全般を指します。具体的には以下のような作業が含まれます。
- 手荷物・貨物の搭降載
- 航空機の誘導、駐機位置への誘導
- プッシュバックや牽引作業
- 機体周辺の安全確認、備品の設置と撤去
これらの作業は、空港管理規則や航空法に準拠して行われるため、厳格なルールと手順が存在します。特定技能外国人が従事する場合も、同等の教育と実務トレーニングを実施することが義務付けられています。
また、空港によっては、特定エリアでの作業に空港事業者の認定や安全講習の受講が必要となる場合もあります。受け入れ企業は、作業の内容と責任範囲を明確にした上で、適切な労務管理と業務指導を行うことが求められます。
このように、特定技能制度の対象業務は広いように見えても、航空分野では「安全」「正確」「法令遵守」が最優先事項となるため、事前の確認と準備が不可欠です。
特定技能外国人の採用要件と在留資格取得の流れ
特定技能「航空」分野において外国人材を採用するには、評価試験の合格と在留資格の取得が必要条件となります。制度上、受け入れ企業は採用前の要件を十分に理解し、候補者が必要な基準を満たしているかどうかを確認したうえで手続きを進める必要があります。
評価試験の構成・出題範囲と合格基準
航空分野で就労を希望する外国人は、「航空分野特定技能評価試験」に合格する必要があります。評価試験は、「航空機整備業務」または「空港グランドハンドリング業務」のいずれかに対応する形で実施され、職種ごとに試験内容が異なります。
【評価試験の主な構成】
- 学科試験:安全管理、基本作業手順、関連する法令や規則に関する設問
- 実技試験:業務に必要な動作、手順、判断力を確認するシミュレーション形式の課題
試験は日本国内および一部海外で実施され、合格証明書が交付された時点で、採用に必要な「技能基準」を満たしたと見なされます。
また、過去に技能実習制度で「航空関係の職種」に従事し、2号を修了した場合、評価試験が免除となる可能性もあります。
試験の出題範囲やレベルは、職務に直結する実務知識を中心とした構成で、航空業に関する基本的な理解が求められます。事前に出題例や公式ガイドラインを確認し、国土交通省や関連機関が公表する最新情報を把握しておくことが大切です。
在留資格の申請・取得方法と日本語要件
評価試験に合格した外国人材は、「特定技能1号(航空分野)」の在留資格を申請できます。申請は企業が主体となって出入国在留管理庁に対して行い、以下の書類が必要です。
【主な申請書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書、支援計画書
- 評価試験合格証明書
- 日本語能力試験の合格証明(後述)
- 企業の体制や条件を示す書類(法人登記簿、直近の決算書など)
在留資格の取得には、日本語能力の証明も要件に含まれます。 現在、以下のいずれかの試験に合格していることが必要です。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
この日本語能力は、現場での指示理解や安全確認、報告対応が円滑に行えるかどうかを判断する基準として重視されます。試験のスコアだけでなく、日常的なコミュニケーション能力の確認も重要です。
申請が受理された後は、在留資格の交付をもって正式に特定技能外国人として就労が可能になります。企業側は申請後のフォローや、ビザ発給・入国に伴う案内も適切に対応する必要があります。
受け入れ企業が満たすべき条件と注意点
特定技能「航空」分野で外国人材を受け入れる企業には、法律や制度に基づく明確な要件と運用体制の整備が求められます。受け入れにあたっては、単に雇用契約を結ぶだけでなく、支援体制・委託業務の管理・協議会との連携といった、広範な責任を担うことになります。
雇用契約・支援体制・委託業務の取扱い
まず、外国人と締結する雇用契約は、「日本人と同等以上の待遇」を前提にしなければなりません。契約には以下の情報を明記する必要があります。
- 業務内容(航空機整備、または空港グランドハンドリング)
- 勤務地・勤務時間・休日・給与・社会保険加入の有無
- 労働期間と更新条件、解雇規定などの詳細
また、企業は「支援計画」を作成し、特定技能外国人が日本で安定的に生活・就労できるよう支援しなければなりません。主な支援内容には、以下が含まれます。
- 日本語学習支援、生活オリエンテーションの実施
- 住居の確保、行政手続きの補助
- 職場での相談対応やトラブル時のサポート
これらの支援は企業が自社で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することも認められています。ただし、委託する場合も最終的な責任は企業側にあるため、委託先の実績や体制を十分に確認する必要があります。
特に空港内での作業においては、委託元・委託先との契約関係や作業責任の所在が曖昧にならないよう、業務範囲を文書で明確化しておくことが重要です。
登録支援機関・分野特定技能協議会との連携
受け入れ企業がすべきことは支援体制の構築だけではありません。制度全体の健全な運用を維持するため、外部機関との連携も義務付けられています。
まず、外国人材の支援を委託する場合、必ず出入国在留管理庁に登録された登録支援機関を選定する必要があります。登録支援機関は、支援実施状況を報告する義務を負っており、企業と支援機関が連携して計画通りの支援が行われているか確認する仕組みが求められます。
また、航空分野では「分野特定技能協議会(航空分野特定技能協議)」が設置されており、受け入れ企業はこの協議会に参加し、以下のような活動を行う必要があります。
- 受け入れ状況や支援内容の定期的な報告
- 制度運用に関する情報共有や事例紹介
- 適正な受け入れに関するガイドラインの遵守
協議会への参加は、単なる形式的な手続きではなく、航空分野における特定技能制度の信頼性を維持するための重要な役割を担っています。企業が制度を活用する際は、内部体制の整備だけでなく、業界全体との連携意識を持つことが求められます。
登録支援機関については「登録支援機関とは?特定技能の支援を委託するときの契約と連携の基本を解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
採用後の運用ポイントと現場管理の実務
特定技能外国人を受け入れたあとの運用では、職場内での管理体制の整備と安全対策の徹底が不可欠です。航空業務は高い精度と迅速性を求められるだけでなく、安全性が最も重視される分野であるため、採用後の管理体制が企業の信頼性に直結します。
業務マニュアルの整備と安全管理
航空機整備や空港グランドハンドリングの現場では、作業手順・使用機材・安全確認の方法が明文化されていることが基本とされています。特定技能外国人が従事する場合も、これらの業務に関するマニュアルや指導体制の整備が必要です。
具体的には、以下のような対策が重要です。
- 多言語またはやさしい日本語による作業マニュアルの整備
- 研修プログラムの構築と定期的な更新
- 作業別のリスクアセスメントと事前説明の実施
- 国土交通省や空港管理規則に基づく安全基準の遵守
特に、装備品の取り扱いや航空機周辺での作業に関しては、一つのミスが重大な事故につながる可能性があるため、反復的な指導とチェック体制の構築が重要です。
また、現場ごとに求められる資格や講習の受講状況も把握し、資格の更新時期や必要な研修スケジュールの管理も企業の責任として対応する必要があります。
労務管理・報告義務・トラブル防止策
採用後は、日常的な労務管理や法令に基づく報告業務も欠かせません。特定技能制度では、出入国在留管理庁への定期報告義務があり、受け入れ企業は以下のような項目を報告する必要があります。
- 就労状況(勤務日数、労働時間、給与支給状況など)
- 支援計画の実施状況
- 労働条件や勤務体制の変更があった場合の報告
これらの報告を怠った場合、制度違反として認定され、今後の受け入れが制限される可能性があります。
また、外国人材とのコミュニケーションギャップや文化的な違いに起因するトラブルも起こり得ます。これを未然に防ぐために、以下のような取り組みが効果的です。
- 定期的な面談による就業状況の確認
- 社内相談窓口の設置と運用
- 同僚・上司への多文化理解に関する研修の実施
- 登録支援機関と連携したフォロー体制の活用
これらの対応を通じて、特定技能外国人が安心して働き続けられる環境を整えることができます。結果的に、離職率の低下や現場の安定につながり、企業全体の生産性と信頼性向上にも寄与します。
まとめ
特定技能「航空」制度は、航空機整備や空港グランドハンドリングなど、安全と正確性が求められる現場において、即戦力となる外国人材を受け入れるための有効な仕組みです。評価試験や在留資格の取得、日本語要件などの採用条件を正しく理解し、企業側の支援体制や法令遵守を徹底することで、安定的な人材活用が実現できます。制度を正しく活用することで、航空業界全体の人手不足の解消と持続可能な運営につながるでしょう。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/