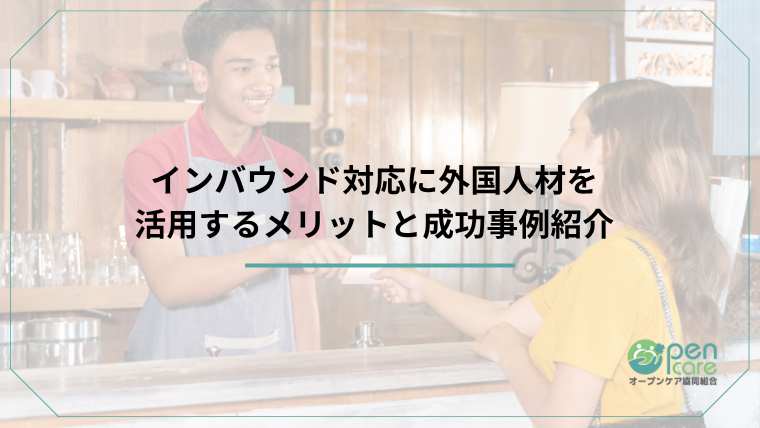訪日外国人観光客の回復が本格化する2025年、サービス現場では多言語対応や異文化理解が欠かせない要素となっています。こうしたニーズに対応する手段として、外国人材の採用が注目されています。
本記事では、接客・案内業務に外国人スタッフを活用するメリットや成功事例、受け入れ時の課題と対策についてわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
インバウンド対応が求められる3つの背景

訪日観光客の回復が進む中、日本の接客・サービス業における「インバウンド対応」は急務となっています。特に観光・宿泊・飲食・小売といった現場では、外国人観光客との円滑なコミュニケーションや、多様なニーズへの対応が求められています。
本章では、外国人材の活用が注目される3つの背景を紹介します。
訪日観光客数の急増と対応力不足
2025年現在、訪日外国人観光客はコロナ前の水準をほぼ回復し、主要都市や観光地では連日多くのインバウンド客で賑わいを見せています。接客や案内の現場では多言語対応や文化理解といった対応力がますます求められています。
しかし、現場では以下のような課題が顕在化しています。
- 外国語対応できるスタッフが不足している
- 接客の質にバラつきが出やすい
- 観光客との意思疎通に時間がかかる
特に小規模な施設では、人手とスキルの両面で限界が見られるようになっています。
接客・案内業務における多言語対応の必要性
外国人観光客が安心してサービスを受けるには、多言語での案内やコミュニケーションが不可欠です。しかし、日本の多くの現場では以下のような対応が後手に回っているのが実情です。
- メニューや案内板が日本語のみ
- 英語や中国語で接客できるスタッフがいない
- 外国人観光客が質問しづらい雰囲気がある
こうしたギャップを埋めるには、言語面で強みを持つ外国人スタッフの配置が現実的かつ有効な対策となります。
サービス品質向上と人材多様化の流れ
外国人材の採用は、単なる「人手不足の補完」にとどまりません。むしろ、企業のサービス品質向上と競争力強化に直結する要素といえます。
例えば、外国人観光客の視点を持つスタッフが加わることで、メニュー表記や案内の改善など、より利用者目線に立った接客が可能になります。結果として、クレーム予防や顧客満足度の向上にもつながります。
さらに、外国人スタッフとの共働によって、日本人従業員が異文化に触れ、柔軟性や対応力を高める効果もあります。これは企業にとって、国籍や文化を越えて共に働ける「ダイバーシティ推進」の第一歩となるでしょう。
特定技能については「特定技能でインバウンド対応?活用できる業種と条件を徹底解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
外国人材を活用する5つのメリット【接客・案内業務編】
接客や案内業務における外国人材の活用は、単なる人手不足の補完ではなく、サービス品質や企業イメージの向上にも大きく寄与します。ここでは、現場で実際に感じられる代表的な5つのメリットを紹介します。
多言語対応で顧客満足度が向上する
訪日観光客とのコミュニケーションにおいて、言語の壁は最も大きな課題の一つです。外国人スタッフが英語・中国語・韓国語などに対応することで、案内や接客時のストレスを軽減できます。
特に以下の場面でその効果は顕著です。
- ホテルでのチェックイン・チェックアウトの手続き
- 飲食店でのメニュー説明やアレルギー確認
- 商業施設での商品案内や道案内
多言語対応により、外国人観光客が安心してサービスを利用できる環境が整います。
宿泊分野については「特定技能の宿泊分野とは?外国人材の宿泊業務での受入れ方法と人材採用の要件解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
文化理解によりクレームが減少する
言語だけでなく、文化的背景への理解も重要です。外国人スタッフは、自国の習慣や価値観を踏まえた対応ができるため、観光客が戸惑いや違和感を感じる場面を事前に察知し、丁寧にフォローできます。
たとえば、宗教上の配慮や食習慣、ジェスチャーに対する反応など、細かな配慮が求められるケースでは、同じ文化圏出身のスタッフが大きな安心感を提供します。
SNSや口コミを通じた情報拡散が期待できる
外国人スタッフが自身のSNSで職場や勤務先のサービスを紹介することで、企業や店舗の魅力が自然と拡散されます。
- 母国語での投稿により、母国のユーザー層にも届く
- 実体験に基づいた情報発信で信頼度が高まる
- 海外からの来訪者増加にもつながる
このように、従業員の「発信力」が、新たな集客チャネルとして機能します。
外国人観光客が安心して訪問できる
「同じ言語・文化を理解するスタッフがいる」というだけで、訪日観光客の不安は大きく軽減されます。外国人スタッフの存在そのものが、“ウェルカムな空気”を醸成するのです。
これは特に初めて日本を訪れる観光客にとって、心理的な安心材料となり、リピート訪問やポジティブな口コミへとつながる要因となります。
採用難の日本人労働力を補完できる
慢性的な人手不足に悩むサービス業界では、若年層の労働力確保が難しくなっています。そんな中で、意欲と能力を備えた外国人材の採用は、事業継続の大きな支えとなります。
- 短時間勤務やシフト柔軟対応が可能
- 高い就業意欲と責任感を持つ人材が多い
- 特定技能などの制度を活用すれば、長期就労も可能
業務の安定化だけでなく、スタッフ全体の士気向上にもつながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
外国人材を受け入れるために必要な3つの準備

外国人スタッフを職場に受け入れる際、採用して終わりではなく、長く安心して働いてもらうための準備が不可欠です。制度的な理解から社内体制の構築まで、以下の3つの観点で準備を整えることが、定着率と職場の満足度を大きく左右します。
在留資格と労働条件の理解
外国人を採用する際は、必ず本人の在留資格が職務内容と合致しているかを確認する必要があります。たとえば、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「留学」など、在留資格ごとに許可される業務範囲や労働時間の条件が異なります。
採用担当者は以下の点を正しく理解・確認しておくことが求められます。
- 短時間勤務やシフト柔軟対応が可能
- 高い就業意欲と責任感を持つ人材が多い
- 特定技能などの制度を活用すれば、長期就労も可能
違反があった場合、企業側にも処罰が及ぶ可能性があるため、制度の理解は最優先事項です。
導入前研修と受け入れ体制の構築
外国人材がスムーズに業務に慣れるためには、入社前後の導入研修や業務サポート体制が欠かせません。日本語や業務フローに不慣れな人材も多いため、教育コストを見越した準備が必要です。
効果的な受け入れ体制の一例としては、以下が挙げられます。
- 簡潔でやさしい日本語を用いたマニュアルの整備
- OJT形式での段階的な業務習得
- 指導役の日本人スタッフを明確に配置(メンター制度など)
この段階でつまずかないよう、言語面だけでなく文化面でのギャップも配慮した体制が望まれます。
多文化共生を支える社内コミュニケーション
外国人スタッフが長く働き続けられるかどうかは、職場での人間関係やコミュニケーションの質に大きく左右されます。文化や価値観の違いを乗り越え、互いにリスペクトし合える風土をつくることが、安定的な雇用につながります。
具体的な取り組みとしては、
- 月1回のミーティングで現場の意見を聞く場を設ける
- 社内イベントや交流会を通じて関係性を築く
- 宗教・食文化などへの理解を促進する研修を実施
といった、小さな取り組みの積み重ねが信頼関係を生み、定着率を高める土台となります。
インバウンド対応に成功した3つの企業事例
外国人材を実際に受け入れ、インバウンド対応を強化した企業では、接客品質の向上や顧客満足度の改善といった成果が多数報告されています。
ここでは、ホテル業界・飲食業界・自治体連携の3つの具体的な事例を取り上げ、それぞれの成功要因を紹介します。
ホテル業界:外国人スタッフが評価された宿泊施設の事例
ある地方都市のビジネスホテルでは、外国人観光客の増加に対応するため、多言語対応が可能な外国人スタッフをフロント業務に配置しました。採用後は以下のような変化が見られました。
- チェックイン・チェックアウトの所要時間が短縮
- 外国人宿泊客からのレビューに「安心感がある」「説明がわかりやすい」といった高評価が増加
- 英語・中国語での対応により予約件数が増加
このホテルでは、事前に業務マニュアルを英訳し、受け入れ体制を整備したことが、成功のポイントとなりました。また、日本人スタッフと外国人スタッフがペアで対応するなど、混成チームの編成による相互補完が、接客力全体の底上げにつながっています。
飲食業界:メニュー翻訳と案内業務を担った事例
都内の飲食チェーン店では、外国人スタッフをホール業務に配置することで、訪日外国人観光客の来店数が大きく伸びました。とくにメニュー翻訳の精度と案内時のコミュニケーションが改善された点が好評でした。
導入当初は「日本語での注文確認が難しい」といった課題もありましたが、タブレット注文とピクトグラムを併用することで、言語の壁を克服しました。結果として、以下のような効果が得られました。
- メニューに英語・中国語・韓国語を追加
- 外国人スタッフによるおすすめ提案で単価が上昇
- 多言語対応によるSNSでの拡散と集客増加
外国人スタッフが積極的に母国語でSNS投稿を行い、母国からの旅行者に向けて店の魅力を発信していたことも、大きな波及効果を生みました。
観光案内所・自治体連携:外国人目線のサービス改善
地方自治体が運営する観光案内所では、地域在住の外国人をスタッフとして採用し、地域ならではの接客強化を行いました。彼らは単なる案内役にとどまらず、「観光客の視点」で不便な点を洗い出し、サービス改善にも貢献しました。
具体的には、
- 外国語パンフレットの文言修正
- 人気観光地の交通案内の見直し
- 小さな商店への多言語POP導入の提案
といった現場発のアイデアが多く採用され、地域全体の「おもてなし力」向上につながりました。このように、外国人材が「サービス提供者」であると同時に、「改善提案者」としても活躍できる好事例です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
外国人材活用で起こりうる3つの課題と解決策
外国人材の受け入れは多くのメリットをもたらしますが、その一方で、現場ではさまざまな課題に直面することもあります。ここでは、特に多くの企業が直面する3つの主要な課題と、その具体的な解決策について紹介します。
日本語力・接客マナーのギャップ
外国人スタッフが接客業務を担う際、日本語能力や日本ならではの接遇マナーにギャップを感じるケースが少なくありません。特に、丁寧語やお辞儀の角度といった文化的な細部は、初期段階での指導が不可欠です。
この課題に対する解決策としては、
- 接客に必要な日本語表現に特化した社内研修の実施
- ロールプレイ形式によるマナー研修の導入
- マニュアルの多言語化と視覚教材の活用(動画・イラストなど)
などが効果的です。長期的には、日本語学校との連携やeラーニング教材の提供なども検討するとよいでしょう。
職場での文化摩擦とその解消法
宗教的配慮、食習慣、休暇の取り方など、文化の違いが日常業務に影響することもあります。これらが積み重なることで、日本人スタッフとの間に誤解や不満が生じる可能性があります。
文化的な摩擦を最小限に抑えるためには、以下のような取り組みが有効です。
- 相互理解を促す「多文化共生研修」の実施
- 食事や礼拝などへの配慮ルールを社内で共有
- 日本人と外国人が混在するチーム単位での対話促進
一方通行の指導ではなく、互いに歩み寄る意識が定着すれば、摩擦はチームの多様性として活かせる要素にもなります。
法令違反を防ぐための労務管理
外国人材の雇用においては、在留資格の確認や就労条件の管理を適切に行わなければ、企業側にも罰則が科される恐れがあります。特に、留学生の資格外活動時間超過や、在留期限切れによる就労などは注意が必要です。
これを防ぐために、企業は次のような対策を講じることが求められます。
- 在留カードのコピーを保管し、有効期限を定期的にチェック
- 出入国在留管理庁の最新ガイドラインを確認し運用ルールを整備
- 勤怠システムに勤務時間制限を自動で反映させる機能を導入
社内の担当者だけで対応が難しい場合は、行政書士や外国人雇用に詳しい専門機関への相談も視野に入れると安心です。
よくある質問(FAQ)
-
外国人材の接客対応はどのような業種で活用されていますか?
-
主にホテル・旅館、飲食店、小売、観光案内所など、訪日外国人と直接接する機会が多い業種で活用されています。多言語対応や文化理解が求められる現場で特に効果を発揮します。
-
外国人スタッフの日本語レベルに不安があります。対応できますか?
-
はい、当組合では日本語能力を一定水準以上に習得した人材をご紹介しています。また、必要に応じて入社前研修やOJTの支援も行っていますので安心して受け入れ可能です。
-
在留資格や制度の理解が難しいのですが、サポートしてもらえますか?
-
法令対応や在留資格の確認は専門的な知識が必要です。当組合では、制度に則った人材紹介・書類作成・申請サポートまでを一括で対応しております。
-
小規模な店舗でも外国人材の受け入れは可能ですか?
-
可能です。特に接客や案内など、1~2名の外国人スタッフでも効果が実感できるケースが多くあります。業務内容に応じた最適なマッチングをご提案いたします。
-
外国人材を受け入れるまでの流れを教えてください。
-
一般的には「ヒアリング→人材選定→面談→契約→受け入れ準備→勤務開始」という流れです。Zoomを活用した事前面談や受け入れ体制づくりもサポートしています。
インバウンド対応の強化には「人材の多様化」が不可欠
インバウンド需要の高まりに伴い、外国人観光客への対応力はサービス業全体の重要課題となっています。接客・案内業務において、外国人材の活用は多言語対応や文化理解を補完し、顧客満足度やサービス品質の向上に直結します。
本記事で紹介したように、外国人材の受け入れには制度理解や社内体制の整備が必要ですが、それを乗り越えることで大きな成果が得られます。特に中小企業にとっては、限られた人材リソースを補う現実的な選択肢となり得るでしょう。
インバウンド対応を強化したい企業こそ、戦略的な「人材の多様化」に一歩踏み出す時期です。
当組合では、接客・案内業務に適した外国人材の紹介から受け入れ体制の構築支援まで、一貫したサポートを提供しています。
まずはお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/