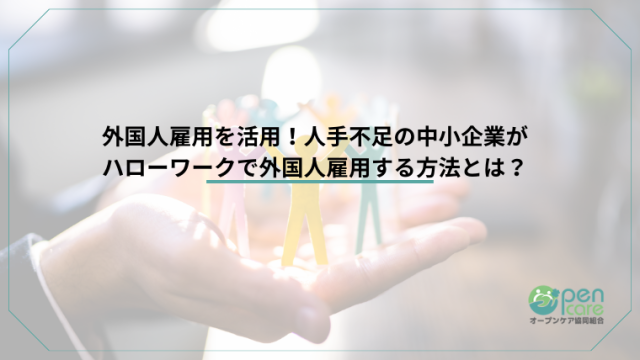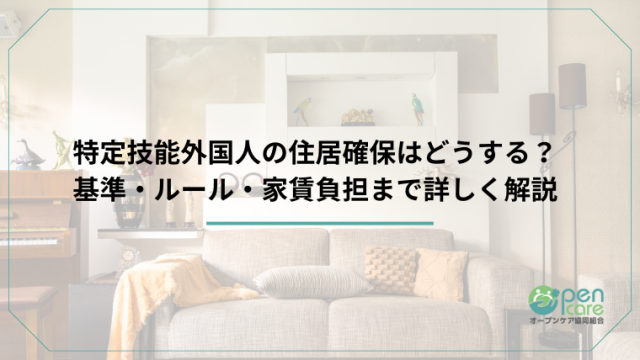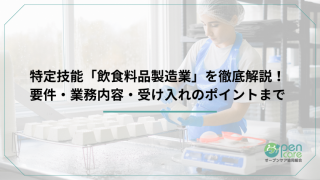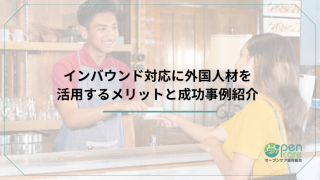訪日観光客の増加により、宿泊・外食業界ではインバウンド対応のための人材確保が急務となっています。そこで注目されているのが、外国人材を雇用できる「特定技能制度」です。
本記事では、インバウンドと特定技能の関係性に焦点を当て、対応可能な業種や導入時のポイントを詳しく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
なぜ今、インバウンド対応で特定技能が注目されているのか

観光・サービス業における深刻な人手不足
訪日観光客の増加に伴い、観光・サービス業の人手不足がますます深刻化しています。特に地方の宿泊施設や飲食店では、以下のような課題が浮き彫りになっています。
- 若年層の採用難と離職率の高さ
- 繁忙期に対応できる人材の確保困難
- 外国語対応可能なスタッフの不足
これらの課題により、サービス品質の維持や顧客対応のスピードに支障が出るケースも少なくありません。
外国人雇用ニーズの高まりと制度の登場背景
こうした背景を受けて、即戦力としての外国人材への期待が高まり、「特定技能」制度が注目されるようになりました。従来の技能実習制度ではカバーしきれなかった労働力不足に対し、労働者としての就労を認める特定技能制度は、企業の実務ニーズにマッチした制度として位置づけられています。
インバウンド需要と特定技能制度の接点とは
特定技能制度の対象職種には、宿泊業・外食業など訪日外国人と直接接する業務が含まれています。インバウンド需要と親和性の高いこれらの業種で、語学力や接客スキルを持つ外国人材が即戦力となる点が、制度活用の大きなメリットです。
さらに、異文化理解に長けた外国人材の存在は、多様な価値観を受け入れる観光地の魅力向上にもつながる要素となっています。
宿泊・外食業界の現場で起きている変化
特定技能制度の活用が進む中、宿泊・外食業界の現場では以下のような変化が見られます。
- 客室清掃やホール業務を担う外国人スタッフの増加
- 外国語対応を前提としたマニュアルの整備
- 社内研修の多言語対応化・文化理解プログラムの導入
こうした取り組みにより、企業はサービス品質を維持しながら、インバウンド対応力を高めています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能で活用できる業種とは?インバウンドと関係の深い分野に注目
宿泊業:接客・客室整備で活躍する外国人材
宿泊業は、特定技能制度の対象分野として明確に定められており、訪日外国人との接点が最も多い業種の一つです。外国人材は以下のような業務で活躍しています。
- フロントでの受付やチェックイン対応
- 客室の清掃・ベッドメイキング
- レストランでの接客や案内
特に、外国語対応が求められる場面では、その語学力と異文化理解が大きな強みとなり、宿泊客からの高い評価につながっています。
宿泊分野については「特定技能の宿泊分野とは?外国人材の宿泊業務での受入れ方法と人材採用の要件解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
外食業:厨房・接客の即戦力として期待
外食業界も特定技能制度の主要対象業種であり、都市部を中心に外国人材のニーズが急速に高まっています。実際の現場では、以下のようなポジションで活躍が見られます。
- キッチンでの調理補助、仕込み作業
- ホールスタッフとしての配膳や注文対応
- 多言語でのメニュー説明や案内
訪日外国人にスムーズかつ快適な飲食体験を提供するために、外国人スタッフの存在が欠かせない要素となりつつあります。
その他関連分野(ビルクリーニング・飲食料品製造)
インバウンド需要に直接関係するわけではありませんが、間接的に支える重要な業種として「ビルクリーニング」や「飲食料品製造」分野も注目されています。
- ビルクリーニングでは、ホテルや商業施設の衛生管理を担う人材が活躍
- 飲食料品製造では、観光地で消費される食品の製造工程を支える存在に
これらの業種も、訪日客に提供されるサービスや商品を支える「裏方」として、インバウンド需要と密接な関係を持っています。
飲食料品製造分野については「特定技能「飲食料品製造業」を徹底解説!要件・業務内容・受け入れのポイントまで」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
業種ごとの業務内容と就労範囲の違い
特定技能制度では、業種ごとに就労可能な業務範囲が定められています。宿泊業では、フロント業務や客室整備、館内案内などの接客全般が含まれます。外食業では、厨房での調理補助やホールでの接客・配膳などが対象で、アルコール提供も可能です。
ビルクリーニング業では、商業施設や宿泊施設における清掃・衛生管理が中心で、裏方業務が多くなります。飲食料品製造業では、観光地向け食品の製造・包装・品質管理など、工場内作業が主な業務です。
こうした業務範囲を正しく理解することは、適切な職務設計と定着率向上に不可欠です。業務と制度要件が合致しない場合、トラブルや離職リスクにもつながるため、事前の確認と準備が重要です。
特定技能人材がインバウンド対応に向いている理由
語学力・多文化理解などのコミュニケーション力
特定技能人材の多くは、日本語能力評価(JLPT N4相当以上)をクリアしており、日常会話レベルの日本語で接客や業務を行うことが可能です。さらに、訪日外国人と文化的背景を共有しているケースも多く、多言語での案内やトラブル対応にも柔軟に対応できます。
異文化理解力を備えた人材が加わることで、日本人スタッフだけでは補いきれない「気づき」や「安心感」を提供できる点は、インバウンド対応において重要な強みとなります。
訪日外国人からの評価向上への貢献
外国人スタッフがフロントやレストランなどの第一線で対応することで、訪日客にとっては「言葉が通じる安心感」や「自国文化への理解」を感じやすくなります。これは、サービス満足度の向上や口コミ評価の改善にも直結します。
特にSNSやレビューサイトでの評価が重視される昨今、外国人スタッフの存在がプラスのブランドイメージを構築する要素として機能しています。
即戦力としてのスキルと専門性
特定技能人材は、試験に合格した者や技能実習から移行した経験者が多く、一定の実務スキルを備えています。厨房業務での包丁使いや盛り付け、客室整備における清掃基準の理解など、現場で即戦力として活躍できる点が評価されています。
未経験者を一から教育する必要が少なく、戦力化までの時間が短いのも大きなメリットです。
定着支援と職場の共生文化の重要性
優秀な人材を確保しても、職場に馴染めなければ長期的な活躍は望めません。言語・生活支援はもちろん、職場内での文化的な違いを理解しあえる環境づくりが不可欠です。
特定技能制度では、登録支援機関による生活支援や相談体制が義務付けられており、これが職場定着にプラスに働いています。企業側も、外国人材を一時的な補填ではなく「共に働く仲間」として迎え入れる姿勢が、長期的な成果に結びついていきます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
導入を成功させるために企業が押さえるべき3つの条件

受け入れ体制と支援計画の整備
特定技能人材を受け入れる企業には、就労環境や生活環境を整備する責任があります。例えば、労働時間や休日の管理、日本人スタッフとの連携体制、ハラスメント防止の取り組みなどが求められます。
加えて、住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の支援なども重要です。これらは単なる福利厚生ではなく、定着率を左右する経営戦略の一部として捉える必要があります。
- 労働条件の明確化と説明
- 社内研修やマニュアルの多言語化
- 日常生活支援(銀行口座開設、役所手続きなど)
登録支援機関との連携と役割分担
特定技能の1号人材を雇用する場合、多くの企業は登録支援機関と連携して支援業務を委託しています。支援計画の立案から、生活相談、定期的な面談までを担う登録支援機関は、企業と外国人材の橋渡し役です。
企業がすべてを内製化するのではなく、外部の専門機関と上手に役割を分担することで、負担を軽減しつつ制度遵守を実現できます。
- 支援業務の外部委託による効率化
- 定期的なモニタリングや報告体制の構築
- 外国人材とのコミュニケーション窓口としての活用
就労ビザ・在留資格申請の手続き理解
特定技能人材の雇用に際しては、「在留資格:特定技能1号」の取得が必須です。出入国在留管理庁への申請手続きや必要書類の準備、申請後のフォローアップなどを正確に行うことが、スムーズな採用の鍵となります。
また、更新時の基準や2号への移行可否など、制度の変化にも注意を払う必要があります。専門家の支援を活用することも、確実な運用には有効です。
インバウンド対応強化には特定技能制度の活用を
訪日観光客の増加により、宿泊業・外食業などの現場では、外国人対応力と人手の両面が問われる時代になっています。こうした背景を受けて、「特定技能」制度は、即戦力となる外国人材を安定的に確保できる選択肢として注目されています。
語学力や多文化理解を備えた人材が、接客やサービス現場に柔軟に対応し、訪日外国人からの評価向上にも寄与します。また、登録支援機関との連携や支援体制の整備によって、企業としての受け入れ負担も軽減され、制度の活用がより現実的なものとなっています。
今後のインバウンド需要を見据え、自社の成長と競争力を高めるためにも、特定技能制度の積極的な導入は大きな武器となるでしょう。導入にあたっての不安や疑問がある場合は、制度に精通した支援機関への相談をおすすめします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/