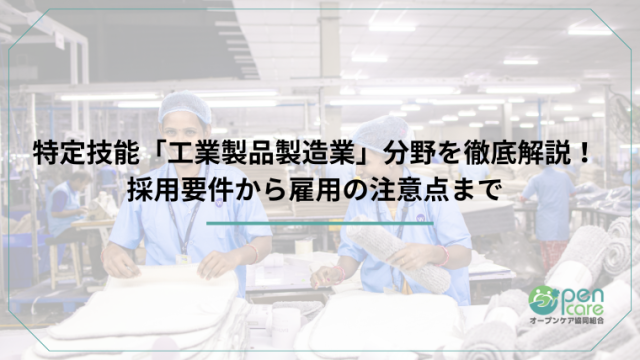特定技能外国人を受け入れる際、企業には「義務的支援」と呼ばれる10項目の支援を確実に実施することが求められます。しかし、その具体的な内容や実施方法について十分に理解できていない企業も少なくありません。本記事では、義務的支援の目的や各項目の内容、実施方法、違反時のリスクまでをわかりやすく整理し、企業として何をすべきかを明確にします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度における義務的支援の基本とは?
義務的支援の定義とその背景
特定技能制度における「義務的支援」とは、特定技能1号の外国人材が安心して日本で働き生活できるようにするため、受け入れ企業または登録支援機関が提供すべき支援内容を指します。これらは出入国在留管理庁により明文化されており、受け入れ機関が制度上果たすべき最低限の責務です。
この制度は、技能実習制度とは異なり「即戦力の労働者としての受け入れ」が前提であるため、雇用契約に基づく労働者としての権利保障が重視されています。そのため、生活面でのサポートや日本語学習、トラブル時の相談対応など、包括的な支援体制が求められています。
制度の背景には、外国人が言語や生活環境の壁によって孤立し、早期離職やトラブルにつながることを防ぐという目的があります。
なぜ企業に支援が求められるのか
外国人が日本で安心して働くためには、単に雇用するだけでなく、生活・社会面での支援が不可欠です。特に来日直後は、日本の行政手続きや医療制度、地域ルールなどに不慣れな場合が多く、これを放置すれば生活に支障をきたし、業務にも影響が及ぶリスクがあります。
企業側が支援責任を果たすことで、外国人労働者の定着率が向上し、結果的に企業の人材確保と育成の安定にもつながります。義務的支援は単なる「制度上の義務」ではなく、「企業の実利」としても重要なのです。
任意的支援との違いとは?
義務的支援は、制度上必ず実施しなければならない10項目に定められており、怠ると入管手続きや受け入れ継続に重大な影響を及ぼします。一方、任意的支援は企業の裁量で提供できる追加的サポートを指し、例えばレクリエーション活動の提供や、母国語を使った生活案内などが該当します。
義務的支援は法的な義務であるのに対し、任意的支援は企業の姿勢や支援体制の充実度を示す取り組みと位置づけられます。
在留資格と支援の関係
義務的支援の実施は、特定技能外国人の在留資格審査や更新に直結します。支援が不十分、あるいは虚偽報告がある場合、在留資格の取り消しや、企業への受け入れ制限措置が取られるケースもあります。
特定技能外国人の在留資格「特定技能1号」は、最大5年間の就労が可能な制度です。しかし、その間も適切な支援の継続が前提とされており、支援体制が不十分な企業は受け入れ機関としての適格性を欠くと判断され、在留資格の更新や再申請が認められない、あるいは受入れ停止の行政指導を受ける可能性があります。
特定技能の在留期間については「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能の義務的支援10項目の内容と目的【2025年版】

特定技能制度において企業が実施すべき義務的支援は、法務省出入国在留管理庁が定める10項目です。これらは外国人労働者が日本で適正に働き、安定した生活を送るために不可欠な内容です。以下、それぞれの支援項目について具体的な内容とその目的を解説します。
事前ガイダンスの提供
特定技能外国人が来日前に制度の概要や日本での就労・生活ルールについて理解できるよう、対面またはテレビ会議等でガイダンスを実施することが義務づけられています。
このガイダンスには、労働条件、業務内容、入国後の支援内容などが含まれ、外国人本人の理解促進とトラブル防止が目的です。
入出国時の送迎対応
空港や港湾などへの到着・出発時における送迎対応も義務的支援に含まれます。特に初来日の外国人にとっては、日本の公共交通機関の利用が困難である場合も多く、送迎対応は安心して生活をスタートさせるための基本です。
送迎対応は安全確保の面でも重要な役割を果たします。
住居の確保と生活支援
企業は、外国人が入国後すぐに生活できるよう、住居の確保と必要な生活環境の整備を行う義務があります。これは在留資格審査における重要要素の一つです。
- 住居物件の契約支援(保証人代行含む)
- ライフライン(電気・ガス・水道・Wi-Fiなど)の契約サポート
- 家具・家電(冷蔵庫・洗濯機など)の手配
- ごみ出しや地域ルールの説明
こうした支援を通じて、外国人が不安なく生活を始められる体制が求められます。
生活オリエンテーションの実施
入国後、地域生活に必要な基礎知識を伝える「生活オリエンテーション」を実施する必要があります。内容としては、交通ルール、防災対策、医療機関の利用方法、緊急連絡先などがあり、自治体が発行する多言語資料の活用も効果的です。
この支援により、生活トラブルの予防と自立支援が促進されます。
行政手続き等の同行
入居や在留に関連する各種行政手続きには、支援担当者の同行が求められます。主な手続きには以下があります。
- 住民票の登録
- 健康保険・年金の加入
- 銀行口座の開設
同行することで、手続きの確実性が増し、言語面での不安も解消できます。
日本語学習の支援体制
外国人が職場や地域で円滑にコミュニケーションを取れるよう、日本語学習の機会を提供する必要があります。方法はオンライン学習、自治体主催の日本語教室紹介、Eラーニングの利用などがあります。
この支援は、長期的な定着とキャリア形成にも寄与します。
相談・苦情への対応窓口
就労・生活に関する悩みやトラブルに対して、外国人が相談できる体制を整えることも義務です。対応者は外国人の言語や文化への理解があることが望ましく、速やかな対応体制が必要です。
対応体制を整えておくことはトラブルの早期発見と関係悪化の予防につながります。
地域住民との交流促進支援
外国人の孤立を防ぎ、地域社会との共生を促進する目的で、交流支援も必要です。
- 地域イベントや自治会活動の案内
- 近隣住民との顔合わせの機会づくり
- 地域防犯・防災訓練への参加支援
この支援により、受け入れ地域との信頼関係構築が可能になります。
転職支援(人員整理等の場合)
やむを得ず契約を解除する場合、外国人がスムーズに次の就職先を見つけられるよう、支援する義務があります。ただし、自己都合退職など一部のケースは対象外です。
求人情報の提供や、ハローワークへの同行などが含まれます。
定期的な面談と記録報告
特定技能外国人の勤務状況や生活状態について、定期的な面談を行い、支援実施記録を文書で残すことが義務付けられています。これらの記録は入管への報告資料としても使用され、支援の実効性を裏付ける重要な証拠となります。
特定技能の支援計画作成と実施プロセスの流れ

特定技能外国人を受け入れる企業は、義務的支援10項目を実施するために「支援計画」を事前に作成し、実際の運用に落とし込む必要があります。この計画は単なる書類作成ではなく、制度上の重要な要件として入管への提出義務もあるため、慎重な準備と運用が求められます。ここでは、支援計画の作成から運用までの基本ステップを解説します。
支援対象者と内容の明確化
まず、支援計画の対象となる特定技能外国人の氏名、国籍、在留資格、所属職種などを明確に記載します。その上で、義務的支援の10項目すべてについて、どのような方法で、どのタイミングで、誰が担当するかを整理する必要があります。
この段階で明確にしておくことで、実施段階でのトラブル防止につながります。
実施スケジュールと体制の構築
支援内容ごとに、入国前・入国直後・定期的実施など、実施時期をスケジューリングします。
たとえば
- 事前ガイダンス:入国の2週間前までにオンラインで実施
- 入出国の送迎:到着当日のフライトに合わせた送迎体制の手配
- 日本語支援:月1回の進捗確認と教材提供の定期見直し
加えて、支援実施担当者の氏名や連絡先を明記し、社内での支援チーム体制を構築しておくことが望ましいです。
実施状況の記録と報告
実施した支援内容は、その都度「支援実施記録」として文書化し、必要に応じて入管に報告できるよう保管しておく必要があります。特に、生活オリエンテーションの出席記録や、面談内容のメモなど在留資格の更新時や監査の際に提出を求められる可能性があるため、正確かつ漏れのない形で保管しておくことが重要です。。
形式としては、チェックリスト方式や写真付き記録などが実務上有効です。
支援委託(登録支援機関)を利用する場合
企業が自ら支援を実施できない場合、登録支援機関に業務を委託することが可能です。委託時にも企業は「支援実施の適切性を確認する責任」を負うため、報告書の提出や月次報告を求めるなど、管理体制の整備が重要です。
また、委託する場合でも支援計画の作成・提出は企業の責任であることを理解しておく必要があります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能の義務的支援を怠った場合のリスクと罰則
特定技能制度において、義務的支援を適切に実施しないことは、受け入れ企業や登録支援機関にとって重大なリスクとなります。ここでは、支援不備によってどのような不利益が生じるのか、具体的な行政処分や制度上の制限について詳しく解説します。
在留資格更新・延長の拒否
最も直接的なリスクは、支援が不十分であると判断された場合に、外国人本人の「特定技能1号」の在留資格更新や延長が認められなくなることです。在留期間は原則1年ごとに更新されますが、その都度「適正な支援が行われているか」が審査対象になります。
仮に支援記録が曖昧であったり、報告義務を怠った場合には、更新が却下され、外国人が帰国を余儀なくされる可能性もあるため、企業にとっても深刻な影響があります。
受け入れ停止・登録支援機関の登録取り消し
支援不備が組織的または継続的に認められた場合、法務省・出入国在留管理庁は企業に対して「受け入れ制限」や「受け入れ停止命令」を発出することがあります。さらに、登録支援機関においては登録そのものが取り消される場合もあります。
一度取り消されると、再登録には時間と手間がかかり、当面の受け入れが不可能になるリスクがあります。
信用低下・取引先への影響
支援義務違反による行政処分は、法務省のホームページ上で公表される場合があります。これにより、企業の社会的信用が損なわれ、取引先からの信頼低下や採用活動への悪影響が広がることが懸念されます。
特に地域密着型の中小企業においては、企業イメージの低下が人材確保の妨げとなるため、見過ごせない問題です。
外国人従業員との信頼関係の崩壊
義務的支援が不十分な場合、外国人従業員との信頼関係も破綻しやすくなります。生活上の不安が解消されなければ、早期離職やトラブルに発展するリスクが高まり、最悪の場合は労働紛争や訴訟に発展することもあります。
支援の質は、定着率や生産性にも直結するため、単なる形式的な対応ではなく、実態として機能しているかが重要です。
成功事例に学ぶ!義務的支援の実践ポイント
義務的支援を形式的に実施するだけでは、特定技能外国人の定着や戦力化にはつながりません。実際に支援を成果につなげている企業には、共通した工夫や仕組みがあります。ここでは、建設・外食・宿泊など各業種の中小企業が行っている実践的な成功事例から、再現性の高いポイントを整理します。
支援担当者の明確化と社内連携の徹底
ある宿泊業の企業では、外国人支援を「総務部」単独で行うのではなく、配属先部門とも密に連携を取りながら対応しています。具体的には、配属現場の上司も支援計画を理解し、通勤・生活・メンタル面のフォローを日常的に行っています。
また、支援担当者を明確にし、「日本語での定期面談を月1回実施」「日誌で実施記録を共有」する体制を築くことで、支援の質と継続性が保たれています。
入国前からの双方向コミュニケーション
外食業で成功しているある企業では、入国前にZoomで3回のオンライン面談を実施し、日本での勤務や生活に関する説明と質疑応答の時間を設けています。これにより、外国人本人の不安を減らし、入国後のギャップを最小限に抑えることができています。
企業側も、事前に性格や日本語能力、対応力を把握できるため、マッチングの精度向上にもつながっています。
任意的支援との組み合わせで定着率向上
義務的支援に加え、「休日の地域イベントへの参加支援」「自転車の貸与」「日本語学習アプリの補助」など、任意的支援を積極的に取り入れる企業も増えています。特に、生活基盤の整備やメンタルケアを重視する企業ほど、離職率の低下や職場への早期適応が見られます。
こうした支援は、社内の雰囲気向上や日本人社員の外国人への理解促進にも寄与しています。
外部パートナーの有効活用
登録支援機関との連携を強化している建設業の中小企業では、支援計画作成や書類提出などを専門機関に委託しつつ、月1回の定例報告会を開催し、現場での様子を共有しています。これにより、委託型であっても「丸投げ」でなく、企業としての関与と管理責任をしっかり果たしています。
また、日本語教育や住居確保については、自治体や地域NPOとも連携しており、地域ぐるみの受け入れ体制が整っています。
※これらの事例は、実際の状況を参考にした想定事例となっています。
このような成功事例に共通しているのは、「外国人を一人の社員として尊重する姿勢」と「支援を制度対応で終わらせない工夫」です。
まとめ
特定技能制度における義務的支援は、単なる制度上の要件ではなく、外国人材の安定雇用と職場定着を実現するための重要な取り組みです。本記事では、企業が実施すべき10項目の支援内容とその意義、違反時のリスク、そして成功事例に基づく実践ポイントまでを網羅的に解説しました。
義務的支援は、「制度だから仕方なくやるもの」ではなく、外国人材の不安を解消し、能力を最大限発揮してもらうための土台作りです。支援を正しく行うことは、結果的に企業の人材戦略の強化にもつながります。
オープンケア協同組合では、こうした義務的支援に関するご相談やサポート体制も整えています。「何から始めれば良いかわからない」「登録支援機関の選び方に悩んでいる」といった企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/