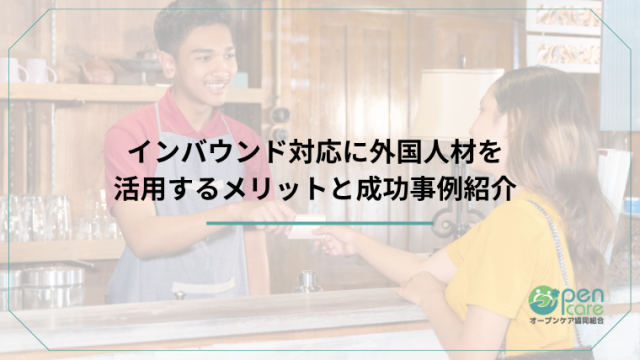人手不足に悩む企業にとって、特定技能外国人の受け入れは現実的な選択肢のひとつです。本記事では、特定技能制度における受け入れ人数の最新データを国別・職種別に紹介し、自社で採用を検討するうえでの判断材料をご提供します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
最新データで見る特定技能外国人の受け入れ状況(2024年6月時点)
特定技能全体の在留人数の推移
特定技能制度は2019年に創設されて以降、年々在留外国人数が増加しています。特に直近1〜2年の伸びは著しく、2023年末時点では20万人を超えていたところ、2024年6月末時点では約24万人に到達したことが発表されました。この増加は、技能実習制度からの移行や、受け入れ分野の拡大による需要増が背景にあります。
また、在留資格「特定技能」は1号と2号に分かれており、現時点ではその大半が1号に集中している状況です。技能実習に代わる実践的な雇用制度として、企業側の理解が進んできた結果といえるでしょう。
特定技能1号・2号の割合と増加傾向
現在、在留している特定技能外国人のうち、およそ97%が「特定技能1号」、残りが2号となっています。特定技能2号は熟練技能を要する職種に限定され、取得のハードルが高いため、今のところ限定的な運用にとどまっています。
以下の点が増加要因として挙げられます
- 外国人材側にとって「技能実習より自由度が高い」
- 企業側にとって「即戦力かつ制度的に安定した人材確保が可能」
- 一部業種では特定技能に人材確保をシフトしている
このような背景から、2024年は前年よりも1.2〜1.3倍の増加ペースで推移しています。
法務省・出入国在留管理庁の公式データ紹介
特定技能の最新在留人数に関するデータは、主に法務省 出入国在留管理庁が定期的に公表しており、以下のような形式で発表されています。
|
年月 |
在留者数(人) |
増減(対前年) |
主な増加要因 |
|
2023年6月末 |
約20万人 |
– |
技能実習→特定技能への移行増加 |
|
2024年6月末 |
約24万人 |
+4万人 |
外食・建設・介護業種の拡大、規制緩和 |
出入国在留管理庁の公式ページでは、国別・分野別・都道府県別の在留者数データも確認できるため、受け入れ検討企業にとっては判断材料となります。
このように、制度開始から5年が経過し、制度としての安定性と信頼性が増してきたことが、人数増加を後押ししているといえるでしょう。
なお、最新の在留人数や分野別・国別の詳細なデータを知りたい場合は、制度に精通した支援機関に直接相談するのが確実です。
オープンケア協同組合では、最新統計に基づいた受け入れアドバイスも行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
職種別の受け入れ実績とその特徴
外食業分野の受け入れ状況と課題
外食業は、特定技能の中でも最も受け入れが活発な分野のひとつです。厨房補助、盛り付け、洗浄業務など、マニュアル化された作業が中心であり、一定の日本語能力があれば即戦力として働きやすいという利点があります。
一方で、接客や顧客対応といった言語的負担の高い業務があるため、日本語能力の確認や教育体制が必要不可欠です。業務内容の幅が広い分、職場ごとの柔軟なマッチングが求められます。
介護分野における特定技能活用の動向
介護分野は人材不足が特に深刻な領域であり、特定技能外国人の導入が着実に進んでいます。2024年現在では、外食業に次ぐ受け入れ人数を記録しており、今後も拡大が期待されています。
以下のような特徴があります
- 日本語能力試験(N4以上)と介護技能評価試験の合格が必要
- 利用者とのコミュニケーションが求められるため、人柄や適応力の確認が重要
- 特定技能から介護福祉士資格を目指すルートもあり、長期雇用にもつながる
現場では定着率が高く、教育と支援体制の整った施設では即戦力化しやすい分野です。
介護分野については「介護分野における特定技能外国人の受け入れ要件とメリット解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
建設業は枠管理あり?制度上の留意点
建設業は他の職種と異なり、「受け入れ枠管理制度」の対象となっています。業界団体の管理下で、適正な範囲内での受け入れが実施されている点が特徴です。
建設業で特定技能を受け入れる際のポイントには以下があります
- 対象職種は「型枠施工」「鉄筋」「塗装」など10職種に限定
- JAC(建設技能人材機構)の監理下で人数枠を管理
- 雇用契約だけでなく「就業計画」の提出や実施も必須
制度上の制約が多いため、事前準備と制度理解が特に重要な分野といえます。
建設分野については「特定技能の建設分野とは?建設業で外国人材の受け入れ方法と注意点を徹底解説!」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
製造・食品加工分野の現場ニーズ
製造業、とくに食品加工分野では、ライン作業や品質管理の現場において外国人材の導入が進んでいます。作業内容が定型的で、日本語のやり取りが少ない職場環境が多いため、導入ハードルは比較的低めです。
多くの企業では以下のような取り組みを行っています
- 作業工程を図解したマニュアルの整備
- 寮・通勤送迎などの生活支援体制の構築
- 現場責任者が外国人対応に関する研修を受講
このような支援体制があることで、外国人材が安心して働きやすい職場環境が整いやすい点が評価されています。
飲食料品製造分野については「特定技能「飲食料品製造業」を徹底解説!要件・業務内容・受け入れのポイントまで」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
清掃・宿泊業などサービス系の特徴
宿泊業やビルクリーニングなどのサービス分野では、外国人材が担う役割が年々拡大しています。特に清掃やベッドメイキングなどの裏方業務においては、日本語力に不安があっても活躍できる場面が多く、多国籍な人材を受け入れやすい分野といえます。
また、観光地では外国人観光客への対応強化を目的として、フロントや飲食部門で多言語対応ができる人材の採用が進んでいます。ただし、受け入れが都市部や観光エリアに偏る傾向があるため、地域による採用難易度の差には注意が必要です。
宿泊分野については「特定技能の宿泊分野とは?外国人材の宿泊業務での受入れ方法と人材採用の要件解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
国別の特定技能在留者数とその背景
ベトナム:全体の約6割を占める主要国
特定技能制度の受け入れ国として最も大きなシェアを占めているのがベトナムです。2024年6月時点では、全体の約6割がベトナム出身者で構成されており、これは技能実習制度時代からの蓄積と関係があります。
ベトナム人材は、技術系・サービス系問わず幅広い分野で活躍しており、日本語教育機関や送り出し機関の体制が整っていることも選ばれる理由のひとつです。特に製造業や外食業では、現場適応力が高いと評価されています。
インドネシア:日本語能力と定着率の高さ
インドネシアは、特定技能人材の中でも日本語能力が比較的高く、宗教的・文化的な順応性が高い国として知られています。介護・清掃分野での活躍が目立ち、長期就労を希望する傾向も強いことから、企業側からの信頼も厚くなっています。
以下のような理由から、インドネシア人材は評価されています
- 日本語教育が義務教育に組み込まれている地域もあり、初期会話レベルの習得が早い
- 宗教的習慣(ハラール対応等)を尊重すれば、人間関係の構築がスムーズ
- オープンケア協同組合のように、現地連携のある支援機関が多数存在
特に中小企業にとっては、高い定着率と円滑なコミュニケーションが大きな魅力です。
フィリピン・ネパール:伸びが顕著な新興国
フィリピンやネパールは、近年急速に在留人数が伸びている国です。どちらも人口が若く、国外就労に前向きな国民性を持ち、一定の教育水準と就労意欲の高さを背景に受け入れが進んでいます。
特にフィリピンは英語教育が進んでいるため、観光・接客系職種での活躍が見込まれます。一方ネパールは技能実習での実績を積み上げており、外食・清掃分野での定着が進んでいます。
今後、送り出し体制の強化が進めば、主要国に次ぐ存在として台頭する可能性があります。
ミャンマー・タイ:特定分野に偏りある採用傾向
ミャンマーやタイ出身の特定技能人材は、分野に偏りがある点が特徴です。ミャンマーでは建設業に、タイでは食品加工・外食業への受け入れが目立ちます。これは、技能実習制度の送り出し実績や、業界ごとのパートナーシップに由来しています。特徴は以下の通りです。
- ミャンマーは技能実習の実績が豊富な一方、政情不安により送り出し数に変動があり
- タイは農業・食品加工系に特化した送り出しが多く、安定した技術習得力が評価されている
- どちらの国も現地教育機関との提携次第で採用数が大きく変化する
そのため、これらの国からの受け入れを検討する企業は、送り出し実績と送り出し機関の質の見極めが重要です。
国籍別に見る文化・言語・適応性の違い
国ごとに文化や宗教、言語背景が異なるため、就業後の適応にも差が出る傾向があります。たとえば、宗教的な制約(食事や祈りの時間など)、敬語の習得難易度、職場での協調性などは、国籍別の傾向を把握しておくことで、採用後のトラブルを未然に防ぐことができます。
企業側に求められる配慮の例としては
- ハラール食や礼拝スペースの整備(インドネシア・バングラデシュ等)
- 寮や食事環境の整備(ネパール・ミャンマーなど郊外型)
- 日本語教育支援と社内OJT体制の明文化
文化的多様性を尊重する職場づくりが、外国人材の定着率や満足度に直結するといえるでしょう。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
受け入れ人数の枠や制限はある?制度上の制限事項を整理
「上限がある分野」と「制限のない分野」
特定技能制度では、分野ごとに受け入れ人数の枠設定に違いがあります。一部の分野には国が定めた人数制限(目安)が設けられている一方で、制限のない分野も存在します。
上限がある主な分野は建設、造船、自動車整備などで、制度創設時から計画的に人材を確保する目的で制限が設定されています。一方、外食業や介護、農業といった分野は基本的に人数の上限はなく、企業の採用意欲次第で柔軟な受け入れが可能です。
こうした差異を理解していないと、「制度上は採れると思っていたのに実際には不可だった」という事態にもつながるため、事前確認が欠かせません。
建設・介護など特定分野の制限枠とは
建設と介護は制度上、特に注意が必要な分野です。いずれも業界特有の事情により、受け入れ枠や条件が他分野よりも厳格に設定されています。
- 建設分野では、JAC(建設技能人材機構)による枠管理が行われ、職種・企業規模ごとに受け入れ可能人数が定められている
- 介護分野は、日本語能力(N4以上)に加え、介護技能評価試験の合格が必須条件とされている
- どちらの分野も、受け入れ後のフォロー体制や職場環境の整備が義務づけられており、制度理解が極めて重要
こうした要件を満たさなければ、申請の段階で不認可となる可能性もあるため、事前に十分な準備と確認が必要です。
受け入れ人数の設定に影響する制度要件
制度上に明確な「上限」がない分野であっても、企業の体制や環境によっては、実質的に受け入れ可能な人数が制限される場合があります。たとえば、登録支援機関を通じた生活支援が不十分である場合や、日本人従業員とのバランスが適切でない場合、審査が通りにくくなることがあります。
特に社内における支援担当者の人員体制や、外国人材向けの教育環境の整備状況は審査で重視される傾向にあります。制度自体は柔軟でも、現場での運用体制によって採用実現の可否が左右されるのが実情です。
制度改正時の注意点と情報収集の重要性
特定技能制度は、まだ制度運用から5年に満たない比較的新しい制度であり、定期的な改正や運用ルールの変更が行われています。特に2024年度には、結核スクリーニングや深夜労働の要件強化など、新たな基準が追加されています。
以下のような情報に日々目を通すことが重要です。
- 出入国在留管理庁による最新通知や統計資料
- 分野別の制度運用要領や改正概要
- 支援機関・監理団体からのガイドラインや注意喚起
こうした情報を正確にキャッチアップできていないと、最新基準を満たしていないまま申請を進めてしまい、不認可やトラブルに繋がる恐れがあります。継続的な情報収集こそが、制度活用の成功を左右します。
まとめ|分野別データから採用の可能性を見極めよう
特定技能制度による外国人材の受け入れは、外食・介護・建設といった業種に集中しており、ベトナムやインドネシアなどの国籍に偏る傾向があります。実績の多い分野や国籍を把握すれば、自社に適した人材の見極めがしやすくなります。
一方で、業種によっては人数枠の制限や受け入れ条件があり、事前確認が不可欠です。制度を正しく理解し、自社が採用可能かどうかを見極めることが採用成功への第一歩です。
特定技能は、即戦力となる人材を柔軟に受け入れられる実用性の高い制度です。
「うちの業種でも採用できる?」「どの国籍が自社に合っている?」といった具体的な疑問がある場合は、特定技能に精通した支援機関に早めの相談をすることで、制度の活用チャンスを逃さずに済みます。
オープンケア協同組合では、最新データをもとに導入可否の診断や具体的なステップのご提案も行っています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/