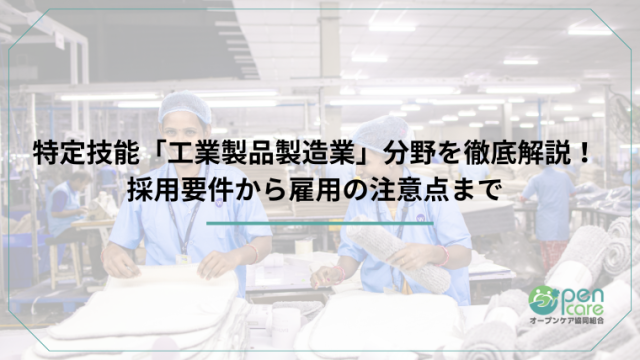造船業界では、熟練工の高齢化や若手不足による人手不足が深刻化しています。本記事では、外国人材を即戦力として採用できる「特定技能」制度の概要と、対象職種・試験内容・採用までの流れをわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
造船業における人手不足の現状とその背景
熟練工の高齢化と若手入職者の減少
造船業は長年にわたり熟練の技能者に支えられてきました。しかし近年では、これらのベテラン職人の多くが高齢化し、人手不足が進行しています。一方、若年層の入職者は減少傾向にあり、技術継承が困難になっているのが実情です。特に溶接や塗装などの工程は、経験による技能が品質に直結するため、技能継承の断絶が深刻な課題となっています。
若年層の離職要因としては、長時間労働や3K職場のイメージ、将来性の不透明さが挙げられます。こうした背景が、人材の確保と定着を一層困難にしているのです。
現場作業の専門性が求められる工程
造船業は単なる製造業ではなく、極めて高い専門性と精度を要求される分野です。船体の設計図に基づいてミリ単位の精密な加工を行い、長期間の耐久性を持つ構造物をつくるには、高度な知識と技能が必要です。
特に次のような工程においては、技能者の質が船の安全性・生産性に直結します。
- 溶接:船体構造を形成する最重要工程であり、強度と気密性の管理が不可欠
- 機械加工:モーター・エンジンなど船舶機器の部品精度を決定する
- 電装作業:電源供給・制御系統の正確な配線技術が求められる
- 塗装・防食処理:長期耐用を支える防錆対策としての役割が大きい
こうした工程に従事できる人材が圧倒的に不足しているため、現場では深刻な稼働率の低下が懸念されています。
中小企業ほど深刻な採用難の実態
大手造船企業と異なり、中小規模の事業者は知名度や労働環境面での訴求力に限界があるため、求人を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。さらに、賃金水準や福利厚生面でも大手との差が出やすく、若年人材の獲得競争で後手に回ってしまいがちです。
また、中小企業では人的リソースや採用ノウハウも限られており、ハローワークや求人媒体への掲載だけでは効果が見込めないことも多くあります。こうした背景から、即戦力の確保が難航しており、実際に「案件はあるが人手が足りないために受注を断念せざるを得ない」といった声も少なくありません。
外国人材採用への関心の高まり
このような構造的な人手不足を受け、造船業界では外国人材の受け入れに対する関心が急速に高まっています。特に「特定技能」制度が整備されたことで、従来の技能実習制度よりも実務性・即戦力性の高い人材が採用できるようになった点は、企業側にとって大きなメリットです。
関心が高まる主な要因は以下のとおりです。
- 外国人材は若年層が中心で、就労意欲が高い
- 特定技能制度は特定の職種に特化しており、業務マッチ度が高い
- 試験制度が整備されており、一定の技能・日本語能力が保証されている
- 制度上、長期間の雇用・定着が見込める(2号資格への移行含む)
こうした背景から、今後さらに「外国人材の制度活用」が現場の人手不足対策の有効な手段として期待されていくでしょう。
外国人雇用状況については「外国人雇用状況と黒字経営中小企業が直面する人手不足の解決策」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能「造船・船用工業」制度とは?
制度の概要と目的
特定技能制度は、深刻な人手不足が続く業種において、外国人が一定の技能・日本語能力を持って日本国内で働くことを可能にする在留資格制度です。2019年に導入され、対象となる分野のうちの1つが「造船・船用工業分野」となっています。
この制度の目的は、単なる労働力確保ではなく、「専門性ある技能を有する外国人材の即戦力化」にあります。造船分野の6職種において、一定の技能試験に合格した人材を企業が受け入れ、継続的な雇用につなげることが制度上想定されています。
外国人が日本企業で正規に働ける制度として、実務性・専門性の観点からも評価されており、受け入れ企業側にとっても即戦力確保の現実的な選択肢となりつつあります。
技能実習制度との違い
特定技能制度と混同されがちなのが、技能実習制度です。両者の目的と運用体制には明確な違いがあります。
- 特定技能は「人手不足解消」が目的で、労働力としての活用が前提
- 技能実習は「技能移転・国際貢献」が目的で、研修的な位置づけ
また、特定技能では日本語試験や技能試験が必要であり、就労分野ごとに定められた範囲内で業務を行うことができます。一方で、技能実習では現場配属の制限や管理体制の厳格さが求められ、受け入れの自由度が低い傾向にあります。
企業にとってのメリットは、特定技能の方が「業務への即応性が高い」「人材定着がしやすい」という点にあり、制度の設計意図そのものが異なる点を理解することが重要です。
対象となる業務区分(全6職種)
特定技能「造船・船用工業」分野では、以下の6職種に限り、外国人材の就労が認められています。
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
- 電装
- 機械加工
- 配管
これらは、造船の製造工程において中核をなす作業ばかりであり、それぞれが一定の実務経験や技能試験によって裏付けられた能力を要します。つまり、制度として定義された「特定技能1号」の対象である以上、雇用される外国人材は即戦力として現場に立てる人材であることが前提です。
受け入れ企業としては、自社の工程内容と対象職種の適合を事前に確認することが必要です。
在留資格1号と2号の違い
特定技能制度には「1号」と「2号」の2つの資格区分があります。現在、造船・船用工業分野では両方の取得が可能であり、長期的な雇用継続にも対応しやすい制度設計となっています。
|
区分 |
在留期間 |
家族帯同 |
主な要件 |
|
特定技能1号 |
最大5年(1年×更新) |
不可 |
技能試験+日本語試験に合格 |
|
特定技能2号 |
期間更新制(事実上無期限) |
可 |
熟練技能者として認定 |
特定技能1号で働きながら、一定の経験と追加試験を経ることで、2号資格への移行が可能になります。これにより、単なる短期労働力としてではなく、長期的な戦力としての登用も視野に入れることができます。
特定技能の在留期間については「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
試験内容とClassNKによる実施体制
技能評価試験の形式と出題範囲
特定技能「造船・船用工業」分野では、外国人労働者の採用にあたり、技能評価試験への合格が必須です。試験は「筆記(学科)」と「実技」の2部構成で行われ、それぞれの職種に応じた基準で技能の有無が判断されます。
対象の6職種ごとに、現場で必要とされる基本技能や安全知識、作業手順への理解が求められます。試験は業務内容に直結した実務的な設計であるため、合格者は即戦力としての活躍が期待されます。
受け入れ企業側は、必要とする職種に合致した試験の種類を事前に確認し、採用方針と照らし合わせることが重要です。
日本語試験の必要要件とレベル
特定技能制度では、日本語による基本的なコミュニケーション能力が求められます。造船・船用工業分野でも、技能評価試験に加えて日本語試験の合格が必須です。
対象となるのは「日本語能力試験(JLPT)N4」または「JFT-Basic」です。N4は初級レベルで、簡単な会話や文章の理解ができる水準とされます。JFT-Basicは特定技能向けの試験で、職場や日常生活でのやり取りに必要な力があるかを測定します。
これらの試験は国内外で実施されており、合格証の有効期限は5年です。在留資格申請時には証明書の提出が必要となるため、採用時点での確認が重要です。
日本語力が担保されていることで、現場での指示伝達が円滑になり、安全性や業務効率にも良い影響を与えます。
ClassNKとは何か?その信頼性と役割
ClassNK(一般財団法人日本海事協会)は、造船・船用機器分野における代表的な第三者検査機関です。技能評価試験の主管機関としても認定されており、国際基準に即した信頼性ある運営が行われています。
ClassNKの役割は以下の通りです。
- 技能評価試験の設計と監修
- 試験実施・管理(国内外対応)
- 合格結果の通知と証明書発行
- 受験情報や試験内容の公開・サポート対応
このように、第三者機関としての中立性と技術的な専門性を持ち、企業にとっても安心して人材採用に活用できる試験体制が整えられています。
最新の試験スケジュール確認方法
試験の日程や開催地は時期によって異なるため、採用計画を立てるには正確なスケジュール確認が欠かせません。
企業担当者が活用すべき主な情報源は次の通りです。
- ClassNKの公式サイト「技能評価試験」ページ
- 出入国在留管理庁の試験情報一覧
- 外国人材支援団体や監理団体からの案内
これらの情報を早めに収集しておくことで、適切なタイミングでの採用と在留資格申請が可能になります。特に海外試験の場合は申込から合格発表まで数ヶ月かかることもあるため、スケジュール管理が重要です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
採用に必要な4つのステップと注意点
受け入れ準備(協議会加入と体制整備)
外国人材の受け入れを開始するには、まず企業側が受け入れ体制を整える必要があります。具体的には、特定技能協議会への加入が義務付けられており、労働条件やサポート体制に関する書類の整備が求められます。
協議会は、外国人労働者の適切な就労環境を維持するための枠組みです。企業は協議会を通じて、支援計画や相談窓口の設置、生活ガイドラインの周知などを行います。
あわせて、外国人が生活しやすいよう、住居・通信環境・相談体制といった受け入れインフラの整備も欠かせません。法的要件を満たすだけでなく、実際に安心して働ける環境を提供することが定着率向上の鍵となります。
外国人材の募集とマッチング
採用活動は、募集先の選定から始まります。海外送出機関、監理団体、民間エージェントなどを通じて候補者を募るのが一般的です。候補者が特定技能の試験に合格しているか、必要な書類が揃っているかの確認も忘れてはなりません。
スムーズな採用のためには、次のようなマッチング方法が有効です。
- Zoomなどを活用したオンライン面談の実施
- 業務内容や条件のすり合わせ
- 日本語レベルや勤務意欲の確認
- 社内での受け入れ担当者との事前調整
面接段階での誤解や条件不一致を防ぐことで、採用後の定着率を高めることができます。
在留資格の申請と必要書類
内定者が決まった後は、「特定技能1号」の在留資格を取得するための申請手続きが必要です。申請は出入国在留管理庁に対して行われ、必要な書類は雇用契約書、支援計画書、協議会加入証明など多岐にわたります。
申請から許可までには1~2ヶ月ほどかかることもあるため、採用スケジュールに余裕をもたせることが重要です。また、不備があると差し戻される可能性があるため、各書類の正確性と整合性には十分注意が必要です。
書類作成や提出を代行してくれる支援団体の活用も、有効な手段のひとつです。
受け入れ後の生活・就労支援
外国人材が入国した後は、単に働かせるだけでなく、生活全般を支える支援が求められます。職場での業務指導とあわせて、日常生活や地域との関係づくりまでを含めた支援体制が定着の成否を分けます。
企業が担う主な支援内容は以下の通りです。
- 住居の確保と初期生活用品の手配
- 通信手段(スマートフォンやWi-Fi)の整備
- 日本語学習の支援や相談窓口の設置
- 交通機関や生活ルールの説明
これらのサポートをきちんと行うことで、外国人材が不安なく生活・就労でき、長期的な戦力として企業に貢献してくれる可能性が高まります。
外国人労働者の受け入れについては「外国人労働者を受け入れるメリット・デメリットを詳しく解説!採用方法と問題点も紹介」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
オープンケア協同組合を活用する3つのメリット
初期費用0円・月額2万円の低コストプラン
外国人材の受け入れにおいて、多くの企業が悩むのがコスト面です。登録支援機関やエージェントの利用には、数十万円の初期費用が発生するケースも少なくありません。その中で、オープンケア協同組合が提供する「初期費用0円・月額2万円」のプランは、業界内でも特筆すべき低価格です。
中小企業にとって、導入のハードルが下がるだけでなく、継続的な支援を安定して受けられるのが大きなメリットです。コストを抑えつつ、制度上必要な支援内容をすべて網羅しているため、初めて外国人を採用する企業でも安心して利用できます。
このような明瞭かつ低額な料金体系が、全国1000社以上の企業に選ばれている理由のひとつとなっています。
Zoom面談による事前マッチングの導入
採用後のミスマッチを防ぐには、採用前のマッチング精度が非常に重要です。オープンケア協同組合では、Zoomを活用した事前面談を標準化しており、候補者の人物像や日本語レベル、仕事への意欲を事前に確認することができます。
この仕組みによって、以下のような採用トラブルを未然に防ぐことが可能です。
- 実際に来日してみたらコミュニケーションが困難だった
- 求人条件と候補者の認識にギャップがあった
- 候補者の態度やモチベーションに不安があった
面接は企業側・候補者側どちらにとっても透明性が高く、互いの理解を深めたうえで採用判断ができるため、定着率の向上にも寄与しています。
住居・通信・教育などワンストップ支援体制
外国人材の受け入れには、就労環境だけでなく生活面のサポートも欠かせません。オープンケア協同組合では、入国後に必要となる生活インフラをワンストップで支援しています。
提供される主なサポート内容は以下の通りです。
- 住居の確保と契約手続きの代行
- ベッド・冷蔵庫・洗濯機などの生活用品の準備
- 携帯電話・Wi-Fiなど通信環境の整備
- 日本語教育や生活指導の実施
- 地域との共生に向けた適応トレーニング
このような包括的な支援があることで、企業の負担は大きく軽減され、採用後のトラブルも最小限に抑えられます。また、制度に則った運営体制が整っているため、法令順守面でも安心して任せることができます。
まとめ|造船業の採用課題を制度活用で乗り越える
造船業界では、熟練工の引退や若手不足により、深刻な人材難が続いています。中でも溶接や電装といった専門性の高い工程では、即戦力となる人材確保が深刻な課題です。こうした状況を打開する手段として、「特定技能」制度の活用は現実的かつ有効な選択肢となっています。
特定技能制度では、技能試験と日本語試験を通じて実力のある外国人材を見極めることができ、制度上も長期雇用への移行が可能です。さらに、ClassNKによる信頼性の高い評価体制や、協議会を通じた支援も整備されており、制度全体として安心して活用できる設計となっています。
とくに、オープンケア協同組合のような支援実績のある支援機関を活用すれば、コストを抑えながら受け入れ準備から生活支援までを一貫して任せることができます。制度を正しく理解し、信頼できるパートナーと連携することで、造船業における人材課題は着実に改善へと向かうはずです。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/