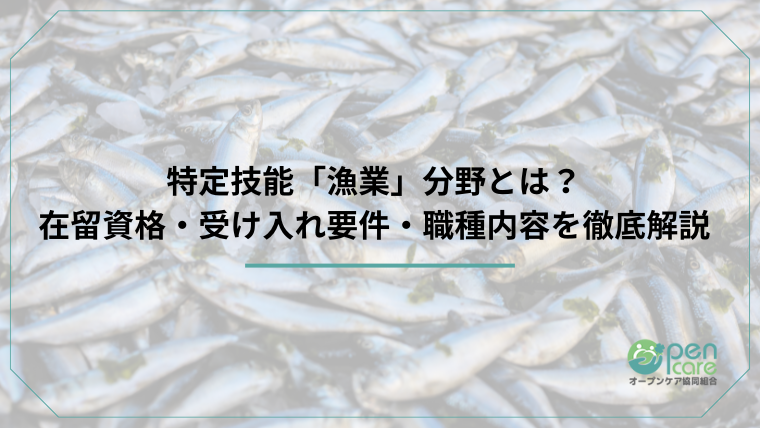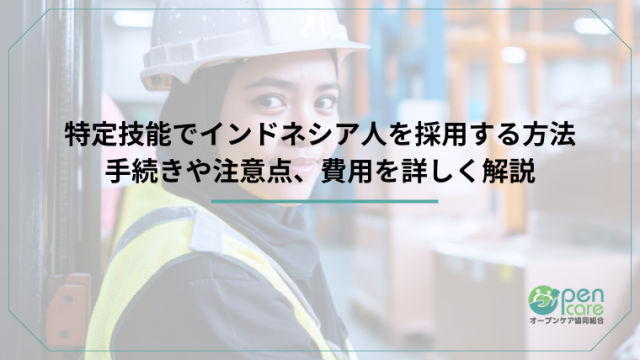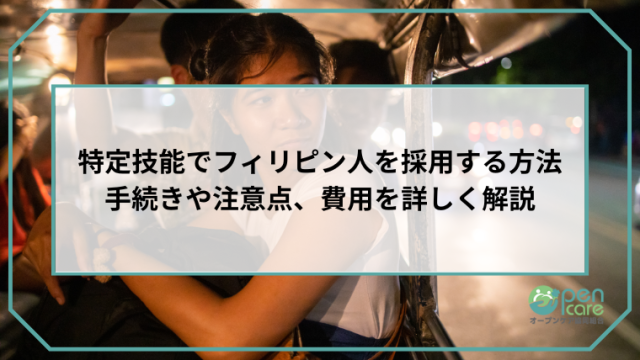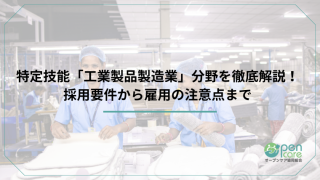日本の漁業分野では、従事者の高齢化や若年層の離職により、深刻な人手不足が続いています。そうした課題に対応するため、特定技能制度が導入され、外国人労働者の受け入れが可能となりました。特定技能「漁業」分野では、操業や選別、養殖関連などの業務に外国人が従事できるようになります。本記事では、特定技能漁業の対象職種、在留資格、企業側の受け入れ要件や制度上の注意点などを整理し、実際の採用・運用に役立つ情報をわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度と漁業分野が対象となった背景
漁業分野における人手不足と制度創設の流れ
日本の漁業分野では、長年にわたり人手不足が深刻化しており、特に沿岸漁業や養殖業では担い手の高齢化と若年層の減少が目立っています。長時間労働や季節変動の激しさといった業務特性もあり、日本人労働者の確保が困難な状況が続いていました。
こうした課題を背景に、政府は2019年4月、出入国在留管理庁の所管のもと特定技能制度を創設し、人手不足の著しい14分野で外国人材の受け入れを可能にしました。漁業分野はその一つであり、特定技能1号として外国人労働者を雇用できる制度的枠組みが整備されました。
制度の目的は、単なる人材補充ではなく、即戦力となる外国人が一定の技能と日本語能力を有したうえで、就業現場で活躍できるようにすることです。技能実習制度とは異なり、労働者としての明確な在留資格と就労の自由度が特徴です。
特定技能が漁業で活用されるようになった理由
漁業分野で特定技能が活用されるようになった主な理由は、技能実習制度によって一定の成果が出ていたことと、漁協や地方自治体が外国人材の必要性を強く訴えていたことにあります。
これまで技能実習制度のもとで外国人が漁業作業に従事してきた実績があり、その受け入れノウハウを生かせる点は、特定技能制度導入の大きな後押しとなりました。特定技能では、技能実習2号を良好に修了した場合、試験なしで特定技能1号への移行が可能となっており、制度間の連携も設計されています。
また、漁業特定技能協議会などが中心となって、制度運用に関するガイドラインや支援体制の整備も進んでおり、受け入れの実務的な準備が進みやすい環境が整っています。
政府としても、漁業の持続的発展を図るため、国際人材の活用は避けて通れない課題と認識しており、今後も受け入れ体制の柔軟な見直しが進められる見通しです。
特定技能漁業で認められている業務と職種内容
従事できる作業の範囲と主な職種
特定技能「漁業」分野において外国人が従事できる業務は、水産資源の採捕や養殖などに関わる作業全般が対象となります。対象となる職種は大きく分けて2つの業務区分に整理されています。
- 漁業(船上作業を含む、漁具の準備や片付けなど)
- 養殖業(餌やり・網交換・収穫・選別など)
これらの業務は、現場での体力作業が中心となるため、安全管理や天候による変動に柔軟に対応できる人材が求められます。また、船に乗って行う作業や夜間作業を含む場合もあり、受け入れ前に職務内容を明確に説明しておくことが重要です。
操業前の準備、漁具や資材の整備、漁獲物の選別・運搬なども含まれ、漁業協同組合と連携して行うことが多いのもこの分野の特徴です。
養殖業・市場関連作業も対象となるのか
特定技能漁業の中には、漁業だけでなく養殖業にも対応した作業が含まれていることが明示されています。具体的には以下のような作業が対象です。
- 稚魚の育成、管理
- 養殖網や設備の清掃・保守
- 出荷に向けた選別・梱包作業
ただし、市場での販売業務や、流通にかかわる事務作業などは対象外です。あくまで水産資源の生産段階に直結した作業範囲に限られ、業務範囲を逸脱する形での従事は制度違反とされる可能性があります。
また、作業内容によっては一定の専門知識が必要となるため、受け入れ企業側には丁寧な指導とマニュアルの整備が求められます。
技能実習との違いと移行のポイント
特定技能と技能実習は混同されやすい制度ですが、制度の目的と在留資格の性質が異なります。
| 比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転 | 労働力確保 |
| 雇用関係 | 実習先との実習契約 | 雇用契約に基づく労働者 |
| 在留期間 | 原則3年(最大5年) | 最長5年(1号)+更新制 |
| 移行要件 | 実習2号修了で移行可 | 試験合格または実習修了 |
特定技能1号へ移行するには、漁業分野の技能測定試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが要件となります。制度間の移行が比較的スムーズに設計されているため、既に技能実習生を受け入れている企業にとっては、特定技能への切り替えが現実的な選択肢となります。
外国人を受け入れるための条件と必要な対応
受け入れ企業が満たすべき主な要件
特定技能外国人を漁業分野で受け入れるには、企業側にも制度上の明確な条件や体制整備が求められます。特定技能制度は「即戦力人材の就労」を目的としているため、雇用者側の責任が非常に重要です。
主な要件
- 漁業分野における事業実態があり、安定した運営が確認されていること
- 外国人との間で特定技能1号に基づく雇用契約を締結していること(派遣不可)
- 日本人と同等以上の報酬水準で雇用すること
- 労働時間・休日・安全衛生・社会保険などの労働法令を遵守していること
- 支援計画の作成・実施体制が整備されていること(自社または委託)
とくに漁業は季節や天候に左右されやすいため、変則的な勤務や遠隔地での就労にも対応できる柔軟な雇用体制が必要です。漁業協同組合と連携した雇用モデルをとるケースも多く、地域全体での受け入れ体制整備もポイントとなります。
特定技能外国人の要件と試験・語学基準
外国人が特定技能「漁業」分野で就労するには、以下の2点の要件をクリアする必要があります。
- 漁業分野特定技能測定試験の合格
- 日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicの合格
これらの試験では、漁具の取り扱いや選別作業の基礎、現場で使われる日本語表現など、就労に必要な知識・語学力が備わっているかが確認されます。また、すでに技能実習2号を「良好に修了」している場合、試験を免除して移行することも可能です。
受け入れ企業は、合格証明や修了証の確認を行い、虚偽のない手続きで在留資格申請を進める必要があります。
登録支援機関・生活支援の体制づくり
特定技能外国人の受け入れでは、就労だけでなく生活面の支援も義務的に求められます。これを担うのが企業自身、もしくは登録支援機関との委託契約による体制構築です。
支援計画に含まれる主な内容
- 住居の確保と入居支援(契約同行、保証会社の紹介など)
- 日本語学習の支援や生活ルールの説明
- 公的手続き(役所、年金、保険など)の案内
- 相談窓口の設置とトラブル対応
登録支援機関を活用する場合でも、支援内容の実施責任は企業側にあるため、実態把握と記録の管理が必要です。漁業の現場では、遠隔地勤務や生活インフラが限られるケースもあるため、より丁寧な支援体制が求められます。
雇用形態と労働環境の整備に関する注意点
直接雇用と派遣の違いと制度上のルール
特定技能制度において、外国人労働者の雇用形態は**原則として「直接雇用」**でなければなりません。派遣形態での雇用は原則禁止されており、制度上も明確に定められています。
直接雇用とは、受け入れ企業(または漁業事業者)が外国人と雇用契約を直接締結し、給与支払いや労務管理を一貫して行う形態です。これにより、企業は外国人の労働条件や生活支援を適正に把握・実施することが求められます。
一部例外的に、漁業協同組合等を通じた共同雇用的な形式が認められることもありますが、派遣業者を介した雇用は制度違反に該当するため、注意が必要です。
労働時間・賃金・安全対策での実務的注意点
漁業は天候や海上の状況に左右される業種であるため、労働時間や休日に柔軟性が求められる場面もあります。しかし、特定技能制度の対象となる外国人労働者には、労働基準法を含む国内法の完全適用が原則です。
整備すべき主なポイント
- 労働時間・休憩・休日の明示と適正な管理
- 賃金の支払い方法、残業・深夜手当の明確化
- 漁船や施設での作業に関する安全教育と防護具の整備
- 事故発生時の対応マニュアルと保険加入状況の確認
また、業務に従事する時間が不規則になりやすいため、出勤・退勤記録や労働時間の把握を正確に行う管理体制の導入が不可欠です。
漁協との連携・受け入れ枠の運用管理
漁業分野では、個別企業だけでなく漁業協同組合や地域の漁業者団体と連携した受け入れ体制が一般的です。これにより、共同での住居確保や教育研修、安全管理などを行うことが可能になります。
一方で、受け入れ可能な人数には上限があり、以下のような制度上の規定があります。
- 受け入れ企業の従業員数に応じた特定技能外国人の受け入れ枠
- 在留資格の更新や変更の際の就業状況・支援実績の提出
- 複数の事業者による共同雇用形態をとる際の明確な役割分担と責任共有
漁協や関係機関と事前に運用ルールを確認し、計画的に採用・配置・管理を行う体制整備が重要です。また、地域ごとに異なる慣習や契約形態が存在する場合もあるため、協議会等のガイドラインを参考にしながら整備を進めましょう。
特定技能「漁業」分野で採用するメリットと今後の展望

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
深刻な人手不足解消と持続可能な人材確保
日本の漁業分野では、年々漁業従事者の数が減少し、高齢化と若年層の就業離れによる人手不足が深刻な課題となっています。季節や気象に左右される業務でありながら、肉体的負担も大きいため、国内人材の確保が困難な状況が続いています。
特定技能制度の活用により、即戦力となる外国人労働者を安定的に確保できる道が開かれたことは、漁業現場にとって大きな意義があります。
特に、以下のような効果が期待できます。
- 一定の技能と日本語能力を有する人材を計画的に採用できる
- 就労後の定着率が向上し、長期的な雇用も見込める
- 現場の高齢化対策や事業継続の基盤として活用できる
正しい制度運用を前提とした採用は、労働力不足の解消だけでなく、持続可能な水産業の土台作りにも直結します。
技術移転と地域活性化につながる可能性
特定技能外国人が漁業分野で継続的に就労することで、現場で培われた知識や技術の伝承が進みます。従来の技能実習制度と異なり、特定技能では「労働力」としての定義が明確なため、OJTを通じての技術移転が現実的に行われやすいのが特長です。
また、受け入れ企業だけでなく、地域全体が外国人材との関係を築いていくことにより、地域活性化への波及効果も期待できます。
- 外国人が地域行事や漁協活動に参加することによる地域交流の活性化
- 空き家の活用や住宅整備による地域インフラの再生
- 地域に根ざした雇用促進により、地元経済の安定化
こうした流れは、漁業における雇用モデルの多様化や新たな地域共生の形として注目されています。
国際交流・育成という新たな雇用観の広がり
特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の補充にとどまらず、国際交流や育成を通じた長期的な関係づくりにもつながります。
漁業分野では、語学や文化の壁が比較的高いとされてきましたが、支援機関や協議会を通じた制度設計が進んだことで、受け入れ環境は大きく改善しています。
外国人が地域に根付き、漁業を学び、働き続けるためには、以下のような姿勢が企業側にも求められます。
- 単純作業の担い手としてではなく、育成すべきチームの一員として接する
- コミュニケーションの積極的促進と日本語学習支援の強化
- 国際的な視点からの業務改善やサービス向上への活用
今後は、特定技能2号への移行や長期的な制度活用も視野に入りつつあり、制度の理解と適正な運用が、より良い人材活用と地域発展の鍵となっていくでしょう。
制度理解と適正な運用で漁業の未来を支える
特定技能「漁業」分野の活用は、慢性的な人手不足に直面する水産業界にとって、有効かつ現実的な解決策となり得ます。制度を正しく理解し、適切な雇用・支援体制を整えることで、外国人労働者が地域に定着し、持続的な雇用環境を築くことができます。単なる労働力ではなく、将来を担う一員として受け入れる姿勢が、漁業の安定と地域社会の活性化につながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/