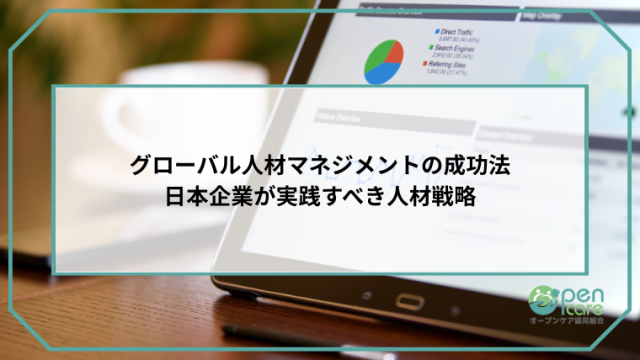建設・製造・外食業などで人材不足が深刻化するなか、即戦力となる外国人を受け入れられる「特定技能制度」に注目が集まっています。
本記事では制度の概要、導入手順、分野別活用事例、企業にもたらすメリットをわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度とは?仕組みと目的を3分で理解する

なぜ特定技能制度が必要なのか(制度創設の背景)
日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少の一途をたどっています。とくに建設・宿泊・介護・製造業などの労働集約型産業では人材の確保が困難で、業務の停滞や人件費の高騰といった深刻な問題を引き起こしています。
このような人手不足への対策として、政府は2019年4月に「特定技能制度」を創設しました。この制度は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、即戦力として受け入れることを可能にする新しい在留資格制度です。
これにより、従来の技能実習制度よりも実践的かつ長期的な雇用が実現できるようになりました。
特定技能1号と2号の違いとは
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号は、日常的な業務を担うことを前提とした制度で、最大5年間の在留が可能です。対象業種は16分野に限定されており、日本語能力試験(N4以上)と技能試験の合格が必要です。
一方、特定技能2号は、より高度な専門性と経験を要する職種に限定され、在留期間の制限がなく、家族帯同も認められています。現時点では建設分野と造船・舶用工業分野のみに適用されていますが、今後の拡大も視野に入れられています。
1号・2号の違いについては「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
対象となる16分野の一覧と選定理由
特定技能1号の対象として政府が定めた16分野は、以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
これらの分野は、いずれも「労働力不足が特に深刻であり」「一定の技能・実務能力を要する」ことを政府が認定した業種です。
たとえば、建設業では高齢化により技能者の引退が相次ぎ、若年層の就業が進んでいない一方で、設備や工具の扱いには一定の熟練度が求められます。介護業では対人サービス力と身体介護の両方が求められ、日本語能力の重要性も高いです。
これらの分野はすでに国内人材での供給が困難であると判断されており、制度設計においても試験制度・支援計画・受け入れ基準が他より厳格に設けられています。
人材不足を解消するために特定技能が有効な3つの理由
即戦力となる外国人材の活用が可能
特定技能制度の最大の特長は、外国人材を即戦力として雇用できる点にあります。特定技能1号の対象者は、日本語能力試験と業種別の技能試験に合格しており、一定の専門知識や業務経験を有しています。
そのため、受け入れ後すぐに現場で活躍できる可能性が高く、OJTなどにかかる教育コストや育成期間を抑えることができます。とくに建設・製造・外食業など、労働集約的な業界では、この“即戦力性”が採用の決め手となるケースが多く見られます。
制度設計によるミスマッチの低減
特定技能制度では、受け入れ企業に対し「支援計画の作成」「定期的な報告」「日本語教育の支援」など、一定の義務が課されています。この制度設計により、労使間の期待のズレや、文化・言語に起因する職場トラブルを防ぐことができます。
さらに、特定技能の受け入れには送り出し機関や登録支援機関が関与するため、採用時点でのマッチング精度も高く、いわゆる“採用のミスマッチ”による早期離職のリスクが軽減されるのです。こうした仕組みにより、受け入れ企業は安心して長期的な雇用戦略を構築できます。
他制度(技能実習・派遣等)との比較優位性
外国人材の雇用手段には、技能実習制度や派遣契約などもありますが、それらに比べて特定技能制度にはより高い自由度と実効性があります。技能実習制度は本来、国際貢献・人材育成を目的としており、労働力の確保を前提とした制度ではありません。
業種別に見る特定技能の活用事例とその効果【主要3業種】
建設業:若年労働力の確保と離職率の低下
建設業界では、ベテラン職人の高齢化が進み、若年層の新規就業者数が著しく低下しています。このため、人材の確保と現場の継続性が大きな課題となってきました。
特定技能制度の導入により、各地の建設会社では外国人の若年技能者を受け入れる事例が増えています。現場での作業を一定期間経験した技能実習生が特定技能へ移行するケースも多く、即戦力として定着しやすいのが特徴です。
また、外国人材はチーム意識が強く、長期雇用を望む傾向もあるため、離職率が下がる傾向にあるという報告もあります。
建設分野については「特定技能の建設分野とは?建設業で外国人材の受け入れ方法と注意点を徹底解説!」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
製造業:技能を持つ人材による安定操業
製造業では、産業機械や電気・電子、飲食料品製造など多様な分野で人材不足が深刻化しています。特定技能制度を導入した中小製造業では、ライン作業の効率化や品質管理の安定化など、即戦力人材によるプラスの影響が顕著に見られています。
特に特定技能制度は、対象業種ごとに技能試験が用意されており、採用段階で必要な基礎スキルを備えた人材を確保できるのが大きなメリットです。さらに、繰り返し作業をいとわず丁寧な作業をこなす外国人材の特性が、製造業の現場において非常に重宝されています。
飲食料品製造分野については「特定技能「飲食料品製造業」を徹底解説!要件・業務内容・受け入れのポイントまで」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
外食・宿泊業:多言語対応とサービス向上
訪日外国人客の増加と、国内飲食店舗の拡大により、外食・宿泊業界では接客人材の需要が高まっています。特定技能制度により、調理や接客に必要な技能を持つ外国人を採用できるようになり、現場では言語面や文化理解を活かしたサービス向上が実現しています。
たとえば、英語・中国語を話せるスタッフがいることで外国人観光客の満足度が高まり、リピーター獲得にもつながるといった副次的効果も確認されています。さらには、日本で働くことへの意欲が高く、責任感のある対応をしてくれることも多く、職場の雰囲気改善に寄与するケースもあります。
宿泊分野については「特定技能の宿泊分野とは?外国人材の宿泊業務での受入れ方法と人材採用の要件解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
特定技能外国人を受け入れるための5つのステップ
求人と募集の開始〜マッチングの流れ
まず最初に行うのが、求人と候補者とのマッチング活動です。特定技能人材は、送り出し機関・登録支援機関・海外の現地パートナーなどを通じて募集されるのが一般的です。
企業側は、募集条件や必要なスキルを明示し、候補者との事前面談や業務内容の説明を行います。近年では、Zoomなどを活用したオンライン面談が活用され、ミスマッチを未然に防ぐ取り組みも進んでいます。
必要な試験と在留資格の取得方法
特定技能での就労を希望する外国人は、「技能試験」と「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。業種ごとに定められた試験をパスした後、日本の受け入れ企業と雇用契約を結び、入国に必要な手続きを進めます。
企業側は、出入国在留管理庁への申請を通じて「在留資格認定証明書」を取得し、それをもとに外国人がビザを申請・取得します。
雇用契約・支援計画の作成
雇用契約書には、就業条件・労働時間・賃金など、日本人労働者と同等以上の待遇が記載される必要があります。加えて、企業は外国人材の生活支援を行うための「支援計画」を策定し、登録支援機関がその実行を代行することも可能です。
この計画には、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語教育支援などが含まれます。
住居・生活支援の準備と義務
外国人材が来日後スムーズに生活を始められるよう、住居の手配・家電の準備・役所手続きの同行などが求められます。特定技能制度では、企業がこれらを自力で行うか、登録支援機関に委託することが義務付けられています。特に日本語が不自由な段階では生活トラブルも起きやすいため、初期段階のサポート体制がその後の定着に大きく影響します。
受け入れ後の管理と報告義務
受け入れ企業は、外国人材の就労状況や生活状況について定期的に出入国在留管理庁へ報告する義務があります。また、契約内容に変更があった場合や、問題が発生した際には、速やかに所轄機関への届出が求められます。
これにより、制度全体の透明性と信頼性が担保され、悪質な雇用を防ぐ仕組みが整っています。
導入企業が実感する特定技能活用の3つのメリット
採用コストの最適化と採用安定化
中小企業にとって、採用活動にかかるコストと手間は大きな負担です。求人広告費や紹介料に対する成果が見込めない状況も多く、「求人を出しても応募が来ない」という声も少なくありません。
特定技能制度を活用することで、技能を備えた外国人材を明確な条件と試験制度を通じて採用できるため、採用活動の効率が大幅に向上します。また、登録支援機関を通じたサポートにより、採用から入社までのフローが可視化されているため、安定した人材確保につながります。
定着率の高さと職場への順応性
特定技能制度では、受け入れ企業に対して支援計画の作成が義務付けられており、生活支援や日本語学習のサポートなどが制度化されています。これにより、外国人材の生活上の不安が軽減され、職場への定着率が高まる傾向にあります。
さらに、受け入れ前のオンライン面談や、日本での生活経験を持つ人材の活用により、企業風土への早期適応も促進されます。現場からは「真面目に仕事へ取り組む姿勢」「責任感の強さ」が評価されており、戦力としての信頼も厚くなっています。
企業ブランドの向上と国際化の推進
外国人材の受け入れを行うことは、単なる人手不足解消にとどまりません。多様性を受け入れる姿勢は、企業としての先進性や柔軟性を外部に示すことになり、企業イメージの向上にもつながります。
特に観光業や製造業では、「外国人と共に働く会社」としてのブランドが、他企業との差別化要因になるケースもあります。また、外国人スタッフを通じて自社の仕組みやマニュアルを見直すきっかけにもなり、職場環境全体の改善や国際対応力の強化にも貢献します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度の今後と企業が備えるべき課題
制度改正と運用の最新動向
特定技能制度は2019年にスタートした比較的新しい制度であり、制度運用の透明性や実効性を高めるため、段階的な改正と見直しが行われています。たとえば、報告義務の簡素化(年4回→年1回)や、対象分野の追加見直しなどが進められており、受け入れ企業の負担軽減と制度の柔軟性が徐々に高まっています。
さらに、特定技能2号の対象職種の拡大や、技能実習制度の将来的な統合に向けた議論も活発化しています。企業側も、制度の変化に敏感に対応し、最新情報を把握したうえで計画的に受け入れを進めることが求められます。
受け入れ体制整備の課題と対策
制度上の整備が進む一方で、企業側の体制整備はまだ十分とは言えないケースも見られます。特定技能の外国人材が定着しやすい職場にするには、職場内コミュニケーションの工夫、教育体制の整備、日本人従業員への理解促進といった社内対応が不可欠です。
さらに、生活面の支援として、住居手配や交通アクセスの確保、日本語学習機会の提供など、実務面でのサポート体制の構築が必要です。これらを外部支援機関と連携して効率的に進めることが成功のカギとなります。
共生社会に向けた企業の責任と役割
外国人材の受け入れは、労働力確保だけでなく、地域社会や職場における「共生」の実現を目指す重要な取り組みでもあります。文化・宗教・言語の違いを尊重し、差別のない職場づくりを推進することが、企業の社会的責任(CSR)としても問われています。
単なる労働力としてではなく、組織の一員として外国人材を受け入れ、ともに成長できる環境づくりが今後さらに重要になっていくでしょう。
よくある質問(FAQ)

-
特定技能外国人と技能実習生は何が違うのですか?
-
技能実習制度は「国際貢献」を目的に技能を学ぶ制度であり、労働力の確保を前提としていません。一方、特定技能は「深刻な人手不足を補う」ことを目的とした在留資格で、即戦力としての就労が可能です。また、特定技能では日本語・技能試験の合格が必須で、業務内容もより専門的です。
-
外国人材の採用にかかるコストはどれくらいですか?
-
採用費用は、登録支援機関の利用や渡航・在留手続き費用を含めて変動します。オープンケア協同組合では企業様のご状況に応じた最適なプランをご案内しております。具体的なコストについて知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-
受け入れにあたって社内で準備すべきことは?
-
職場での指導体制・コミュニケーション支援、日本語教育の機会提供、生活面でのサポート(住居・役所手続きなど)が必要です。これらを支援計画に基づき、企業または登録支援機関が実施します。
特定技能で人材不足を解消し、持続可能な組織づくりを
特定技能制度は、日本国内で深刻化する人材不足に対し、即戦力となる外国人材を受け入れることで解決を図る、現実的かつ制度的に整備された手段です。制度の創設背景や対象となる業種、導入手順を正しく理解することで、自社にとって最適な人材確保の形が見えてきます。
実際に導入している企業からは、採用コストの最適化、職場定着率の向上、多様性を活かした企業文化の醸成といった成果が報告されており、特定技能は単なる「労働力確保」にとどまらないメリットをもたらしています。
今後、制度の改正や運用の進展に伴い、企業に求められる対応も変化していくことが予想されますが、柔軟かつ計画的に取り組むことで、持続可能な人材戦略の構築が可能です。
オープンケア協同組合では、特定技能制度に関するお問い合わせを随時受け付けております。導入に向けた不明点やご相談がある場合は、お気軽にご連絡ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/