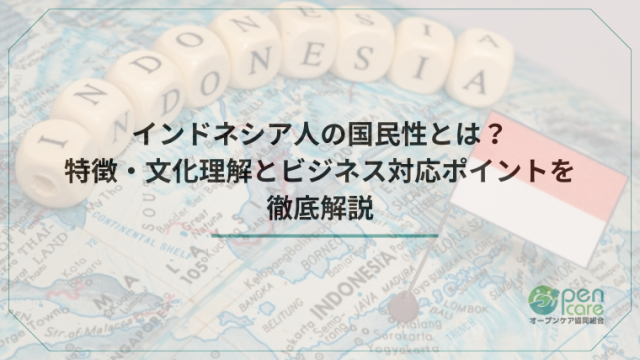- 「グローバル人材を採用したいけど、具体的にどう進めればいいのかわからない」
- 「文化や言語の違いで職場に馴染めるか不安…」
- 「採用してもすぐ離職してしまったらどうしよう」
そんな悩みを感じていませんか?
この記事では、グローバル人材採用の背景やメリット・課題を整理し、外食・製造業の事例を交えながら、採用から定着までの戦略プロセスをわかりやすく解説します。制度理解や支援体制の整備、費用設計のポイントまで網羅しているので、実務にそのまま活かせる内容です。これからグローバル人材の採用を検討している企業担当者の方に、ぜひ最後まで読んでいただきたい記事です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
グローバル人材の採用が注目される背景

日本企業がグローバル人材の採用を進める背景には、複数の社会的要因があります。まず少子高齢化による労働人口の減少が、人材不足を深刻化させています。特に外食や製造業などの労働集約型産業では若年層の確保が難しく、海外人材への期待が高まっています。
また、訪日観光客の増加や国際的な取引の拡大により、語学力や異文化理解に強い人材のニーズも拡大しています。海外市場を見据えた商品開発やインバウンド対応には、多様なバックグラウンドを持つ人材の力が欠かせません。
さらに、多様性を受け入れる組織は創造性やイノベーションの推進に寄与するという研究結果もあり、人手不足解消だけでなく競争力強化の観点からも採用が後押しされています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
グローバル人材の採用メリットと課題
グローバル人材を採用することで、企業には大きな利点が生まれます。異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、組織の視野が広がり柔軟な発想が育ちます。加えて、日本人だけでは補いにくい語学力や専門スキルを活用でき、国際市場対応力が高まります。外食業界では多言語対応が可能となり、製造業では新しい技術導入を後押しする場面も見られます。
一方で、課題も存在します。代表的なのは言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさです。生活支援や教育体制が不十分であれば離職リスクが高まります。さらに、在留資格の種類や労働関連法規の複雑さも大きなハードルです。例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザなど職務に応じた資格を選ぶ必要があり、正しい制度理解が欠かせません。
グローバル人材の採用を成功させる戦略プロセス
採用を成功させるためには、流れを体系的に設計することが重要です。まず、採用目的を明確にし、自社に必要な人材像を定義します。「人手不足を補う」だけでなく「どの業務を任せたいか」「どのスキルが必要か」を具体化することが出発点です。
次に、採用チャネルの選定です。
- 人材紹介会社を通じた採用
- 登録支援機関による包括的支援
- 海外大学との連携や直接応募
採用フローの設計では、応募から面接、評価基準までを透明性高く定めることが不可欠です。評価軸を日本人採用と同様に明確にし、差別的扱いを避けることが信頼につながります。
入社後は受け入れ・定着支援と教育体制が鍵です。職場ルールや安全衛生教育に加え、日本語研修や生活支援を含む包括的サポートが定着率向上に直結します。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度を活かしてグローバル人材を確保

国内の深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れは「特例的な施策」ではなく、企業経営における新たな必然となりつつあります。厚生労働省の発表によれば、外国人労働者はすでに230万人(2024年時点)を超え過去最高を更新しており、今後は300万人規模に拡大するとの見方も広がっています。特定技能制度は、こうした状況を受けて2019年に創設された在留資格で、一定の日本語能力と専門技能を持つ外国人材を受け入れるための仕組みです。
対象分野は介護・建設・外食業をはじめとする16分野で構成されており、これにより、人手不足が特に深刻な産業で外国人材の採用がさらに進めやすくなっています。
特定技能には、相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事できる「特定技能1号」と、熟練した技能を必要とする業務に従事できる「特定技能2号」があります。ここで留意すべきは、特定技能1号では家族帯同は原則認められておらず、家族帯同が可能となるのは特定技能2号へ移行した場合に限られるという点です。
すでに製造業や宿泊業などでは、外国人就業者が従業員の一定割合を占める状況が生まれており、企業にはグローバルな組織運営力が求められています。特定技能制度を活用すれば、人手不足を補うだけでなく、多様性を取り入れた職場づくりを進め、長期的な企業成長につなげることができます。これからの時代を見据え、積極的にグローバル人材の確保と育成に取り組むことが重要です。
国内企業の導入事例
外食業界のフィクション事例
参考資料 農林水産省:「外食業の特定技能外国人受入れ例」概要
東京都内で展開する全国チェーンの外食業の企業では、特定技能制度創設に先立ってグループ内に登録支援機関を設立し、採用から入社後のキャリア支援、生活支援まで一括して対応しています。
この企業では店舗スタッフとして接客や調理、衛生管理などを行う特定技能外国人が多数活躍。業務は日本人社員とほぼ同様です。
さらに、日本語能力向上のための教育アプリを提供し、業務と人間形成・自己成長をテーマに計画的な研修も実施。また、受け入れる店舗の日本人マネージャーにも研修を行い、相互理解を促進する体制を整えています。
このように、単なる採用では終わらず、教育と生活支援を融合した一貫体制で定着へ導いた点が成果につながった事例として描かれます。
製造業界のフィクション事例
参考資料 経済産業省:「製造業における特定技能外国人受入れ事例」
東海地方にある金属部品製造業では、まず技能実習を終えた者を優先的に特定技能の在留資格へ移行させる試みをスタート。そのうえで、鍛造や品質検査など専門作業を任せ、リーダー的な役割を担う存在に成長しています。
社内では人事部や生活指導担当者が日本語指導を実施。当初テキスト中心だった学習支援を会話重視へ転換し、プライベートや業務現場の両方で使える実践的な内容に変化させています。また、地域の国際交流協会が主催する日本語教室を活用し、社員OBがボランティアとして支援に関わるなど、社外との連携による学習支援も機能しています。
これにより、外国人材が業務に習熟し、教育とコミュニティ支援を通じて現場への定着を高めた体制として描かれます。
これらのフィクション事例に共通するのは、「採用を単なる入口にせず、教育・生活支援・現場理解までを包括的に行う」という点です。こうした全方位型のサポート体制が、定着と成果を支える鍵になります。
グローバル人材の採用を進める際の実務ポイント
グローバル人材採用で企業が見落としがちな点は、制度と運用の両立です。まず登録支援機関や人材紹介サービスを活用し、在留資格申請や生活支援を外部委託することで自社負担を軽減できます。
次に社内体制の整備です。異文化マネジメント研修を導入し、社員全体で受け入れる姿勢を育てることが協働促進につながります。
コスト設計も重要です。採用・教育・生活支援にかかる費用を整理し、助成金や補助金を活用することで計画的投資が可能になります。
さらに短期的な人手不足解消だけでなく、将来の幹部候補や海外拠点人材育成を見据えた長期戦略が不可欠です。こうした視点を持つことで採用の意味が大きく変わります。
まとめ
グローバル人材採用は、人手不足解消にとどまらず、組織の成長と競争力強化に直結する取り組みです。成功する企業は採用目的を明確にし、採用から定着支援まで一貫したプロセスを設計しています。外食や製造の事例でも、教育や生活支援が定着率を高め成果につながっていることが確認できます。今後の採用戦略を考える際は、外部機関の活用や長期的視点を取り入れることをおすすめします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/