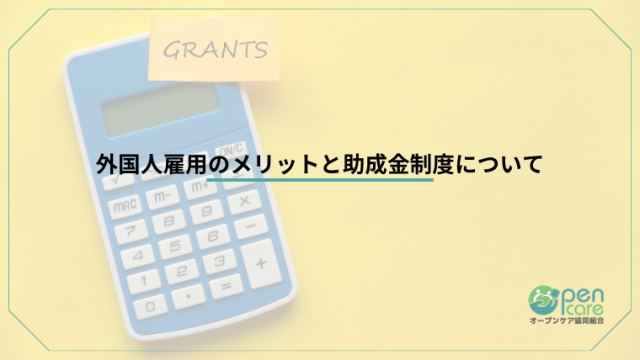せっかく受け入れた外国人材が早期に転職・離職してしまう。そんな悩みを抱える企業は少なくありません。特定技能制度では、一定条件を満たせば転職が可能なため、受け入れ後の対応が定着率を大きく左右します。本記事では、特定技能人材の離職リスクの実態と、流出を防ぐための具体策を紹介し、安定雇用を実現するためのヒントをお届けします。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度における転職リスクとは?
特定技能1号の在留資格は、技能実習とは異なり、条件を満たせば転職が可能な制度ですが、転職が制度的に許容されていることを知らずに受け入れている企業も多くあります。この認識のズレは、転職リスクに対する準備不足や対応の遅れにつながります。
企業が「転職できない制度だと思っていた」という前提で運用を行うと、離職後の対応が後手に回り、追加の事務負担やトラブルが発生しかねません。制度の根本を理解することが、まず転職リスクを防ぐ第一歩です。
企業側に発生する4つの実務的リスク
外国人材が転職した場合、企業には以下のようなリスクが現実的に生じます。
- 教育・採用にかかった初期コストの損失
- 登録支援機関との再契約や変更対応による事務工数の増大
- 「短期間で辞める会社」としてのレピュテーションリスク
- 他の従業員や地域社会への影響(不信・不安)
こうしたリスクは、単なる「離職」では済まない複合的な問題に発展します。特定技能外国人の受け入れには、コストだけでなく制度運用上の責任が伴うため、転職の想定は事前に織り込んでおくべき要素です。
離職理由に多いのは「制度への不満」ではない
転職が発生した際、多くの企業は「制度が悪い」と制度側に原因を求めがちですが、実際には生活環境・支援体制・職場との相性といった「企業側要因」に起因するケースが大半です。
たとえば、言語の壁による孤立感や、就業条件と実態のギャップ、サポート不足など、日常の中で蓄積された不満が転職という選択肢につながります。制度を正しく理解することに加えて、自社の受け入れ体制を客観的に見直す視点が欠かせません。
採用直後の転職は企業ブランディングにも影響
特定技能人材が早期に退職した場合、その情報は母国のコミュニティや他の求職者にも広がりやすいというリスクがあります。特にインドネシアやベトナムなど、SNSを通じた口コミ文化が強い国の人材では、受け入れ先企業の評判がダイレクトに拡散されることもあります。
「この会社は待遇が悪い」「サポートがない」といった声が出回ることで、今後の外国人採用活動にも影響を及ぼす可能性があるため、単なる一件の離職として軽視せず、採用ブランディング全体として対策を講じる必要があります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
転職されやすい企業の特徴と5つの要因
外国人との事前コミュニケーション不足
採用前に候補者と十分な対話や相互理解がないまま雇用に至ると、ミスマッチが発生しやすくなります。特定技能人材の中には、日本語での表現が苦手な方もおり、条件や仕事内容の細部を正しく理解していないケースもあります。
受け入れ企業が「言えば伝わるはず」と考える一方で、候補者側は「説明されていなかった」というような認識のズレは、信頼関係の喪失と早期退職につながりかねません。採用の段階から、Zoom面談や多言語資料による説明などの工夫が必要です。
仕事内容と実際のギャップが大きい
求人票や面接で伝えた仕事内容と、現場での実務内容に差があると、外国人材は「騙された」「聞いていた話と違う」と感じてしまいます。以下のようなギャップが、転職の引き金となります。
- 求人では「簡単な作業」と記載されていたが、実際には重労働だった
- 就業時間が実態と異なる(残業が多い、休憩が取りにくい)
- 担当業務が入社後に変更された
このようなズレを防ぐには、業務内容を写真・動画で事前に見せるなど、視覚的な情報共有が効果的です。
生活環境・支援体制の不備
外国人材の定着において、職場内の支援体制と同じくらい重要なのが、住居・生活環境の整備です。以下のようなサポート不足が、離職につながる大きな要因となります。
- アパート契約が自力では難しく、支援がない
- Wi-Fiやスマホ契約など通信環境のサポートがない
- ゴミ出しや公共料金の手続きなど、生活面の指導が不十分
特定技能制度では、こうした支援を担う登録支援機関との連携が推奨されています。支援を外部委託するか、社内に体制を整えるかの判断が重要です。
職場内の人間関係や文化摩擦
「技能面には問題がないのに、職場になじめなかった」という理由での離職も少なくありません。特定技能人材にとって、日本人スタッフとの人間関係の構築は非常に重要です。
声をかけてもらえない、指示が抽象的すぎる、休憩中に孤立してしまうなど、こうした日常の積み重ねが、職場への不信感を生み出します。文化の違いを尊重した接し方や、教育係の指名制度など、現場レベルでの配慮が転職防止につながります。
キャリアや昇給のビジョンが提示されていない
多くの特定技能人材は、「長く働けるかどうか」を重視しています。待遇だけでなく、将来的にどのように成長できるのか、スキルアップや昇給のチャンスがあるのかといったキャリアビジョンが見えない企業では、魅力を感じにくくなります。
- 昇給や職種変更の基準が曖昧
- 勤続年数に応じたインセンティブがない
- 特定技能2号など将来の選択肢が示されていない
こうした「先が見えない環境」では、他社への転職を選ぶ動機になりやすいため、キャリア設計の可視化が重要です。
流出を防ぐ企業づくりのコツ
採用前にすべきマッチング精度の向上
採用段階でのミスマッチを防ぐことが、最も効果的な転職リスク対策です。以下のような取り組みによって、候補者の業務理解と企業側の不安を軽減できます。
- Zoomによる事前面談で、仕事内容や人間関係の質問に応じる
- 作業風景や職場の様子を動画・画像で共有し、実務のイメージを伝える
- 翻訳ツールや通訳を使って、条件や勤務形態を明確に説明する
- 就労条件通知書を多言語で用意し、相互確認を徹底する
事前の情報提供を充実させることで、「聞いていた話と違う」といった初期の不満を未然に防げます。マッチング精度の高さは定着率に直結します。
外国人を雇用する際の手続きについては「【最新】外国人を雇用する際の手続きと注意点を解説 | 外国人材活用を支援するオープンケア共同組合」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
受け入れ後の定着支援(生活・教育・労務)
特定技能人材が「日本で働き続けたい」と思える環境づくりには、生活面の安定と安心感が欠かせません。住居の確保、日本語教育、日常生活のサポートといった分野での包括的な支援が求められます。
特に初期段階では、行政手続きやゴミ出しルールといった細かな点までサポートが必要です。また、職場ルールや労務上の注意点を適切に伝えることも、トラブル防止に効果的です。
教育面では、Eラーニングの提供や社内OJTの仕組み化など、日本語力の向上を支援する体制を整備することが理想です。生活・教育・労務の3本柱を揃えることが、離職の引き金を取り除く鍵となります。
評価制度とキャリアパスを明文化する
働く上での安心感と将来展望を提示するために、昇給やキャリアアップの仕組みを制度化し、視覚化することが重要です。以下のような仕組みを用意すると、外国人材の定着意欲が高まります。
- 勤続年数や成果に応じた昇給テーブルの提示
- 特定技能2号への移行支援や試験合格者への報奨制度
- サブリーダーや通訳担当など、社内ステップアップポジションの創設
- 業績や行動評価に基づくインセンティブ制度の導入
これらを「将来への道筋」として可視化することで、「ここで頑張れば報われる」という意識が定着します。目に見える評価制度は、転職の動機を減らす効果が大きいです。
外部支援機関を活用したサポート体制構築
企業単独で全ての支援を担うのは現実的ではありません。登録支援機関との連携や、外部の専門機関との協力によって、外国人材の生活・労務支援を安定的に実行する体制を整えることができます。
信頼できる支援機関を選べば、入国手続きから定着支援、日本語教育、緊急対応まで一貫して任せることが可能です。特にオープンケアのように、Zoom事前面談や生活インフラの整備も支援する機関は、転職リスクの根本にアプローチできる貴重なパートナーとなります。
社内負担を抑えつつ、定着率向上にコミットするには、外部機関の活用が不可欠です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
転職リスク対策に強い支援機関の選び方
サポート内容が「定着」に直結しているか
支援機関を選ぶ際、重要なのはそのサービスが「採用手続き」だけでなく、外国人材の定着支援にまで踏み込んでいるかどうかです。単なる形式的な書類代行や翻訳支援だけで終わってしまう支援機関も少なくありません。
以下のような支援が含まれているかを確認することが、転職リスクの低減につながります。
- 生活面の個別相談対応(家賃・携帯契約・通院など)
- 就業後フォローの定期実施(1か月・3か月・6か月)
- 定着を目的とした日本語教育や文化研修の提供
- 離職防止に向けた本人・企業へのアラート通知体制
定着率にコミットする支援設計がされているかを必ずチェックしましょう。
日本語・文化支援の実績があるか
言語の壁や文化の違いによる離職は、特定技能人材の転職理由としてよくある理由です。日本語研修の質や文化教育への取り組み実績がある支援機関は、こうしたギャップを緩和する役割を果たします。
たとえば、eラーニングや日本語能力試験(JLPT)対策講座、職場で使える日本語指導などが継続的に提供されているかは、選定時の大きな判断材料です。また、企業への日本文化理解サポートや、異文化マネジメントに関するアドバイスができる支援機関であれば、双方の理解が深まり定着率が格段に高まります。
初期費用・運用コストの透明性
支援機関を選ぶ際には、費用体系の分かりやすさと、長期的なコスト負担のバランスも重要です。中には、初期費用が高額だったり、追加オプションが多く実質的なコストが不明瞭なケースも見受けられます。
以下のような観点で比較検討することが推奨されます。
- 初期費用が明示されているか
- 月額料金に含まれるサービス範囲が明確か
- サポートごとの追加料金が発生しないか
- 契約期間や途中解約時の条件が明記されているか
透明性が高く、低コストで継続しやすい支援機関は、企業にとっても導入・継続しやすいパートナーになります。
Zoom面談など事前対応の有無も重要
近年、Zoomなどオンライン面談を活用した事前マッチングサポートを行う支援機関が増えています。このような取り組みは、採用前のミスマッチ防止に大きく寄与し、結果として転職リスクの軽減に直結します。
オンラインでのやり取りにより、候補者の日本語力や人柄、理解力を採用前に把握することが可能となり、企業側も安心して受け入れの準備ができます。また、採用候補者本人にも仕事内容や環境について確認する機会が生まれ、双方の納得感あるマッチングが実現します。
オープンケアのように、Zoom面談を標準対応としている支援機関は、採用成功率と定着率の両方を高める存在です。
まとめ
特定技能人材の転職は、制度上避けられないリスクではありますが、企業の受け入れ体制次第で大きく低減することが可能です。特に、採用前の丁寧なマッチング、受け入れ後の生活支援、キャリア設計の明示、そして信頼できる支援機関との連携は、転職を未然に「防ぐ」ための鍵となります。
外国人材の定着に成功している企業は、単に制度を利用するのではなく、制度の背景や人材の立場に寄り添った支援を惜しみません。採用から定着までの一連の流れを、自社だけで完結させようとせず、専門性のある登録支援機関と手を取り合うことが、安定した外国人雇用の第一歩です。
もし現在、外国人材の離職でお困りであれば、今一度自社の支援体制を見直し、外部の専門機関への相談を検討してみてください。オープンケア協同組合では、初期費用0円・月額2万円から始められる定着支援プランをご用意しており、Zoom面談や生活インフラ整備など、転職リスクを抑える仕組みを整えています。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/