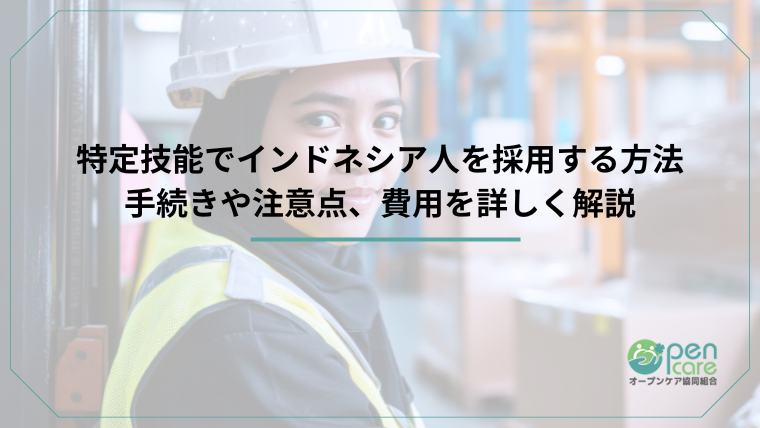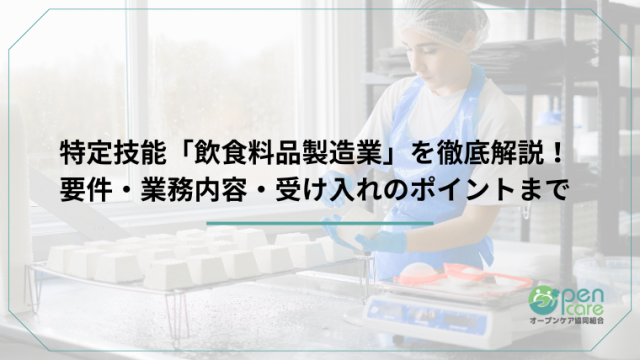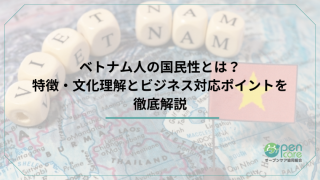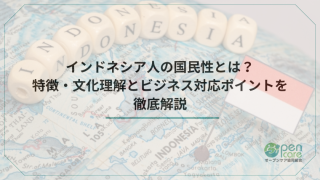- 「インドネシア人材を採用したいけど、手続きが複雑そうで不安…」
- 「費用はどのくらいかかるんだろう?」
- 「宗教や生活習慣への配慮も必要なのかな?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
本記事では、特定技能でインドネシア人を採用する方法を、手続きの流れ、費用の目安、注意点まで網羅的に解説します。インドネシア人材の特徴や強み、支援機関の活用ポイントについても整理しています。
これから特定技能人材としてインドネシア人の採用を検討している企業担当者の方に、役立つ情報が満載です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
インドネシア人特定技能採用が注目される背景

特定技能外国人におけるインドネシア人の受け入れ実績
出入国在留管理庁の統計によると、特定技能外国人の国籍別構成ではベトナムに次いでインドネシア人が多い傾向にあります。特に介護や外食業、建設などの分野での就労が目立ち、若い労働力として期待されています。
これは、日本語学習意欲が高く、日本社会への適応力を持つ人材が多いことが背景にあります。
今後はさらに在留者数の増加が見込まれており、企業にとって重要な採用対象国の一つとなっています。
インドネシア政府(MOM)との二国間協定の意義
日本とインドネシアは、インドネシア共和国労働省(MOM)を窓口とした二国間協定を締結しています。この協定によって、送り出し機関を通じた人材供給の適正化が図られ、不透明な仲介や不当な費用負担が排除されやすくなりました。
結果として、企業側は安心してインドネシア人材を採用できる仕組みが整い、採用プロセス全体の透明性が向上しています。
技能実習生・留学生から特定技能への移行が多い理由
インドネシアからは技能実習生や留学生として来日している人が多く、一定の日本語力や生活経験を持っています。そのため特定技能へ移行しやすく、採用後の即戦力化もスムーズです。
また、技能実習2号を修了している場合、特定技能への移行が制度上認められているため、企業にとっても信頼性の高い人材採用につながります。
こうした背景を理解することで、企業はインドネシア人材の強みを踏まえた採用戦略を立てやすくなります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度とインドネシア人材の基本
特定技能1号の16分野とインドネシア人が多い分野
特定技能1号の対象分野は16分野あり、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業が含まれます。
このうちインドネシア人が多く従事しているのは介護、外食業、建設、自動車整備などです。これらの分野は慢性的な人手不足が続いており、インドネシア人材の活躍が大きな支えとなっています。
特定技能2号との違いと在留期間
特定技能1号は在留期間が最長5年と定められており、永住を前提とした在留は認められていません。一方で、特定技能2号に移行できる分野では在留期間の更新が可能となり、将来的な永住申請も視野に入ります。
インドネシア人材は特定技能2号でも多く活躍しています。特定技能2号は建設や造船など11分野で利用でき、更新により長期雇用も可能です。これにより、長期雇用を見据えた人材確保が可能となります。
特定技能の在留期間については「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。
技能実習生から特定技能への移行ルート
技能実習2号を良好に修了した人材は、特定技能1号への移行が可能です。さらに、技能測定試験や日本語試験に合格すれば直接移行するルートもあります。すでに日本での就労経験があるため、企業にとっては採用リスクが低く、職場への定着も期待しやすい点がメリットです。
インドネシア人を特定技能で採用する流れ
採用準備と求人・雇用契約の整備
最初に求人条件の整理と雇用契約書の準備が必要です。特定技能制度では、労働条件が日本人と同等以上であることが求められます。また、登録支援機関を利用することで、申請書類の作成や労務管理のサポートを受けられます。
申請と在留資格認定証明書交付までの手続き
地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。処理期間は1.5〜3か月が目安とされているため、採用スケジュールには余裕を持たせることが重要です。書類不備があると再申請が必要になるため、専門的なサポートを活用するのが安心です。
入国後に必要な生活支援(住居・日本語教育・宗教配慮)
入国後は、住居確保、日本語教育、生活オリエンテーションが義務付けられています。特にインドネシア人はイスラム教徒が多いため、礼拝やハラル対応の食事など宗教上の配慮が必要なケースがあります。これらの支援を整えることで、定着率向上と円滑な就労につながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
インドネシア人特定技能採用にかかる費用
採用に必要な主な費用項目
- 登録支援機関利用料
- 送り出し機関に関する費用
- 渡航費・在留資格申請手数料
これらの費用は企業負担となるのが一般的ですが、利用する支援機関や業種によって金額は異なります。
費用が変動する要因と比較のポイント
費用の総額は、受け入れる人数、分野、地域、支援内容によって変動します。例えば、都市部と地方では住宅確保のコストが異なり、また介護分野と建設分野では支援の内容が変わるため費用差が生じます。
インドネシア人特定技能採用のメリットと注意点
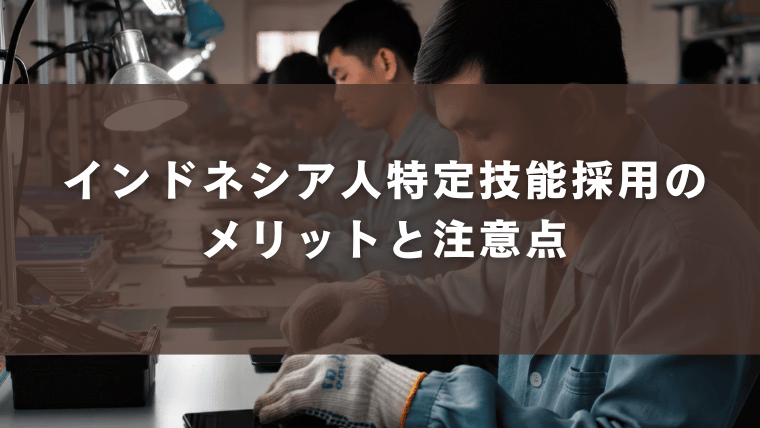
採用メリット(若い労働力・日本語力・文化的親和性)
インドネシアは人口の半分以上が30歳未満という若年層中心の社会であり、日本語学習にも積極的です。文化的に協調性が高く、日本の職場文化になじみやすい点も企業にとって大きな魅力です。
注意点(宗教・生活習慣への配慮、マッチング精度、国内外の需給)
- 礼拝やハラル対応などの宗教的配慮
- コミュニケーション不足によるミスマッチ
- 採用時期による人材需給の変動
これらを事前に理解し対応することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
オープンケア協同組合の支援内容と活用方法
オープンケア協同組合では、住居や生活支援、日本語教育、宗教面の配慮までワンストップで提供しています。さらに、Zoomを活用した事前面談により、採用前のマッチング精度を高めています。
これにより、受け入れ企業の負担軽減と定着率向上が期待できます。
こうした支援を理解した上で、最後に採用成功のためのまとめを確認しておきましょう。
まとめ|インドネシア人特定技能採用を成功させるために
インドネシア人は特定技能外国人の中でも存在感を増しており、介護や建設など幅広い分野で活躍しています。採用を成功させるには、制度の正しい理解、登録支援機関の活用、宗教や文化への配慮が欠かせません。費用や支援内容はケースによって異なるため、早めに相談することで安心して計画できます。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/