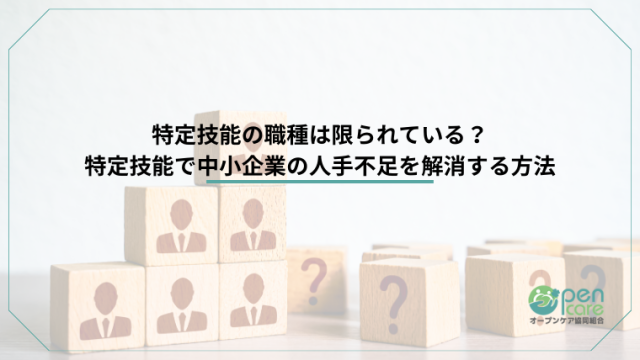日本の人手不足が深刻化する中、特定技能制度が2024年に拡大され、新たに4つの分野が追加されました。これにより、特定技能1号の対象分野は従来の12分野から16分野に拡大され、より多くの業種で外国人労働者の受け入れが可能となりました。
本記事では、特定技能制度の変更点、新たに追加された4分野の詳細、既存分野との違い、受け入れ企業が注意すべきポイントについて詳しく解説します。特定技能外国人の受け入れを検討している企業や関係者にとって、最新情報を正しく理解し、適切な採用計画を立てるための参考になれば幸いです。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度の拡大と最新の変更点
特定技能制度は、日本の労働力不足を補うために2019年に導入された在留資格制度です。これまで特定技能1号の対象は12分野でしたが、2024年3月の閣議決定により、新たに4分野が追加され、全16分野へと拡大されました。
特定技能の拡大による変更点
受け入れ拡大の背景
日本では、特に地方を中心に深刻な労働力不足が続いており、新たな分野への特定技能適用が求められていました。今回の拡大は、輸送業・資源産業・建築関連業種の人材不足解消を目的とした施策です。
特に、バス・トラックなどの運転士不足、森林資源の管理・活用のための人材確保が急務となっており、今回の4分野の追加により、より幅広い業界で外国人労働者の受け入れが可能になりました。
特定技能の対象分野と業務内容【全16分野】
特定技能1号の対象分野は、2024年の拡大によって12分野から16分野へと拡大しました。各分野ごとに求められる技能レベルや業務内容が異なるため、企業は事前に要件を理解した上で採用を進めることが重要です。
既存の12分野と業務内容
以下の12分野では、すでに特定技能外国人の受け入れが進められています。
- 介護
(介護施設での身体介助・生活支援) - ビルクリーニング
(建物内の清掃業務) - 素形材産業
(金属・鋳造・ダイカスト・溶接などの加工業務) - 産業機械製造業
(機械組立・部品加工) - 電気・電子情報関連産業
(電子機器・電気部品の製造) - 建設業
(土木・鉄筋・塗装・施工管理など) - 造船・舶用工業
(船舶の建造・溶接・塗装) - 自動車整備業
(自動車の点検・修理) - 航空業
(空港内のグランドハンドリング・整備) - 宿泊業
(ホテル・旅館でのフロント・清掃・接客業務) - 外食業
(飲食店での調理・接客) - 農業
(野菜・果物の栽培、家畜の飼育)
新たに追加された4分野と業務内容
2024年3月に閣議決定された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野では、従来の特定技能1号ではカバーされていなかった業務が対象となります。
- 自動車運送業
(バス・タクシー・トラック運転士) - 鉄道
(運行管理・設備保守) - 林業
(育林・伐採作業) - 木材産業
(製材・木材加工)
これらの分野では、業務に必要な資格要件や、日本国内のライセンス取得が求められるケースがあるため、企業側も受け入れ準備をしっかり行う必要があります。
新たに追加された4分野の要件と受け入れのポイント
2024年3月の閣議決定により、特定技能1号の対象として新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。これらの業種は、特に深刻な人手不足が続いており、外国人労働者の受け入れが今後本格化する見込みです。
それぞれの分野ごとに求められる技能レベルや受け入れの際の注意点があるため、詳細を確認していきましょう。
自動車運送業(バス・タクシー・トラック運転士)
【要件】
- 運転業務を行うため、日本国内の運転免許取得が必須。
- 日本語能力試験(JLPT)N3以上が推奨。
- 長時間労働の管理や安全運行のため、適切な指導体制が求められる。
【受け入れのポイント】
- 免許取得にかかる費用や期間を考慮した雇用計画が必要。
- 交通ルールや安全対策の研修を徹底することが重要。
- 企業側の支援体制(寮の提供・生活サポート)を整えることで定着率向上が期待できる。
関連記事:特定技能1号「自動車運送業分野」とは?受け入れ企業の要件、業務内容について詳しく解説
鉄道業界(運行管理・保守)
【要件】
- 鉄道運行に関わる業務のため、専門的な技術知識が必要。
- 保守作業などの業務は、建設業との共通点も多く、経験者の受け入れが有利。
- 日本語での指示理解が求められるため、N3以上が望ましい。
【受け入れのポイント】
- 鉄道インフラを扱うため、安全管理教育の徹底が不可欠。
- 深夜勤務やシフト勤務が発生するため、労働環境の整備が必要。
関連記事:特定技能の「鉄道分野」とは?概要や企業側の要件、業務内容について詳しく解説
林業(育林・伐採など)
【要件】
- 伐採作業などの危険を伴う業務が含まれるため、安全研修の受講が必須。
- 高所作業や重機の使用が伴うため、体力と技術が求められる。
- 地域によっては、冬季の作業制限があるため、労働計画の柔軟性が必要。
【受け入れのポイント】
- 森林管理の知識や機械操作の研修を事前に実施することが重要。
- 山間部での勤務が多いため、住居の確保や地域コミュニティとの連携が求められる。
関連記事:特定技能の林業分野とは?企業側の要件と受け入れる条件、業務内容を解説
木材産業(製材・木材加工)
【要件】
- 製材業務における機械操作スキルが必要。
- 特定の加工技術を要するため、事前研修の実施が望ましい。
- 品質管理の基準を満たすため、日本の生産管理方式を理解する必要がある。
【受け入れのポイント】
- 機械加工の経験者を優遇すると即戦力として活躍できる。
- 工場勤務が多いため、安全管理の徹底が必要。
関連記事:木材産業分野における特定技能とは?対応可能な業務と受け入れ要件を詳しく解説!
これらの分野では、既存の特定技能12分野とは異なる専門的なスキルが求められるため、企業側も研修や支援体制を整備することが重要です。
特定技能外国人の受け入れ手続きとビザ申請の流れ
特定技能外国人を受け入れるには、適切な手続きを踏んで在留資格を取得し、労働環境を整備することが必須です。特定技能1号の受け入れには、日本語能力や技能試験の合格が必要な場合があり、企業側も準備を徹底することが重要です。
受け入れまでの基本的な流れ
- 求人募集とマッチング
- 国内の求職者または海外の送り出し機関を通じて採用活動を行う。
- 特定技能の対象分野であることを確認し、雇用契約を締結。
- 技能試験・日本語能力試験の確認
- 特定技能の分野ごとに定められた技能評価試験の合格が必要。
- 日常会話レベルの日本語能力(JLPTN4程度)が求められる場合が多い。
- 雇用契約の締結と支援計画の作成
- 労働条件(給与・勤務時間・社会保険加入)を明記した雇用契約を作成。
- 生活・就労支援計画を策定し、外国人労働者が安心して働ける環境を整える。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 企業が出入国在留管理庁に申請し、COE(在留資格認定証明書)を取得。
- COEを取得した後、外国人本人が日本の大使館・領事館でビザ申請を行う。
- 入国・就労開始
- 日本到着後、在留カードを取得し、労働開始。
- 住居や生活支援を提供し、職場環境に適応できるようフォローアップ。
企業側が準備すべき書類
- 雇用契約書
(労働条件の詳細を記載) - 支援計画書
(住居・生活サポートの詳細を明記) - 企業概要書
(受け入れ企業の事業内容を説明) - 技能試験・日本語能力試験の合格証明書
特定技能外国人の受け入れには、単に労働力を確保するだけでなく、外国人が安心して働ける環境を整えることが不可欠です。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/
特定技能制度の拡大による今後の展望と課題
特定技能制度の拡大により、より多くの業種で外国人労働者の受け入れが可能となりました。特に、2024年に追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は、長年人手不足が問題視されていた業種であり、今後の労働力確保に大きな影響を与えると考えられます。
一方で、受け入れ拡大に伴い、雇用管理や職場環境の整備、外国人労働者の定着に向けた課題も浮上しています。
今後の展望
受け入れ拡大に伴う課題
- 言語の壁や文化の違いによる職場環境への適応
業務上のコミュニケーションを円滑にするための日本語教育の充実が必要。 - 労働条件の適正管理と長期的な雇用の確保
給与や労働時間が適正に管理されない場合、外国人労働者の早期離職が発生する可能性がある。 - 業界特有の資格取得や技術習得の負担
運転免許や安全管理の研修など、企業側の教育・指導体制の強化が求められる。
特定技能制度の拡大は、日本の人手不足を解消する大きなチャンスですが、適切な受け入れ体制を整えなければ、外国人労働者の定着は難しくなる可能性があります。企業は、単なる労働力確保ではなく、長期的な雇用の安定を見据えた採用計画を立てることが重要です。
特定技能の職種についてよくある質問
特定技能の職種拡大は今後も続く可能性がありますか?
特定技能の対象分野は、日本の労働市場の需要や業界の人手不足状況に応じて見直しが行われています。2024年の4分野追加に続き、今後もさらなる拡大が検討される可能性があります。政府の方針や業界の動向を注視することが重要です。
特定技能の追加職種は、どのような基準で決定されるのですか?
新たに特定技能の職種が追加される際には、厚生労働省や国土交通省など関係省庁の協議を経て決定されます。主な基準として、深刻な人手不足が続いているか、技能実習生からの移行が可能か、業界全体の成長見込みがあるかなどが考慮されます。
特定技能2号に移行できる新職種はありますか?
現時点で特定技能2号へ移行できるのは従来からの建設分野・造船舶用工業分野に加え2023年6月に、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、以下の9分野が追加されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
今後も新たな分野が追加される可能性もあります。政府は、外国人労働者の長期的な定着を促進するため、特定技能2号の対象職種の拡大を検討しており、今後の発表に注目する必要があります。
まとめ:特定技能を活用し、労働力の確保と業界発展を目指そう
特定技能制度の拡大により、従来の12分野に加え、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。これにより、より多くの業種で外国人労働者の受け入れが可能となり、深刻な人手不足の解消につながることが期待されています。
しかし、受け入れを成功させるためには、企業側が適切な体制を整え、外国人労働者が安心して働ける環境を提供することが重要です。
以下、特定技能外国人を受け入れる際のポイントです。
- 各分野ごとの要件を正しく理解し、適切な技能試験・日本語能力試験の合格者を採用する。
- 在留資格申請や雇用契約の手続きを適切に行い、不法就労を防ぐ。
- 職場での日本語教育や文化の違いへの配慮を徹底し、外国人労働者の定着率を向上させる。
- 業界特有の資格取得や研修体制を整え、長期的な戦力として活躍できる環境を構築する。
特定技能制度の拡大は、企業にとって新たな人材確保のチャンスであると同時に、適切な受け入れ管理が求められる課題でもあります。労働力の確保だけでなく、業界全体の発展を目指し、外国人労働者が安心して働ける職場づくりを進めていくことが重要です。
企業様の人手不足を解消する有効な手段として、特定技能を選択される企業様が増えています。本記事をご覧いただいた企業様についても人手不足の解消に向けて特定技能導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
特定技能の活用方法については特定技能の職種は限られている?特定技能で中小企業の人手不足を解消する方法をご参照ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!
- 相談しても受入が内定するまでは完全無料
- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します
- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応
外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!
\お客様相談センター(06-4708-6750)/